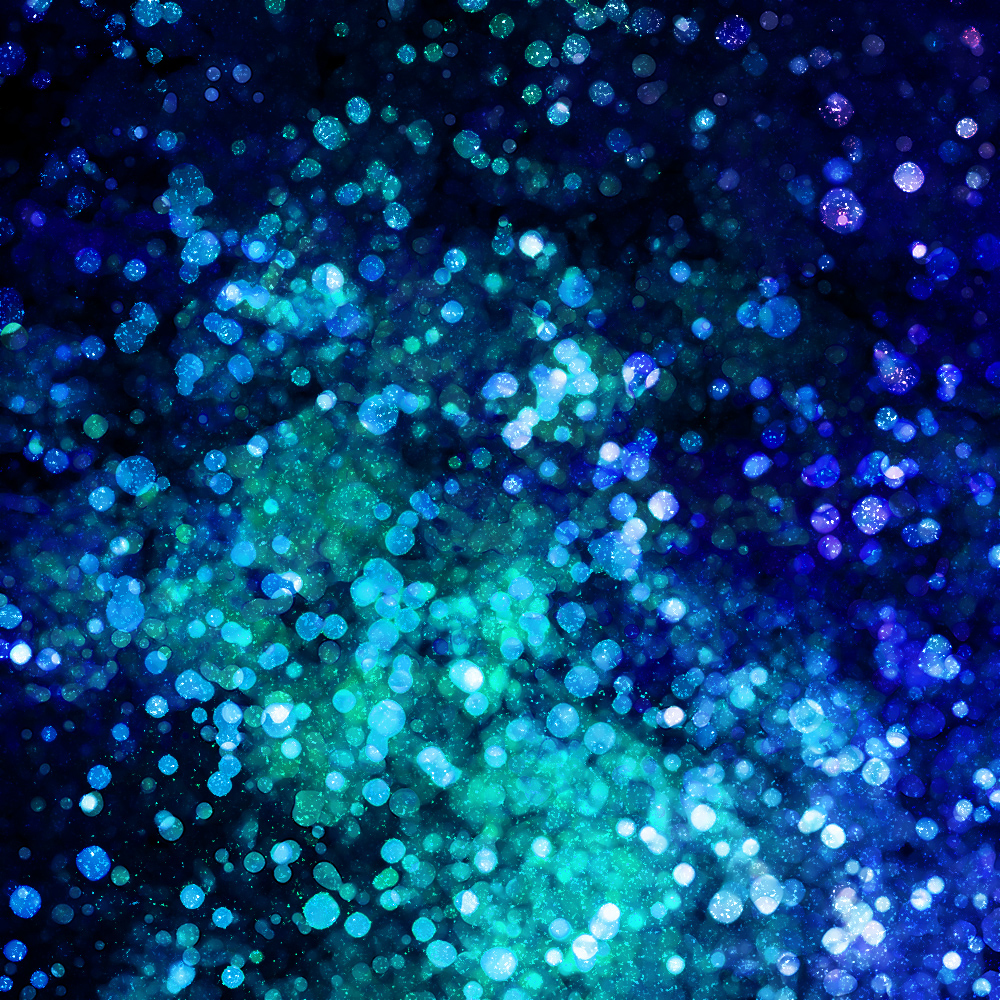
耽溺 後
昼前に本部塔を出てジェット機で3時間の距離にある西国の要塞にパラシュート無しで降り立ち、空から亜音速で落ちてきた化け物に恐慌状態に陥った兵士を適当にいなしながら人道的に良からぬ細菌兵器を製造ラインごと叩き潰すのと、逃げ惑う主要研究員とゴーサインを出した軍人をまとめて密室に追い詰めて「もうこんな危ないもの作っちゃいけません」と”説得”するのを30分で済ませて戦闘機を拝借し、行きより一時間早い帰還を五体満足で果たした傑が自室に戻ると、悦は出た時と同じようにゲーム機を抱えてリビングのラグに寝転がっていた。
「ただいま」
「……」
緩慢に傑を見上げる瑠璃色は熱を孕んで濡れている。片手に持ったゲーム機の画面はコンティニューを促す表示のままだ。キャビネットに乗った手入れ道具が詰まった箱に開けられた形跡は無いし、ローテーブルに投げ出されたお気に入りのナイフの位置も変わっていない。
穴だらけになったシャツを脱ぎ捨ててゴミ箱に突っ込む傑を、熱を持った視線がふらふらと追いかけてくる。いつも通りを取り繕う余裕も、目を反らしてそれを隠す意地も、薄っすらと頬を上気させた悦にはもう無い。
いい傾向だ。
本当に飲み込みが早くて可愛い限りだが、正確なタイムテーブルも条件付けの一つなので、今からベッドに連れて行くわけにはいかない。あの様子では昼もまともに食べていないだろうし、決して正解を教えられない”躾”の内容を必死に推測している今の悦は、自分で作った精神的な縛りでがんじがらめだ。いくら芯が強いとはいえ、あまり厳しくしても参ってしまう。
取り敢えずシャワーを浴びて硝煙と血を洗い流し、今後の段取りもあるので適当な服を着て、傑はリビングのソファに腰掛けた。ソファに背を向ける形で横向きに寝転んだ悦の後頭部を見ながら、髪を拭っていたバスタオルを首に掛ける。
「退屈そうだな、それ」
「……ん」
相変わらずの表示を続けている手のひらサイズの機械を指して言うと、微かに頷いた悦は旧型だが大事に使われていると解るそれから手を離した。普段の機敏さが嘘のようにのろのろと動く指先がカチン、とボタンを弾いて、悲壮感のあるBGMを止める。
「暇なら、俺と遊ぶ?」
「……」
普段なら「それ絶対俺が遊ばれるヤツだろ」とジト目で睨んで来る所だが、頭だけを動かして振り返った瑠璃色は隠しきれない期待と少しの怯えを含んで傑を見上げた。
「簡単なゲームだけど、それよりは面白いと思うぜ」
今の悦には、特に。
誘うように首を傾げて見せてから、傑は深くソファに座った自分の足をぽんぽんと叩く。起き上がった悦がのたのたと近づき、”躾”中と違って服を着ている傑の体を物言いたげにじぃっと見つめるのを腕を引いて背中を向けさせ、太腿ではなく足の間に座らせて、くたりと背中を預けて来る体温の高い体を抱きしめた。
「はぁ……あっ」
「ここ、咥えて」
ぺろりとTシャツを捲りあげても抵抗せず、閉じた両膝を擦り合わせる悦の口元にたくし上げた裾を近づける。お遊びなので命令では無くあくまでもお願いの形だが、勿論断られるとは思っていない。
「今から10分、離さないでちゃんと噛んでられたら悦の勝ち。離させたら俺の勝ち。簡単だろ?」
「ん……」
「やる?」
「……んん」
裾をしっかり噛んで咥えた蜂蜜色が躊躇いがちに頷いたので、傑はポケットから出した端末に10分のタイマーを設定して悦にそれを持たせてから、緩く腰を抱いていた掌をする、とみっしり中身が詰まった薄い脇腹に滑らせた。
期待に鳥肌立った肌の感触を楽しみながら両手を使って腹から胸までを撫で上げ、触って欲しそうに尖った乳首の周りをくるくると指先で撫でて少し焦らしてから、左右一緒に中指の腹で押し潰す。
「んぅううッ……!」
くん、と顎を上げた悦の体に力が入るが、この体勢ではいくら背を反らした所で逃げられはしない。寧ろ差し出すような格好になって弄り易くなったので、ご要望に応えてきゅ、きゅ、と緩急をつけて優しく摘んでやると、端末を持っていない方の悦の手が傑のシャツを掴む。
「ぅんっ、ん、んンっ……ふぅ、う……!」
「気持ちいい?」
「んっ……んぅ、ん……ッ」
「こっちも力抜けよ。その方が気持ちいいから」
不随意な震えと痙攣以外は身動ぎ一つ許さない”躾”の時と同じく、がちがちに緊張した腰から太腿を撫で下ろして囁くと、ぴくりと肩を跳ねさせた悦が振り返った。動いてもいいの、と問う不安げな瑠璃色に優しく目を細めて見せて、赤く色づいた先端を引っ掻く。
「ひぅんっ……ん、んーッ……!」
散々抑圧してやった分、陥落はあっという間だった。
かりかりと引っ掻かれるのに合わせて控えめに足を跳ねさせていたのは最初だけで、裾を離さずにいれば逃げるように体を捻っても、縋るように手首を掴んでも叱られないと理解してからは、愛しい恋人は一秒だってじっとしていなかった。
くにゅくにゅと押し潰されて身を捩り、外れた傑の手を引っ張って自分から敏感なそこに押し当て、すりすりと指の腹で撫でられるのにぱたぱたと足を動かしたり、かと思えば爪先までぴんと伸ばしてみたりと、いつになく素直な様子で与えられる快感に浸っている。
「ふー……ふーっ……!」
床に落ちた端末がアラームを鳴らす頃には、シャツを離してしまわないよう両手で自分の口を覆ぎながら、ぷくりと膨らんだ乳首を差し出すように傑の足の上に寝転んでいる有様だった。
「離さなかったから、悦の勝ちだな」
「ふぅう……っ」
端末を拾い上げながら鎖骨をくすぐると、いやいやと首を横に振った悦が小指を握った。もっと、と太腿から背中を浮かせながら、引き下ろした傑の掌を胸に押し当てる。
久しぶりに何の我慢もしなくていい状態で与えられる快感に、悦はすっかり溺れてしまったようだ。実際はシャツを噛んでいるので声も満足に上げられないし、一度だってイかせて貰えていないのだが、とろりと蕩けた瑠璃色はもう「シャツを離さずにいれば気持ちいいことをしてもらえる」ということ以外なにも解っていない。
仮初の自由を味わえば味わうだけ、それを制限された時が辛くなることくらい、そこらの子供でも解りそうな単純な理屈だろうに。バカな子ほど可愛いというのは真理だ。
「……もう一回やる?」
「んんっ……!」
自分で自分の首を締めていることなど露ほども気づかない悦に蕩けるように微笑んで、傑は電源を落とした端末をローテーブルの上に放り投げた。
3日目。
「あぁぁッ……や、だ、もうやだぁああっ!」
面白いくらい想定通りに、3度目の入れ直しの半ばで叫びながら暴れだした悦を、傑は腰を掴んでいない方の手で背中を押さえてシーツに縫い止めた。
「やだ、やだぁっ!はなして、こすってぇっ!」
「”待て”だって言ってるだろ」
「待てない、もうまてないぃ……っ!」
猿轡の代わりに着けた目隠しをシーツに擦りつけて外してしまった泣き腫らした瑠璃色に、あの強靭な覚悟はもう跡形も無い。
「嫌だ、って言って止めたんじゃただのプレイだろうが」
「も、いい、それでいい、からぁ!お願い、傑、すぐる……っ!」
「……あのなぁ」
はぁ、と大きく溜息を吐いて、背中に置いた掌にぐっと力を掛ける。頭の中は想定していた数倍の鋭さで嗜虐心やら征服欲やら性欲やらを煽る悦の姿に理性がぎりぎり音を立てて軋み、半端に腰を止めている所為で回路が2度ほど焼き切れていたが、幸いなことに傑は純血種だ。
どこぞの最高幹部を「人間にしては良く頑張っている」と上から目線で褒められる程度には内面と外面を切り離す術に長けているので、「ヤバい」と「可愛い」以外の語彙が吹き飛んだ思考を完璧に隠して、苛立ったように眉を顰めて見せた。
「躾けてくれ、って言ったのはお前だろ」
「でも、だって……!」
「あー、もういい。喋るな」
ひぅ、と喉を震わせる悦の弁解を雑に遮って傍目には乱暴に、実際は引き込もうと蠢く内壁の動きを完璧に読んだ針に糸を通すような繊細さでモノを引き抜き、悦の腰から離した手を枕元に伸ばす。
察した悦がやだ、やだ、と子供のように泣きじゃくるのを聞いていると自分が極悪人のように思えてくるが、仕方ない。これも世間的には同じ極悪人である可愛い悦の為だ。
今の悦にとっては焦らされたとしても”待て”の方が辛いので、お仕置きを引き合いに出して脅すことはせず、こうなることを予想して用意してあった布を丸めて開かせた口に押し込む。背中を押さえる手を膝に置き換えて上から猿轡を噛ませると、声量と同時に一気に抵抗が弱まり、反比例してぽたぽたとシーツに滴る涙の量が増えた。化け物を本気にさせるほど可愛いばっかりに、可哀想に。
「頭で覚えらんねぇのは解ったから、体で覚えろ」
「う゛ぅっ、うぅうう……!」
低い声で言いながら震える悦の体を仰向けにひっくり返し、同じく用意してあった3本目のベルトで手首から肘までを縛り上げる。意図して凍てつかせた視線に怯えて完全に抵抗を止めた両足を揃えて曲げさせ、腰から外した1本目のベルトで太腿と脛を纏めて縛り、その上から掛けた2本目のベルトを腰の下に通してぎゅっと絞め上げて、傑は顔を上げて悦と視線を合わせた。
「これなら集中出来るだろ?」
「ふっ、ふぅうッ!」
言外にいいから大人しく悶えてろ、と告げて、ぼろぼろと涙を零す瑠璃色を目隠しで塞ぐ。
「……はぁ」
目が見えなくなったことでようやく軋んでいた理性に多少の余裕が戻り、傑はシーツに座り込んで思っきり素の溜息を吐いた。もう少しでこの数日間の悦の頑張りを無駄にしてしまう所だ。
悦に見えていないのをいいことに「あー、危なかった」と天井を仰ぎ、ついでに焼き切れたまま適当に繋いでいた回路を3秒で修復して少し補強もしてから、傑はローションボトルの蓋を跳ね上げた。両膝を胸にくっつけるようにして拘束されている所為で随分コンパクトな姿になった悦がびく、と大きく震えるのを見ながら、苛立つ演技の一環で堰き止めていた下半身の血流を元に戻す。
自分で動かないよう自制させるよりも、動けないよう縛ってやった方が精神的な負荷は少ない。とはいえ、今日で3日目。結局2時間近く続けた昼間のゲームの甲斐あって、経験豊富なZ地区の男娼としての覚悟も意地もようやく折れた。更に人間の知覚情報の8割を占める視覚を奪う目隠し。昨日までとは違って完全に口を塞ぐキツめの猿轡。
どれだけ加減してやっても1時間が限度だ。
「んぅうぅッ、ぅう゛ぅーー……っ!」
今の自分の体内時計に自信が持てなかったので端末で時間を確認してから、傑は最高に可哀想で可愛い恋人を、何一つ満足させてやらないよう慎重に貫いた。
「ふ、ぶっ……ぅぶ……ぅっ!」
残り10分を切った所で呼吸すら覚束なくなった悦が自分の唾液に溺れ始めたので、猿轡と一緒に目隠しを外す。滴るほどに涙を吸った布は猿轡とそう変わらないくらい重い。
「……集中出来たか?」
「はぁ゛っ……は、……!」
舌を出して酸素を貪りながら、快感と酸欠で真っ赤になってしまった顔が微かに頷く。一番気持ちよくて辛い所を抉りも擦りもして貰えず、ただ圧迫され続ける感覚に強制的に集中させられた頭でどれだけ理解しているか怪しいが、返事が出来るだけ上等だ。
「いい子だ」
「ぁ……あ゛……っ」
その健気さに免じて残りの10分はおまけしてやることにして、悦と同じだけ”待て”を食らっている下腹部の血流を極度に制限して無理矢理萎えさせてから、傑はずるりと腰を引いた。中折れのようでどうにも情けないが、3日目ともなると完勃ちのままじわじわ抜くのはキツい。いくら純血種でも流石にキツい。
「す、ぐ……ぅ……っ」
「水飲めるか?」
「ん、……」
今日はこれ以上追い詰めるつもりは無いので腕と足のベルトを手早く解き、ついでに短くなったキャンドルの小さな炎を指で揉み消して、傑はサイドボードに乗せていたペットボトルを抱き起こした悦の口元に近づけた。霞がかった五感全てで注意深く傑の気配を探っていた震える手が、常温のスポーツ飲料水に触れる寸前でぱたりとシーツに落ちる。
意識も半分トんでいるような状態だろうに、ここからは”事後”だと確信出来るまで緊張を保ち続ける様子が痛々しくてとても可愛い。
「今日は流すだけにしような」
「ひぅ……っ」
「明日は好きなだけ自分で弄ってイイから」
昨日と一昨日のシャワー責めがよほど辛かったのか、抱き上げた途端に泣きそうな顔をする悦を宥めながらベッドを降り、すっかり習慣になりつつある「恋人じみた」手厚い後始末の為、バスルームに向かった。
「……変わるもんだな」
ロックグラスの中の氷をからんと手遊びに鳴らしながら、傑はぽつりと独りごちた。
皇国から飛行機で東に5時間の位置にある、観光を主産業にする小国。その首都の外れにある小洒落たバーのカウンター席に座った藍色の視線の先には、画面を埋め尽くす文字と記号がスクロールし続けるノートパソコンがある。
グラスを持ったままの手でいくつかのキーを叩いて延々と伸び続けていた文字列を停止させ、警告音と共に5つのポップアップが表示されるのを確認してパソコンを閉じ、傑はグラスの中身を飲み干した。
温かい食事によって味蕾の職務怠慢が改善されたのか、こんなありふれた安酒すらも妙に美味く感じる。録音のモード・ジャズが内側からの軋む音に煩わされることのない聴覚に、L字のカウンターを彩る飴色の木目が歪まない視覚に心地いい。
突き詰めてしまえばたった1つ、散大していたベクトルの方向が定まっただけなのに。ただそれだけで、本当に世界は変わるものだ。
「”寝て醒めた後に、”ってやつか」
この国で生まれた古い舞台の一節を引用しながら冗談めかして笑う傑に、酒瓶が並ぶ棚に凭れた愛想の悪いバーテンは明後日を向いたまま、答えなかった。
それに軽く首を竦めて、傑は足の長い椅子から腰を浮かせてグラスを置いた手を伸ばす。相変わらずこちらを見ないバーテンの左肩の向こう、整然と並んだ酒瓶の一本を抜き取って座り直した所で、何本かの瓶とグラスを道連れにしながらバーテンがずるずると傾いた。
脛骨を折られて明後日を向いた死体が倒れる重い音に、甲高い電子音が重なる。
「はいよ」
『傑……』
「よぉ、鬼利」
頬杖をついていた手を伸ばして着信に応じた傑の気楽な声に、3本のケーブルでパソコンに繋がったままの端末が重々しく溜息を吐く。
珍しく素直に忌々しげなその声にくく、と喉を鳴らして笑い、傑は封を切った酒を瓶ごと呷った。
「イイ腕してるな、あのガキ」
『……お陰様で、顔を青くしているよ。3ヶ月を無に帰されたって』
「へぇ、そりゃ凄い」
今しがた叩き潰したあのシステムを3ヶ月で構築したのなら本物だ。ころころ変わる派手な髪色はハッタリじゃなかったんだな、と素直に感心する傑に、端末向こうの”飼い主”はもう一度深く溜息を吐いた。
『どういうつもり?』
「十四隊、龍鱗楼一家、管理難度」
『……』
いちいち説明するのが面倒なので要点だけを話すと、人間にしては高性能な脳を積んでいる最高幹部が黙り込んだ。同族相手にしか使ったことの無い不親切な話法のシステムと、それを今日この場で初めて用いた傑の心情を鬼利が理解するまで、約3秒。
「あと、迷惑かけたお詫び」
『……気色の悪い……』
期待通りに化け物の意図を汲んでくれた脆弱な人間が、珍しく何を取り繕う事もなく心の底からの声でそんなことを言うものだから、傑は思わず声を出して笑った。
『……ご機嫌が麗しいようで何よりだよ。”彼”の状態は?』
「砂とサボテンが装置の舞台には間に合う」
『まさかとは思うけど』
「この程度でわざわざ裏取るかよ。俺のことは割と正面きってナメてくるよな、お前」
『信頼の証と思ってくれていいよ』
「書き割り相手に?いい性癖だな」
『……はぁ……』
目のいい片割れと一緒に引き篭もっている箱庭の完成度を含めて賛辞を贈ると、面倒臭そうに溜息を吐いた頭のいい方がカツン、と万年筆で机を叩く。
『……こういう形の”進化”は望んでいなかったよ』
「だろうな」
手駒の”劣化”を喜ぶ指し手はいない。そのゲームに命以上のものが懸かっていれば尚の事そうだ。だからこそ、この”飼い主”には考え続けるよう釘を刺しておかなければならない。
崩壊寸前の兵器から死に様の決まった生き物に劣化した化け物の、一番上手い使い方を。
「お前ならすぐ慣れる。明日の昼には戻るから、土産話はその時にな」
『明日?』
「何事も緩急が大事だろ?」
『……同情するよ』
「酷ぇな」
血の一滴も空薬莢の1つも無くカウンターとテーブル席に突っ伏している15の死体にではなく、自室に残してきた恋人を心から憐れんで切れた端末に、傑は瓶を傾けながら苦笑する。
「よろこばせたいだけなのに」
軽薄な笑みに似合わず真摯に響いたその言葉を、明後日を向いた死体だけが聞いていた。
4日目。
優れた体幹が見る影もないふらふらとした足取りで寝室に入った悦は、そのままの足でサイドボードの前に立つと、そこに乗ったアロマキャンドルの残骸を床に払い落とした。
最下段の棚を足で引き出し、中から真新しいキャンドルとライターを取り出して、乳白色に薄いオレンジでマーブル模様を描いたそれに火を点ける。芯が燃える焦げ臭さを覆い隠す、甘酸っぱくてどこか苦い香り。
4日前までは空っぽだった2段目の棚を手で開けて中の物をシーツの上に放り投げ、はぁ、と震える息を一度吐いてから、悦は羽織っていたバスローブを床に脱ぎ捨ててベッドに上がった。
「んんっ……」
シーツを裁断した四角い布を紐状にして口に咥え、3本の中で一番長いベルトを腰に巻いて端をヘッドボードの装飾に括り付けて、それがぴんと張る位置で引き寄せた枕の上にうつ伏せにぼすんと倒れ込みながら、真新しいローションボトルの蓋を指で跳ね上げる。
「ふ、……ふー……ッ」
止まりそうになる息を努めてゆっくり吐き出しながら、悦はシーツから持ち上げた腰に直接ローションを垂らし、じっとりと肌を伝うそれを掬い取った中指を慎重に奥に埋めた。
言っていた通りに仕事に出掛けて戻らない傑が、この3日間必ず”躾”を始めていたのと同じ時間に、同じ場所で、していたのと同じ様に。
「ん、ふっ……んんぅ……!」
絶対に傷をつけないように細心の注意を払って、慣れたそこを慣れない手付きで解しながら、悦はベルガモットが染み込んだ灰色のシーツの上でぎゅっと目を閉じる。
伊達にシーツの上を主戦場にして生きて来ていない。こんなことはあらゆる意味で何の慰めにもならないと、ちゃんと悦は理解していたが、解って止められる程度の泥沼ならあんなに無様に泣き喚いたりしない。
悦自身のそれよりも長い指の記憶をなぞって動かした指の先で、薬を入れられたように敏感になった膨らみがこりこりと潰れる。
「んぅうっ……ん、んン、……ぅうぅ……!」
じん、と走った甘い電気に揺れようとした腰をベルトに引き戻され、つい加減無しに押し潰していた指を引き抜いた。どぷりと掌に垂らしたローションを絡めて入れ直し、きゅうきゅうと締め付けてくる粘膜の中でそっと第二関節を曲げて、呼吸に合わせて緩やかに膨らみを押す。
初物相手のような丁寧で緩慢な、体どころか頭の中まで溶かすようなやり方は、勿論今は居ない傑を真似たものだ。少しでも壊され難くする為にローションまで仕込んで下準備された淫乱を、こんな手間をかけて悠長に解すような男は、少なくとも悦が知る限り他に居ない。
「ふー……っふー……!」
嗜虐的に冷えた外郭の内にどろどろした灼熱を飼い慣らしながら、まずはローションを絡めた長い中指一本でじっくり熱を持った粘膜をくすぐる。小波のように広がった甘い痺れに頭から爪先までどっぷり浸された頃に人差し指が、大人しく開いていた両足がびくびくと痙攣するようになってやっと薬指が増やされ、掌を伝って流し込まれた人肌に温いローションを丹念に塗り広げていく。
とろとろに解された内壁のどこが気持ちいいのか、どうされるのが一番堪らないのか、1つ1つ丁寧に思い知らされてようやく、指が抜かれる。
瞳の内側にある熱量そのままに硬く滾ったモノが、それを受け入れる為だけに在るような有様にされたところに押し当てられて、そして。
―――”待て”。
絶望的なまでの性能差が生む圧力をたった一言で表して、極限まで飢えさせられた何もかもを一欠片だって満たさないようにゆっくりと、悦の身も心も屈服させるのだ。
「ふッ……―――!」
残酷に甘い声を思い出しただけで浅い絶頂が白く頭の中で弾け、悦は自由な手で千切れるほどシーツを握りしめる。
空気を甘酸っぱい香りに満たしても、一人きりのシーツの上でその残骸を噛んでも、丈夫なベルトで震える体を縛り上げても、あの声や指や熱をいくら鮮明に思い出して再現したって、この飢餓感は満たされない。
精々浅くて軽い絶頂にほんの一瞬救われたような気になって、すぐにその倍の深さで叩き落されるだけだ。ちゃんと解っているが、解っていて止められるような浅い泥沼なら始めから落ちていない。
「ぁう、う……っ」
今は辛うじて残ったこの正気も、きっと一時間と保たずに擦り切れるだろう。気休めだということすら解らなくなって、冷たい革や布の感触に藍色の面影を探しながら、記憶に残るその姿に縋り付く。自分からねだって与えられたものも満足に受け止めきれない惰弱さのままに、みじめに泣き喚きながら。
その内に力尽きて啜り泣きながら意識を失った元男娼の姿は、きっとその肩書きの分だけ倍増しで無様だ。
呆れられるだろうか。嘲笑われるだろうか。
悦自身が一番嫌いな悦の救いようもなく弱い所を、多少崩れたって桁違いに強い藍色が、見たら。
あの完璧に美しい化け物は、
「……すぐ、る……っ」
……よろこんで、くれるだろうか。
観光名所の一つである朝市をのんびり回って形は悪いが味の良いお土産をいくつか選び、予定より半日遅い飛行機で戻った傑を、鬼利はその顔と抱えた紙袋を睨みつけながらもう一度「気色悪い」と評した。
自覚はあったので「羨ましい?」と茶化して閉口させてから自室に戻り、瑞々しい野菜や果物を紙袋から冷蔵庫に移して、先にシャワーを浴びる。結局朝方まで居座ったバーの残り香を綺麗に洗い流し、脱水症状の危険性を身に沁みて知っている悦が常備しているスポーツ飲料水のペットボトルを2本片手に提げて、ベルガモットが溢れ香る寝室の扉を開けた。
「……は、」
目の前に広がった光景に思わず、上擦った声が漏れる。
その為に選んで敷いた灰色のシーツは、零れたローションやその他の液体で半分以上の面積を濃い色に濡らしてぐしゃぐしゃになっていた。空になって転がったボトルの数は2本。猿轡や目隠しに使っていたのと同じ布がマットレスの縁に引っ掛かり、シーツの合間にはいつか使ってそのままサイドボードに入れていた、銀色のマドラーまでもがローションまみれになって転がっている。
そして、ヘッドボードに繋がれたベルトの先で、どろどろに濁った瑠璃色が瞠目して傑を見上げていた。
「愉しそうだな」
吊り上がる口元を隠そうともせずに言えば、その蜂蜜色の髪の一部までも透明な粘液に濡らした可愛い恋人が、びくりと大きく震える。リードのように腰に巻き付いた以外にも、両腕が手首の位置で、右足が折り畳んだまま太腿の位置で、それぞれ白い肌に映える黒いベルトで絞め上げた格好のまま。
「ち……ちが……っ」
「違わねぇだろ」
力なく首を振る悦の言い訳を遮って、着ていたシャツを頭から脱ぎ捨てながら膝でベッドの上に乗り上げる。傑の気配を察知して気絶から飛び起きるほど鋭敏な癖に、逃げるでも、皺の寄ったシーツに隠れるでも無く、ただその場で震えながらきゅっと体を丸める仕草は無力な獲物そのものだ。この上更に愛らしさを上乗せしてくるポテンシャルの高さに目眩がする。
「こんなモンまで引っ張り出して」
「あっ……!」
「そこら中びしょびしょに濡らすくらい愉しいこと、してたんだろ?」
拾い上げたマドラーをベッドの外に投げ捨てて、羞恥と期待に体中をほんのり上気させたご馳走を真上から両腕の中に閉じ込めた傑は、ようやくそれを頭から喰らえる捕食者の愉悦に目を細めた。
「俺もまぜろよ、悦」
5日目。
ヘッドボードに凭れた自分の体を椅子代わりに悦を両足の間に座らせて、折角なので腕と右足を縛るベルトは解かないまま、傑は最後の一本になったローションで濡らした掌を震える内腿に滑らせた。
「あーあー、溢れてきてんじゃねぇか」
「ひあぁ……ッ」
「……俺の物に傷つけてねぇだろうな」
「な、いっ……つけ、てなぃ……!」
流し込まれたローションが溢れるそこに中指を埋め、確かめるようにぐるりとナカを撫ぜながら低い声を出すと、びくりと肩を竦めた悦が首を横に振る。物覚えのいい可愛い恋人のことだ、きっと傑の動きを懸命になぞってたっぷりローションを使い、優しく優しく自分を追い詰めていたのだろう。
「ホントか?お前いっつも荒いだろ」
「す、傑がして、くれるみたい、に……ゆっくり……っあぁぁ……!」
「ゆっくり、ね」
「される」ではなく「してくれる」と言う辺り、本当に悦はよく解っている。普段の命知らずな言葉遣いとのギャップが素晴らしいので、ご褒美にすっかり敏感になった縁につぷつぷと割り開かれる感触を味わわせてから、入り口から順番にイイところを苛めてやることにした。
まずは一番浅瀬、皮膚と粘膜の境目を、たらたらと零れてくるローションを塗り込めるようにして優しく解す。貞淑に締め付けてきていたそこがはしたなく口を開けたら少し指を進めて、次は悦が特に好きな前立腺を。
「あ、あっ……はぁあぁぁ……ッ!」
張り詰めたしこりを数回押し上げてから形を確かめるようにぐるりと周囲を撫で、焦れた悦が泣き出したら、ローションで滑りの良くなった指先でこりゅ、くりゅ、と転がす。イかせてしまわないように間隔を空けて繰り返し、大きく広げられた内腿の痙攣がいい具合になった所で、指で届く一番奥、精嚢と膀胱を指の腹で押し上げた。
「ひぅっ、んぁ、あ、あっ!」
「次は?」
浅いピストンで突き上げる度にぴゅく、と先走りを零す裏筋を撫で上げながら聞くと、手放しに喘いでいた悦がぎこちなく傑を振り返る。快感と焦燥と期待と怯えと、雄の欲を刺激するなにもかもを詰め込んで蕩けた瑠璃色から、じわりと涙が溢れた。
「あぁっ……つ、つぎ、はぁ……っ」
床に転がったマドラーを見た悦が、手を止めた傑のモノをすり、と腰で撫でる。
「指じゃ、とどかない……とこ……!」
「…………はぁ」
ぞぞぞ、と背筋を這い上がったものを誤魔化すために溜息を吐いて、傑は怒らせたのかと首を竦める悦のナカから指を引き抜いた。
……ヤバい。保たない。
「な、なんで……っ」
「”待て”」
なんで止めるの、と涙声で追い打ちをかけてくる悦を雑に大人しくさせ、指を濡らすローションを物ともせずに腕と足のベルトを引き千切りながら、凭れていたヘッドボードから背を離す。ひっくり返した体を膝立ちにさせて切っ先を押し当て、そのまま突き上げそうになるのを軋む理性で辛うじて押し留めながら、傑はもう一度熱の籠もった息を吐いた。
悦が溢れるほどにローションを注いで一人遊びをしていたお陰で、柔らかく蕩けたそこはしっかり濡れている。傑自身はまだ中指一本しか入れていないが、一番気をつけなければならない入り口は十分に解したし、これ以上は悦がまたガチ泣きしそうだし、そんな顔を見たら今度こそ傑の方の理性が弾け飛ぶだろうから、まぁ、いい加減頭も回らなくなってきたことだし、いいだろう。
「す、ぐる……?」
「……悦」
ちゅうちゅうと押し当てた先端に吸い付きながらも、流石の覚えの良さできちんと”待て”をしている悦の腰を両手でしっかり掴み、傑は可愛い恋人が一番気に入ってくれている熱に掠れた低い声で、その期待に応えた。
「”よし”」
「え……ぁ゛っ―――!?」
言うと同時に腰を引き下ろし、一気に根本まで貫いた悦の体が、一拍の間を置いて弓なりに仰け反る。
「っッ―――――!!」
「ぐ……っ」
声も出ない絶頂の深さを物語るようにギリギリと折られそうに絞り上げられ、思わず呻き声が漏れた。情けないと自嘲する余裕も無い。持っていかれないようにするだけで精一杯だ。
「―――っは、……はあ゛っ……!」
仰け反ったままがくがくと痙攣していた悦の手が傑の髪をわし掴み、引っこ抜く勢いでそれを引き寄せて無理矢理に反っていた体と頭を戻す。薬物によって限りなく近い所に引きずり上げられたことはあっても、酩酊も混濁もしていない意識でそれを味わうのは初めての筈だ。
大きく見開かれたままの瑠璃色が、天然物の脳内麻薬と快感のみに深く深く犯されながら、傑を見る。
「たか、い……っ!」
「……そーだな。気持ちいいだろ?」
安心させる為に平然とした声で答えると、未だに引かない波に怯えた悦がぎゅうっと首に両腕を回してしがみついてきた。以前の悦なら一人きりで体を丸めてやり過ごしていただろうから、こうして自分から縋って来るだけでも目覚ましい進歩だ。この数日散々抱きつかせて慣れさせた甲斐があった。
「し、らな……っぁ、また、まだ、……!」
「ゆっくり息しろ、大丈夫だから」
「っひ……ひぐ……ッ!」
「大丈夫、降りられる。俺が降ろす」
囁きながらすり、と優しく頬を擦り合わせると、慣れているそれより3段は深くて重い余韻に抗おうと強張っていた悦の体からふっと力が抜け、直ぐにぶるりと大きく震える。背を撫でる傑の掌に合わせて懸命に息をする様子がいじらしい。
「ゃあ、あっ……まだ、たかいっ……」
「我慢した甲斐あったろ?」
「ぃ、いけ、なっ……これ、あとで……!」
「このくらい、いつでもやってやるよ」
「すぐる、傑……っ!」
「ここに居る」
「は、ぁあ……っ」
最後に心底気持ちよさそうな溜息を漏らして、化学物質による横槍の無い余韻を味わい尽くした悦はくた、と全身から力を抜いた。髪を梳いて伺った表情には怯えも恐れも既になく、満足気に傑の肩口に頭を擦り寄せてくる。流石の順応力だ。
「これ、すっごい……」
「気持ちよかった?」
「ヤバい……スーダの廃直ブレンドよりキマる……」
ふわふわと語尾が蕩けた可愛い声で闇深いことを呟きながら、首から背中に回った腕が甘えるようにきゅ、と傑を抱きしめる。危ない。暴発しかけた。
「すぐる……」
「ん……もう一回?」
「……うん」
小さくもしっかり頷いた悦の腕から、促すように力が抜けた。傑としても浸っている顔を正面から見たかったので、比較的無事な部分を選んでシーツの上に押し倒し、腰を引き寄せようと絡む膝裏を掴んで大きく広げさせる。
「ここ、持ってろ」
「う……ぁ、はい……っ」
抱きつかれるのもいいが顔が見たいので自分で両膝を広げさせると、うん、といつもの調子で頷きかけた悦が自主的に言い直した。しかもいつになく殊勝な言葉遣いが恥ずかしいのか、少し目を反らして。ここまで来ると最早テロ行為に等しい。
「そのまま離すなよ。”待て”」
「ぁ、あぁぁ……ッ」
ぎしりとマットレスを鳴らして顔のすぐ側に手を突き、今までと同じ様にゆっくりと腰を引く。すっかり傑の形を覚えてくれた具合のいい居場所からお暇するのに、実はいつもそれなりの精神力を要していたのだが、もうその必要も無い。
本当はここも今までのようにじっくり擦り上げてやった方がいいのだが、いい加減下半身が熱暴走を起こしそうなので最適解を無視して一気に突き上げた。
「あぅ゛うっ!」
「ごめん、ちょっと我慢な」
イッた直後にこの深さと速度は辛いと解っているが、もう止められそうにない。久しぶりに扱かれる感触が良すぎて視界が揺れる。
「んぁッ、あ、あぁ゛っ、あぁあっ!」
「は、……やべぇなこれ……っ」
「ひぁああっ!?ふ、かい、ふかいぃっ!」
一突きごとに浅くイって痙攣する内壁の具合が最高過ぎて、深いストロークではとても保たない。堪え性の無さを申し訳なく思いながら小刻みに最奥を突く動きに切り替え、いやいやと首を振っている悦の頬に手を添えて半ば無理矢理視線を合わせた。
「……”よし”」
「ッ――――!!」
絞るような締め上げに今度は逆らわず、ぐん、と仰け反った悦の背を片手で支えながら、これも久しぶりの無理矢理ではない射精の感覚に大きく息を吐く。
「はぁ……」
「―――っひ、……はひ……っッ」
見開かれた瑠璃色が、二度目とは思えない慣れの早さでうっとり細められるのを真上から見つめながら、添えていた手を下ろしてびく、びく、と跳ねる背をシーツに寝かせ、頃合いを見て一度モノを抜く。
こぷ、と好き勝手に注いだものが溢れてくる様が、その感触だけで高さを増す波に攫われている悦の表情と相まって凄まじくエロい。こんな扇情的な恋人を前に冷静さを保とうとするだけ無駄なので、出したばかりだと言うのに相変わらずの腕白さの自身についてはもう諦めることにした。
「次、どの体位がいい?」
「……ば、っく……」
「わかった」
お利口に膝を抱えていた両腕を解かせてうつ伏せにひっくり返し、貪欲に期待に震える腰を両手で掴んで膝を立たせる。やはり加減した分だけ縛りが軽く、”溜め”の長さがかなり影響しているようだ。本当はもう少し慣らしてからにするつもりだったが、この反応なら耐えられるだろう。
「ちょっとキツいやり方するけど、”待て”出来るか?」
「できる……っ」
「イイ子だ」
ぎゅっとシーツを握り締めて頷くうなじにキスを落として、リードの代わりに両手で腰を掴んだまま、三夜をかけて覚え込ませた動きで根本まで挿れる。
「んぅうぅ……ッ」
猿轡の代わりにシーツを噛む愛らしさに目を細めながらゆっくり引き、回転率と生存率を上げる為に激しいやり方に傾倒した悦が嫌いなペースで、逃したいほど大好きな所を緩慢に擦り上げると、塞いで縛られていない唇はすぐにシーツを離した。
「はあぁっ、ぁ、あー……っ!」
「ここ、好きだろ?」
「っす、き……すき……ッあぁぁぁ……!」
”躾”の最中に求めていたのとはかけ離れた緩やかさの筈だが、悦は濡れた頬に新しい涙を伝わせながら何度も頷く。普段なら連続でイってしまうので時々外して刺激を散らしてやる必要があるが、”待て”がかかっている今は勝手に動いてはいけない、から転じて勝手に気持ちよくなってはいけない―――のは無理だから勝手にイってはいけない、という精神的な制限が掛かっているので、小細工も手加減も不要だ。許容量の限界まで狙いを反らさず責めてやれる。
「気持ちいい?」
「いいっ……ぁんン……きもちいぃ……!」
「よかった」
これを機にがりがりと理性を削り取るばかりが最高のセックスではない、と覚えてくれればこの”躾”は大成功だ。身も世もなく暴力的な快感に泣き喚いている悦も可愛いが、喚く余地も与えられずにじっくり丁寧に嬲られてか細く啜り泣く顔も捨て難い。
悦の休暇が終わってそうそう時間をかけていられなくなったとしても、可愛い恋人から強靭に鍛えられた矜持や覚悟や意地を優しく剥ぎ取ってやる方法は、他に幾らでもある。
「んぅぅ、うぅっ……すぐる、すぐるぅ……ッ」
「あぁ、ここばっかりじゃ飽きるよな」
「ひぁああっ!」
「ちょっと強いか。このくらい?」
絶頂一歩手前のところでずっと宙吊りにされている悦が終わらない快感に怯え始めたので、ごちゅん、と突き上げた最奥に狙いを変えた。一番好きなノックするように小刻みに突く動きに加えて、時々押し上げたそこをぐちぐちと捏ねるように抉る。
「あっ、ぁ、あ、あぁッ……んゃあぁぁ……っ!」
「さっきの方がいい?」
「ちがっ……ぁあぁ……っぬ、ぬかない、で……!」
「抜かねーよ」
人間を人間扱いしない外道ばかりを相手にしていた悦は、S字を抜かれるのが嫌いだ。そこを許すと体を破壊される可能性が格段に上がるので、殆ど怖がってすらいる。ゆくゆくはその辺りも壊されるからではなく、そこでしか満足出来なくなったら困るから、に認識を塗り替えてやりたい所だが、いくら覚えが早いとはいえ詰め込みは禁物だ。人格に影響が出る。
「悦が好きなことしかしない、って言ったろ」
「はぁ、ぁああっ……んん……ッ」
”躾”中に何度も繰り返し教え込んだ角度と深さで腰を止めると、切なげにシーツを引っ掻きながら小さく頷いた。覚えたての深い快感を求めて蜜のように蕩けた瑠璃色が、打算も演出も無く哀願だけを湛えて傑の顔色を伺う。
「す、好き……がまん、するの……すき……っ」
「自由に動けないのも好きだよな」
「うん、ぅん……すき、だからぁ……っ」
「だから?」
求めた結果与える為に促した傑の膝を、これ以上は無いと断言出来る最適の力加減で、きゅっと爪先を丸めた悦の両足が挟み込んだ。
「よし、って……言って……!」
……ああ、もう。どうしてやろうか。
「……最高だな、お前」
それ以外の感想が無かったのでしみじみと呟いて、傑はゆっくり腰を引いた。また一息に突き上げられて連れて行かれる、と思った悦が縋るようにシーツを掴んでいるのが微笑ましい。
勿論、あんな殺し文句を貰って二番煎じを返すつもりは無いので、浅い所から順番に、じっくり感じるところを擦り上げながら貫き、ゆるゆると抜ける寸前まで引いて、奥へ誘う内壁に逆らわず緩慢に突き上げる。
「ぁ、あ、ぁ……っ?」
好みを差し引いても今の”最適解”である深く緩いストロークの意図に、4度目で気づいた悦が首を巡らせて傑を振り返った。鍛えられた観察眼で藍色の瞳に哀願を切り捨てる素振りが無く、約束を違える気も無いことを読み取って、微かに首を横に振る。
「や、やだ……!」
「ヤクに負けるわけにいかねぇからな」
「ッ……これやだっ……はやく、はやくして……!」
「大丈夫だから力抜いてろ。いい子だから」
一気に注ぎ込むよりも、時間を掛けてじわじわ注ぐ方が表面張力の限界まで”溜め”られるのは自明の理だ。また知らない所に、しかも知らないやり方で連れて行かれる、と怯える悦の手を握り、指の間を掠めるように撫でて余計な力が抜けるように促す。
極限の緊張状態を保つことで正気を守り抜いてきた悦は、その緊張が緩む危険性を本能で知っている。雑音を排して、それだけに集中して、身も心も溺れる快楽がそれ以外とは別物だということも、もう解っている。経験がある分恐れがあるのは当然だが、幸いにして傑は純血種だ。人間を壊す方法も、絶対に壊さない方法も熟知しているので、自我の限界まで溺れさせてやれる。
「だ、めっ……ゆ、っくり、だめぇ……!」
「ちゃんと降ろしてやるから」
「あぁ、ぁっ、あッ……い、言わないで、いま、だめ、だからぁッ、言わないでぇ……っ!」
「”よしよし”、怖くない怖くない」
「ぁ゛っ……~~~~~っッ!!」
お互い必要無いのでスイッチとして強く深く突き上げることもなく、背後から抱きしめて耳元に囁くのと同時に目を見開いた悦が、腕の中で一度ぎくんと大きく跳ねた。
声にならない声と共に引きつった指が傑の掌に爪を立て、強烈な締め付けに息が止まる。駆け上がった勢いのままに脳裏で弾ける快感と多幸感は、やはりそれ以外とは別物だ。最後の一滴まで搾り取ろうと痙攣する体が、より深く重い絶頂を上手に受け入れてとろんと瞳を蕩けさせる自我が、腕の中にすっぽり収まってくれた全てが愛おしくて仕方がない。
「……ひっ……ひぃ……っ…!」
「可愛いな、お前」
箍を飛ばしてベクトルを捻じ曲げた愛情が抑えられず、抑える必要性も無く、傑は与えた快感に深く浸った悦を抱き上げた。掠れた甘い悲鳴を上げてかくん、と肩に乗った頭を撫で、不規則に震える体を壊れないように抱き締める。
「うぁ……ぁ……っ」
「……はは、」
躊躇いがちに、それでも確かに応えるように背中に回った腕にきゅっと指先で抱き返され、思わず笑ってしまった。
この愛しさと幸福の全てを表す言葉は、さしもの純血種にも解らない。
「……よく飽きねぇな」
バスタブの中で胸板に凭れた悦が沈まないよう片腕で腰を抱き、もう片方でシーツを握ったり傑の背中に爪を立てたり髪を引っ張ったりと大活躍だった古傷の残る手をマッサージしていると、半分微睡んだ恋人が枯れた声でぼそりと呟いた。
「飽きる?」
「こんなの、……意味ねーのに」
言いながらされるがままだった指先が微かにお湯を掻き、ようやく傑は隠された主語を察する。ベルガモットのアロマキャンドルが燃え尽きて、その残り香も薄れるまで貪り尽くして満腹だったというのもあるが、それ以上に埒外過ぎてすぐには考えが及ばなかったのだ。
察してしまえば成る程、らしい言葉ではある。優しさや気遣いを一時でも受け入れてしまったら、Z地区の男娼としては、しかも”群れ”の生存率を上げるために金払いが良く外道な”上客”ばかりを引き受けていた悦にとっては、自分の耐久値の低下を招きかねない。正当な進化を経た生き物の、慣れと順応という脆弱な対応策を最大限活用しようと思えば、確かにそれは最適解だ。
人間相手なら。
「ぁ、……し、躾は……よかった、けど……」
邪魔なので早々に壊してやりたいが、根が深いので根幹に影響しかねない。早急かつ慎重にぶち壊そう、と考える傑の沈黙を不興と取ったのか、ぽそぽそした声で悦が可愛い補足を入れてくれる。勿論そんなことは百も承知だが、言葉で「よかった」と伝えられるのは純粋に嬉しかったので、頭を撫でておいた。
「好きでやってンだから、飽きるわけねぇだろ」
「……」
「それに、意味ならあるし」
今はな、誰だってそう言うんだよ、と言いたげに足の爪先を動かした悦の腰に両腕を回して、傑はしっとり濡れた蜂蜜色のつむじに鼻先を埋めた。
境遇を思えば疑い深くなるのは仕方がない。そういう所も可愛いし、邪魔な箍を全て弾き飛ばした今の傑には純然な事実として敵はいないし、過酷な環境を生き抜いてきた悦の本能の方は完璧な安寧を提供できる傑の味方だ。何も問題は無い。
「意味?」
「俺が楽しい」
「……ンだそれ」
呆れたように溜息を吐く悦を抱いたまま、傑は心地いいぬるま湯の中で目を閉じる。
目を閉じたままでも、言葉や態度がどれだけかけ離れていても、選んで掴んだ愛しい道連れが自分でも気づいていない本心から望むものくらい、純血種には手に取るように解るのだ。
Fin.
「あの人をよろこばせたい」というのは、とてもピュアな愛の形。
傑も、そして悦も、互いをよろこばせたい。
つまりこの2人はピュアです。
ピュアです。
「ただいま」
「……」
緩慢に傑を見上げる瑠璃色は熱を孕んで濡れている。片手に持ったゲーム機の画面はコンティニューを促す表示のままだ。キャビネットに乗った手入れ道具が詰まった箱に開けられた形跡は無いし、ローテーブルに投げ出されたお気に入りのナイフの位置も変わっていない。
穴だらけになったシャツを脱ぎ捨ててゴミ箱に突っ込む傑を、熱を持った視線がふらふらと追いかけてくる。いつも通りを取り繕う余裕も、目を反らしてそれを隠す意地も、薄っすらと頬を上気させた悦にはもう無い。
いい傾向だ。
本当に飲み込みが早くて可愛い限りだが、正確なタイムテーブルも条件付けの一つなので、今からベッドに連れて行くわけにはいかない。あの様子では昼もまともに食べていないだろうし、決して正解を教えられない”躾”の内容を必死に推測している今の悦は、自分で作った精神的な縛りでがんじがらめだ。いくら芯が強いとはいえ、あまり厳しくしても参ってしまう。
取り敢えずシャワーを浴びて硝煙と血を洗い流し、今後の段取りもあるので適当な服を着て、傑はリビングのソファに腰掛けた。ソファに背を向ける形で横向きに寝転んだ悦の後頭部を見ながら、髪を拭っていたバスタオルを首に掛ける。
「退屈そうだな、それ」
「……ん」
相変わらずの表示を続けている手のひらサイズの機械を指して言うと、微かに頷いた悦は旧型だが大事に使われていると解るそれから手を離した。普段の機敏さが嘘のようにのろのろと動く指先がカチン、とボタンを弾いて、悲壮感のあるBGMを止める。
「暇なら、俺と遊ぶ?」
「……」
普段なら「それ絶対俺が遊ばれるヤツだろ」とジト目で睨んで来る所だが、頭だけを動かして振り返った瑠璃色は隠しきれない期待と少しの怯えを含んで傑を見上げた。
「簡単なゲームだけど、それよりは面白いと思うぜ」
今の悦には、特に。
誘うように首を傾げて見せてから、傑は深くソファに座った自分の足をぽんぽんと叩く。起き上がった悦がのたのたと近づき、”躾”中と違って服を着ている傑の体を物言いたげにじぃっと見つめるのを腕を引いて背中を向けさせ、太腿ではなく足の間に座らせて、くたりと背中を預けて来る体温の高い体を抱きしめた。
「はぁ……あっ」
「ここ、咥えて」
ぺろりとTシャツを捲りあげても抵抗せず、閉じた両膝を擦り合わせる悦の口元にたくし上げた裾を近づける。お遊びなので命令では無くあくまでもお願いの形だが、勿論断られるとは思っていない。
「今から10分、離さないでちゃんと噛んでられたら悦の勝ち。離させたら俺の勝ち。簡単だろ?」
「ん……」
「やる?」
「……んん」
裾をしっかり噛んで咥えた蜂蜜色が躊躇いがちに頷いたので、傑はポケットから出した端末に10分のタイマーを設定して悦にそれを持たせてから、緩く腰を抱いていた掌をする、とみっしり中身が詰まった薄い脇腹に滑らせた。
期待に鳥肌立った肌の感触を楽しみながら両手を使って腹から胸までを撫で上げ、触って欲しそうに尖った乳首の周りをくるくると指先で撫でて少し焦らしてから、左右一緒に中指の腹で押し潰す。
「んぅううッ……!」
くん、と顎を上げた悦の体に力が入るが、この体勢ではいくら背を反らした所で逃げられはしない。寧ろ差し出すような格好になって弄り易くなったので、ご要望に応えてきゅ、きゅ、と緩急をつけて優しく摘んでやると、端末を持っていない方の悦の手が傑のシャツを掴む。
「ぅんっ、ん、んンっ……ふぅ、う……!」
「気持ちいい?」
「んっ……んぅ、ん……ッ」
「こっちも力抜けよ。その方が気持ちいいから」
不随意な震えと痙攣以外は身動ぎ一つ許さない”躾”の時と同じく、がちがちに緊張した腰から太腿を撫で下ろして囁くと、ぴくりと肩を跳ねさせた悦が振り返った。動いてもいいの、と問う不安げな瑠璃色に優しく目を細めて見せて、赤く色づいた先端を引っ掻く。
「ひぅんっ……ん、んーッ……!」
散々抑圧してやった分、陥落はあっという間だった。
かりかりと引っ掻かれるのに合わせて控えめに足を跳ねさせていたのは最初だけで、裾を離さずにいれば逃げるように体を捻っても、縋るように手首を掴んでも叱られないと理解してからは、愛しい恋人は一秒だってじっとしていなかった。
くにゅくにゅと押し潰されて身を捩り、外れた傑の手を引っ張って自分から敏感なそこに押し当て、すりすりと指の腹で撫でられるのにぱたぱたと足を動かしたり、かと思えば爪先までぴんと伸ばしてみたりと、いつになく素直な様子で与えられる快感に浸っている。
「ふー……ふーっ……!」
床に落ちた端末がアラームを鳴らす頃には、シャツを離してしまわないよう両手で自分の口を覆ぎながら、ぷくりと膨らんだ乳首を差し出すように傑の足の上に寝転んでいる有様だった。
「離さなかったから、悦の勝ちだな」
「ふぅう……っ」
端末を拾い上げながら鎖骨をくすぐると、いやいやと首を横に振った悦が小指を握った。もっと、と太腿から背中を浮かせながら、引き下ろした傑の掌を胸に押し当てる。
久しぶりに何の我慢もしなくていい状態で与えられる快感に、悦はすっかり溺れてしまったようだ。実際はシャツを噛んでいるので声も満足に上げられないし、一度だってイかせて貰えていないのだが、とろりと蕩けた瑠璃色はもう「シャツを離さずにいれば気持ちいいことをしてもらえる」ということ以外なにも解っていない。
仮初の自由を味わえば味わうだけ、それを制限された時が辛くなることくらい、そこらの子供でも解りそうな単純な理屈だろうに。バカな子ほど可愛いというのは真理だ。
「……もう一回やる?」
「んんっ……!」
自分で自分の首を締めていることなど露ほども気づかない悦に蕩けるように微笑んで、傑は電源を落とした端末をローテーブルの上に放り投げた。
3日目。
「あぁぁッ……や、だ、もうやだぁああっ!」
面白いくらい想定通りに、3度目の入れ直しの半ばで叫びながら暴れだした悦を、傑は腰を掴んでいない方の手で背中を押さえてシーツに縫い止めた。
「やだ、やだぁっ!はなして、こすってぇっ!」
「”待て”だって言ってるだろ」
「待てない、もうまてないぃ……っ!」
猿轡の代わりに着けた目隠しをシーツに擦りつけて外してしまった泣き腫らした瑠璃色に、あの強靭な覚悟はもう跡形も無い。
「嫌だ、って言って止めたんじゃただのプレイだろうが」
「も、いい、それでいい、からぁ!お願い、傑、すぐる……っ!」
「……あのなぁ」
はぁ、と大きく溜息を吐いて、背中に置いた掌にぐっと力を掛ける。頭の中は想定していた数倍の鋭さで嗜虐心やら征服欲やら性欲やらを煽る悦の姿に理性がぎりぎり音を立てて軋み、半端に腰を止めている所為で回路が2度ほど焼き切れていたが、幸いなことに傑は純血種だ。
どこぞの最高幹部を「人間にしては良く頑張っている」と上から目線で褒められる程度には内面と外面を切り離す術に長けているので、「ヤバい」と「可愛い」以外の語彙が吹き飛んだ思考を完璧に隠して、苛立ったように眉を顰めて見せた。
「躾けてくれ、って言ったのはお前だろ」
「でも、だって……!」
「あー、もういい。喋るな」
ひぅ、と喉を震わせる悦の弁解を雑に遮って傍目には乱暴に、実際は引き込もうと蠢く内壁の動きを完璧に読んだ針に糸を通すような繊細さでモノを引き抜き、悦の腰から離した手を枕元に伸ばす。
察した悦がやだ、やだ、と子供のように泣きじゃくるのを聞いていると自分が極悪人のように思えてくるが、仕方ない。これも世間的には同じ極悪人である可愛い悦の為だ。
今の悦にとっては焦らされたとしても”待て”の方が辛いので、お仕置きを引き合いに出して脅すことはせず、こうなることを予想して用意してあった布を丸めて開かせた口に押し込む。背中を押さえる手を膝に置き換えて上から猿轡を噛ませると、声量と同時に一気に抵抗が弱まり、反比例してぽたぽたとシーツに滴る涙の量が増えた。化け物を本気にさせるほど可愛いばっかりに、可哀想に。
「頭で覚えらんねぇのは解ったから、体で覚えろ」
「う゛ぅっ、うぅうう……!」
低い声で言いながら震える悦の体を仰向けにひっくり返し、同じく用意してあった3本目のベルトで手首から肘までを縛り上げる。意図して凍てつかせた視線に怯えて完全に抵抗を止めた両足を揃えて曲げさせ、腰から外した1本目のベルトで太腿と脛を纏めて縛り、その上から掛けた2本目のベルトを腰の下に通してぎゅっと絞め上げて、傑は顔を上げて悦と視線を合わせた。
「これなら集中出来るだろ?」
「ふっ、ふぅうッ!」
言外にいいから大人しく悶えてろ、と告げて、ぼろぼろと涙を零す瑠璃色を目隠しで塞ぐ。
「……はぁ」
目が見えなくなったことでようやく軋んでいた理性に多少の余裕が戻り、傑はシーツに座り込んで思っきり素の溜息を吐いた。もう少しでこの数日間の悦の頑張りを無駄にしてしまう所だ。
悦に見えていないのをいいことに「あー、危なかった」と天井を仰ぎ、ついでに焼き切れたまま適当に繋いでいた回路を3秒で修復して少し補強もしてから、傑はローションボトルの蓋を跳ね上げた。両膝を胸にくっつけるようにして拘束されている所為で随分コンパクトな姿になった悦がびく、と大きく震えるのを見ながら、苛立つ演技の一環で堰き止めていた下半身の血流を元に戻す。
自分で動かないよう自制させるよりも、動けないよう縛ってやった方が精神的な負荷は少ない。とはいえ、今日で3日目。結局2時間近く続けた昼間のゲームの甲斐あって、経験豊富なZ地区の男娼としての覚悟も意地もようやく折れた。更に人間の知覚情報の8割を占める視覚を奪う目隠し。昨日までとは違って完全に口を塞ぐキツめの猿轡。
どれだけ加減してやっても1時間が限度だ。
「んぅうぅッ、ぅう゛ぅーー……っ!」
今の自分の体内時計に自信が持てなかったので端末で時間を確認してから、傑は最高に可哀想で可愛い恋人を、何一つ満足させてやらないよう慎重に貫いた。
「ふ、ぶっ……ぅぶ……ぅっ!」
残り10分を切った所で呼吸すら覚束なくなった悦が自分の唾液に溺れ始めたので、猿轡と一緒に目隠しを外す。滴るほどに涙を吸った布は猿轡とそう変わらないくらい重い。
「……集中出来たか?」
「はぁ゛っ……は、……!」
舌を出して酸素を貪りながら、快感と酸欠で真っ赤になってしまった顔が微かに頷く。一番気持ちよくて辛い所を抉りも擦りもして貰えず、ただ圧迫され続ける感覚に強制的に集中させられた頭でどれだけ理解しているか怪しいが、返事が出来るだけ上等だ。
「いい子だ」
「ぁ……あ゛……っ」
その健気さに免じて残りの10分はおまけしてやることにして、悦と同じだけ”待て”を食らっている下腹部の血流を極度に制限して無理矢理萎えさせてから、傑はずるりと腰を引いた。中折れのようでどうにも情けないが、3日目ともなると完勃ちのままじわじわ抜くのはキツい。いくら純血種でも流石にキツい。
「す、ぐ……ぅ……っ」
「水飲めるか?」
「ん、……」
今日はこれ以上追い詰めるつもりは無いので腕と足のベルトを手早く解き、ついでに短くなったキャンドルの小さな炎を指で揉み消して、傑はサイドボードに乗せていたペットボトルを抱き起こした悦の口元に近づけた。霞がかった五感全てで注意深く傑の気配を探っていた震える手が、常温のスポーツ飲料水に触れる寸前でぱたりとシーツに落ちる。
意識も半分トんでいるような状態だろうに、ここからは”事後”だと確信出来るまで緊張を保ち続ける様子が痛々しくてとても可愛い。
「今日は流すだけにしような」
「ひぅ……っ」
「明日は好きなだけ自分で弄ってイイから」
昨日と一昨日のシャワー責めがよほど辛かったのか、抱き上げた途端に泣きそうな顔をする悦を宥めながらベッドを降り、すっかり習慣になりつつある「恋人じみた」手厚い後始末の為、バスルームに向かった。
「……変わるもんだな」
ロックグラスの中の氷をからんと手遊びに鳴らしながら、傑はぽつりと独りごちた。
皇国から飛行機で東に5時間の位置にある、観光を主産業にする小国。その首都の外れにある小洒落たバーのカウンター席に座った藍色の視線の先には、画面を埋め尽くす文字と記号がスクロールし続けるノートパソコンがある。
グラスを持ったままの手でいくつかのキーを叩いて延々と伸び続けていた文字列を停止させ、警告音と共に5つのポップアップが表示されるのを確認してパソコンを閉じ、傑はグラスの中身を飲み干した。
温かい食事によって味蕾の職務怠慢が改善されたのか、こんなありふれた安酒すらも妙に美味く感じる。録音のモード・ジャズが内側からの軋む音に煩わされることのない聴覚に、L字のカウンターを彩る飴色の木目が歪まない視覚に心地いい。
突き詰めてしまえばたった1つ、散大していたベクトルの方向が定まっただけなのに。ただそれだけで、本当に世界は変わるものだ。
「”寝て醒めた後に、”ってやつか」
この国で生まれた古い舞台の一節を引用しながら冗談めかして笑う傑に、酒瓶が並ぶ棚に凭れた愛想の悪いバーテンは明後日を向いたまま、答えなかった。
それに軽く首を竦めて、傑は足の長い椅子から腰を浮かせてグラスを置いた手を伸ばす。相変わらずこちらを見ないバーテンの左肩の向こう、整然と並んだ酒瓶の一本を抜き取って座り直した所で、何本かの瓶とグラスを道連れにしながらバーテンがずるずると傾いた。
脛骨を折られて明後日を向いた死体が倒れる重い音に、甲高い電子音が重なる。
「はいよ」
『傑……』
「よぉ、鬼利」
頬杖をついていた手を伸ばして着信に応じた傑の気楽な声に、3本のケーブルでパソコンに繋がったままの端末が重々しく溜息を吐く。
珍しく素直に忌々しげなその声にくく、と喉を鳴らして笑い、傑は封を切った酒を瓶ごと呷った。
「イイ腕してるな、あのガキ」
『……お陰様で、顔を青くしているよ。3ヶ月を無に帰されたって』
「へぇ、そりゃ凄い」
今しがた叩き潰したあのシステムを3ヶ月で構築したのなら本物だ。ころころ変わる派手な髪色はハッタリじゃなかったんだな、と素直に感心する傑に、端末向こうの”飼い主”はもう一度深く溜息を吐いた。
『どういうつもり?』
「十四隊、龍鱗楼一家、管理難度」
『……』
いちいち説明するのが面倒なので要点だけを話すと、人間にしては高性能な脳を積んでいる最高幹部が黙り込んだ。同族相手にしか使ったことの無い不親切な話法のシステムと、それを今日この場で初めて用いた傑の心情を鬼利が理解するまで、約3秒。
「あと、迷惑かけたお詫び」
『……気色の悪い……』
期待通りに化け物の意図を汲んでくれた脆弱な人間が、珍しく何を取り繕う事もなく心の底からの声でそんなことを言うものだから、傑は思わず声を出して笑った。
『……ご機嫌が麗しいようで何よりだよ。”彼”の状態は?』
「砂とサボテンが装置の舞台には間に合う」
『まさかとは思うけど』
「この程度でわざわざ裏取るかよ。俺のことは割と正面きってナメてくるよな、お前」
『信頼の証と思ってくれていいよ』
「書き割り相手に?いい性癖だな」
『……はぁ……』
目のいい片割れと一緒に引き篭もっている箱庭の完成度を含めて賛辞を贈ると、面倒臭そうに溜息を吐いた頭のいい方がカツン、と万年筆で机を叩く。
『……こういう形の”進化”は望んでいなかったよ』
「だろうな」
手駒の”劣化”を喜ぶ指し手はいない。そのゲームに命以上のものが懸かっていれば尚の事そうだ。だからこそ、この”飼い主”には考え続けるよう釘を刺しておかなければならない。
崩壊寸前の兵器から死に様の決まった生き物に劣化した化け物の、一番上手い使い方を。
「お前ならすぐ慣れる。明日の昼には戻るから、土産話はその時にな」
『明日?』
「何事も緩急が大事だろ?」
『……同情するよ』
「酷ぇな」
血の一滴も空薬莢の1つも無くカウンターとテーブル席に突っ伏している15の死体にではなく、自室に残してきた恋人を心から憐れんで切れた端末に、傑は瓶を傾けながら苦笑する。
「よろこばせたいだけなのに」
軽薄な笑みに似合わず真摯に響いたその言葉を、明後日を向いた死体だけが聞いていた。
4日目。
優れた体幹が見る影もないふらふらとした足取りで寝室に入った悦は、そのままの足でサイドボードの前に立つと、そこに乗ったアロマキャンドルの残骸を床に払い落とした。
最下段の棚を足で引き出し、中から真新しいキャンドルとライターを取り出して、乳白色に薄いオレンジでマーブル模様を描いたそれに火を点ける。芯が燃える焦げ臭さを覆い隠す、甘酸っぱくてどこか苦い香り。
4日前までは空っぽだった2段目の棚を手で開けて中の物をシーツの上に放り投げ、はぁ、と震える息を一度吐いてから、悦は羽織っていたバスローブを床に脱ぎ捨ててベッドに上がった。
「んんっ……」
シーツを裁断した四角い布を紐状にして口に咥え、3本の中で一番長いベルトを腰に巻いて端をヘッドボードの装飾に括り付けて、それがぴんと張る位置で引き寄せた枕の上にうつ伏せにぼすんと倒れ込みながら、真新しいローションボトルの蓋を指で跳ね上げる。
「ふ、……ふー……ッ」
止まりそうになる息を努めてゆっくり吐き出しながら、悦はシーツから持ち上げた腰に直接ローションを垂らし、じっとりと肌を伝うそれを掬い取った中指を慎重に奥に埋めた。
言っていた通りに仕事に出掛けて戻らない傑が、この3日間必ず”躾”を始めていたのと同じ時間に、同じ場所で、していたのと同じ様に。
「ん、ふっ……んんぅ……!」
絶対に傷をつけないように細心の注意を払って、慣れたそこを慣れない手付きで解しながら、悦はベルガモットが染み込んだ灰色のシーツの上でぎゅっと目を閉じる。
伊達にシーツの上を主戦場にして生きて来ていない。こんなことはあらゆる意味で何の慰めにもならないと、ちゃんと悦は理解していたが、解って止められる程度の泥沼ならあんなに無様に泣き喚いたりしない。
悦自身のそれよりも長い指の記憶をなぞって動かした指の先で、薬を入れられたように敏感になった膨らみがこりこりと潰れる。
「んぅうっ……ん、んン、……ぅうぅ……!」
じん、と走った甘い電気に揺れようとした腰をベルトに引き戻され、つい加減無しに押し潰していた指を引き抜いた。どぷりと掌に垂らしたローションを絡めて入れ直し、きゅうきゅうと締め付けてくる粘膜の中でそっと第二関節を曲げて、呼吸に合わせて緩やかに膨らみを押す。
初物相手のような丁寧で緩慢な、体どころか頭の中まで溶かすようなやり方は、勿論今は居ない傑を真似たものだ。少しでも壊され難くする為にローションまで仕込んで下準備された淫乱を、こんな手間をかけて悠長に解すような男は、少なくとも悦が知る限り他に居ない。
「ふー……っふー……!」
嗜虐的に冷えた外郭の内にどろどろした灼熱を飼い慣らしながら、まずはローションを絡めた長い中指一本でじっくり熱を持った粘膜をくすぐる。小波のように広がった甘い痺れに頭から爪先までどっぷり浸された頃に人差し指が、大人しく開いていた両足がびくびくと痙攣するようになってやっと薬指が増やされ、掌を伝って流し込まれた人肌に温いローションを丹念に塗り広げていく。
とろとろに解された内壁のどこが気持ちいいのか、どうされるのが一番堪らないのか、1つ1つ丁寧に思い知らされてようやく、指が抜かれる。
瞳の内側にある熱量そのままに硬く滾ったモノが、それを受け入れる為だけに在るような有様にされたところに押し当てられて、そして。
―――”待て”。
絶望的なまでの性能差が生む圧力をたった一言で表して、極限まで飢えさせられた何もかもを一欠片だって満たさないようにゆっくりと、悦の身も心も屈服させるのだ。
「ふッ……―――!」
残酷に甘い声を思い出しただけで浅い絶頂が白く頭の中で弾け、悦は自由な手で千切れるほどシーツを握りしめる。
空気を甘酸っぱい香りに満たしても、一人きりのシーツの上でその残骸を噛んでも、丈夫なベルトで震える体を縛り上げても、あの声や指や熱をいくら鮮明に思い出して再現したって、この飢餓感は満たされない。
精々浅くて軽い絶頂にほんの一瞬救われたような気になって、すぐにその倍の深さで叩き落されるだけだ。ちゃんと解っているが、解っていて止められるような浅い泥沼なら始めから落ちていない。
「ぁう、う……っ」
今は辛うじて残ったこの正気も、きっと一時間と保たずに擦り切れるだろう。気休めだということすら解らなくなって、冷たい革や布の感触に藍色の面影を探しながら、記憶に残るその姿に縋り付く。自分からねだって与えられたものも満足に受け止めきれない惰弱さのままに、みじめに泣き喚きながら。
その内に力尽きて啜り泣きながら意識を失った元男娼の姿は、きっとその肩書きの分だけ倍増しで無様だ。
呆れられるだろうか。嘲笑われるだろうか。
悦自身が一番嫌いな悦の救いようもなく弱い所を、多少崩れたって桁違いに強い藍色が、見たら。
あの完璧に美しい化け物は、
「……すぐ、る……っ」
……よろこんで、くれるだろうか。
観光名所の一つである朝市をのんびり回って形は悪いが味の良いお土産をいくつか選び、予定より半日遅い飛行機で戻った傑を、鬼利はその顔と抱えた紙袋を睨みつけながらもう一度「気色悪い」と評した。
自覚はあったので「羨ましい?」と茶化して閉口させてから自室に戻り、瑞々しい野菜や果物を紙袋から冷蔵庫に移して、先にシャワーを浴びる。結局朝方まで居座ったバーの残り香を綺麗に洗い流し、脱水症状の危険性を身に沁みて知っている悦が常備しているスポーツ飲料水のペットボトルを2本片手に提げて、ベルガモットが溢れ香る寝室の扉を開けた。
「……は、」
目の前に広がった光景に思わず、上擦った声が漏れる。
その為に選んで敷いた灰色のシーツは、零れたローションやその他の液体で半分以上の面積を濃い色に濡らしてぐしゃぐしゃになっていた。空になって転がったボトルの数は2本。猿轡や目隠しに使っていたのと同じ布がマットレスの縁に引っ掛かり、シーツの合間にはいつか使ってそのままサイドボードに入れていた、銀色のマドラーまでもがローションまみれになって転がっている。
そして、ヘッドボードに繋がれたベルトの先で、どろどろに濁った瑠璃色が瞠目して傑を見上げていた。
「愉しそうだな」
吊り上がる口元を隠そうともせずに言えば、その蜂蜜色の髪の一部までも透明な粘液に濡らした可愛い恋人が、びくりと大きく震える。リードのように腰に巻き付いた以外にも、両腕が手首の位置で、右足が折り畳んだまま太腿の位置で、それぞれ白い肌に映える黒いベルトで絞め上げた格好のまま。
「ち……ちが……っ」
「違わねぇだろ」
力なく首を振る悦の言い訳を遮って、着ていたシャツを頭から脱ぎ捨てながら膝でベッドの上に乗り上げる。傑の気配を察知して気絶から飛び起きるほど鋭敏な癖に、逃げるでも、皺の寄ったシーツに隠れるでも無く、ただその場で震えながらきゅっと体を丸める仕草は無力な獲物そのものだ。この上更に愛らしさを上乗せしてくるポテンシャルの高さに目眩がする。
「こんなモンまで引っ張り出して」
「あっ……!」
「そこら中びしょびしょに濡らすくらい愉しいこと、してたんだろ?」
拾い上げたマドラーをベッドの外に投げ捨てて、羞恥と期待に体中をほんのり上気させたご馳走を真上から両腕の中に閉じ込めた傑は、ようやくそれを頭から喰らえる捕食者の愉悦に目を細めた。
「俺もまぜろよ、悦」
5日目。
ヘッドボードに凭れた自分の体を椅子代わりに悦を両足の間に座らせて、折角なので腕と右足を縛るベルトは解かないまま、傑は最後の一本になったローションで濡らした掌を震える内腿に滑らせた。
「あーあー、溢れてきてんじゃねぇか」
「ひあぁ……ッ」
「……俺の物に傷つけてねぇだろうな」
「な、いっ……つけ、てなぃ……!」
流し込まれたローションが溢れるそこに中指を埋め、確かめるようにぐるりとナカを撫ぜながら低い声を出すと、びくりと肩を竦めた悦が首を横に振る。物覚えのいい可愛い恋人のことだ、きっと傑の動きを懸命になぞってたっぷりローションを使い、優しく優しく自分を追い詰めていたのだろう。
「ホントか?お前いっつも荒いだろ」
「す、傑がして、くれるみたい、に……ゆっくり……っあぁぁ……!」
「ゆっくり、ね」
「される」ではなく「してくれる」と言う辺り、本当に悦はよく解っている。普段の命知らずな言葉遣いとのギャップが素晴らしいので、ご褒美にすっかり敏感になった縁につぷつぷと割り開かれる感触を味わわせてから、入り口から順番にイイところを苛めてやることにした。
まずは一番浅瀬、皮膚と粘膜の境目を、たらたらと零れてくるローションを塗り込めるようにして優しく解す。貞淑に締め付けてきていたそこがはしたなく口を開けたら少し指を進めて、次は悦が特に好きな前立腺を。
「あ、あっ……はぁあぁぁ……ッ!」
張り詰めたしこりを数回押し上げてから形を確かめるようにぐるりと周囲を撫で、焦れた悦が泣き出したら、ローションで滑りの良くなった指先でこりゅ、くりゅ、と転がす。イかせてしまわないように間隔を空けて繰り返し、大きく広げられた内腿の痙攣がいい具合になった所で、指で届く一番奥、精嚢と膀胱を指の腹で押し上げた。
「ひぅっ、んぁ、あ、あっ!」
「次は?」
浅いピストンで突き上げる度にぴゅく、と先走りを零す裏筋を撫で上げながら聞くと、手放しに喘いでいた悦がぎこちなく傑を振り返る。快感と焦燥と期待と怯えと、雄の欲を刺激するなにもかもを詰め込んで蕩けた瑠璃色から、じわりと涙が溢れた。
「あぁっ……つ、つぎ、はぁ……っ」
床に転がったマドラーを見た悦が、手を止めた傑のモノをすり、と腰で撫でる。
「指じゃ、とどかない……とこ……!」
「…………はぁ」
ぞぞぞ、と背筋を這い上がったものを誤魔化すために溜息を吐いて、傑は怒らせたのかと首を竦める悦のナカから指を引き抜いた。
……ヤバい。保たない。
「な、なんで……っ」
「”待て”」
なんで止めるの、と涙声で追い打ちをかけてくる悦を雑に大人しくさせ、指を濡らすローションを物ともせずに腕と足のベルトを引き千切りながら、凭れていたヘッドボードから背を離す。ひっくり返した体を膝立ちにさせて切っ先を押し当て、そのまま突き上げそうになるのを軋む理性で辛うじて押し留めながら、傑はもう一度熱の籠もった息を吐いた。
悦が溢れるほどにローションを注いで一人遊びをしていたお陰で、柔らかく蕩けたそこはしっかり濡れている。傑自身はまだ中指一本しか入れていないが、一番気をつけなければならない入り口は十分に解したし、これ以上は悦がまたガチ泣きしそうだし、そんな顔を見たら今度こそ傑の方の理性が弾け飛ぶだろうから、まぁ、いい加減頭も回らなくなってきたことだし、いいだろう。
「す、ぐる……?」
「……悦」
ちゅうちゅうと押し当てた先端に吸い付きながらも、流石の覚えの良さできちんと”待て”をしている悦の腰を両手でしっかり掴み、傑は可愛い恋人が一番気に入ってくれている熱に掠れた低い声で、その期待に応えた。
「”よし”」
「え……ぁ゛っ―――!?」
言うと同時に腰を引き下ろし、一気に根本まで貫いた悦の体が、一拍の間を置いて弓なりに仰け反る。
「っッ―――――!!」
「ぐ……っ」
声も出ない絶頂の深さを物語るようにギリギリと折られそうに絞り上げられ、思わず呻き声が漏れた。情けないと自嘲する余裕も無い。持っていかれないようにするだけで精一杯だ。
「―――っは、……はあ゛っ……!」
仰け反ったままがくがくと痙攣していた悦の手が傑の髪をわし掴み、引っこ抜く勢いでそれを引き寄せて無理矢理に反っていた体と頭を戻す。薬物によって限りなく近い所に引きずり上げられたことはあっても、酩酊も混濁もしていない意識でそれを味わうのは初めての筈だ。
大きく見開かれたままの瑠璃色が、天然物の脳内麻薬と快感のみに深く深く犯されながら、傑を見る。
「たか、い……っ!」
「……そーだな。気持ちいいだろ?」
安心させる為に平然とした声で答えると、未だに引かない波に怯えた悦がぎゅうっと首に両腕を回してしがみついてきた。以前の悦なら一人きりで体を丸めてやり過ごしていただろうから、こうして自分から縋って来るだけでも目覚ましい進歩だ。この数日散々抱きつかせて慣れさせた甲斐があった。
「し、らな……っぁ、また、まだ、……!」
「ゆっくり息しろ、大丈夫だから」
「っひ……ひぐ……ッ!」
「大丈夫、降りられる。俺が降ろす」
囁きながらすり、と優しく頬を擦り合わせると、慣れているそれより3段は深くて重い余韻に抗おうと強張っていた悦の体からふっと力が抜け、直ぐにぶるりと大きく震える。背を撫でる傑の掌に合わせて懸命に息をする様子がいじらしい。
「ゃあ、あっ……まだ、たかいっ……」
「我慢した甲斐あったろ?」
「ぃ、いけ、なっ……これ、あとで……!」
「このくらい、いつでもやってやるよ」
「すぐる、傑……っ!」
「ここに居る」
「は、ぁあ……っ」
最後に心底気持ちよさそうな溜息を漏らして、化学物質による横槍の無い余韻を味わい尽くした悦はくた、と全身から力を抜いた。髪を梳いて伺った表情には怯えも恐れも既になく、満足気に傑の肩口に頭を擦り寄せてくる。流石の順応力だ。
「これ、すっごい……」
「気持ちよかった?」
「ヤバい……スーダの廃直ブレンドよりキマる……」
ふわふわと語尾が蕩けた可愛い声で闇深いことを呟きながら、首から背中に回った腕が甘えるようにきゅ、と傑を抱きしめる。危ない。暴発しかけた。
「すぐる……」
「ん……もう一回?」
「……うん」
小さくもしっかり頷いた悦の腕から、促すように力が抜けた。傑としても浸っている顔を正面から見たかったので、比較的無事な部分を選んでシーツの上に押し倒し、腰を引き寄せようと絡む膝裏を掴んで大きく広げさせる。
「ここ、持ってろ」
「う……ぁ、はい……っ」
抱きつかれるのもいいが顔が見たいので自分で両膝を広げさせると、うん、といつもの調子で頷きかけた悦が自主的に言い直した。しかもいつになく殊勝な言葉遣いが恥ずかしいのか、少し目を反らして。ここまで来ると最早テロ行為に等しい。
「そのまま離すなよ。”待て”」
「ぁ、あぁぁ……ッ」
ぎしりとマットレスを鳴らして顔のすぐ側に手を突き、今までと同じ様にゆっくりと腰を引く。すっかり傑の形を覚えてくれた具合のいい居場所からお暇するのに、実はいつもそれなりの精神力を要していたのだが、もうその必要も無い。
本当はここも今までのようにじっくり擦り上げてやった方がいいのだが、いい加減下半身が熱暴走を起こしそうなので最適解を無視して一気に突き上げた。
「あぅ゛うっ!」
「ごめん、ちょっと我慢な」
イッた直後にこの深さと速度は辛いと解っているが、もう止められそうにない。久しぶりに扱かれる感触が良すぎて視界が揺れる。
「んぁッ、あ、あぁ゛っ、あぁあっ!」
「は、……やべぇなこれ……っ」
「ひぁああっ!?ふ、かい、ふかいぃっ!」
一突きごとに浅くイって痙攣する内壁の具合が最高過ぎて、深いストロークではとても保たない。堪え性の無さを申し訳なく思いながら小刻みに最奥を突く動きに切り替え、いやいやと首を振っている悦の頬に手を添えて半ば無理矢理視線を合わせた。
「……”よし”」
「ッ――――!!」
絞るような締め上げに今度は逆らわず、ぐん、と仰け反った悦の背を片手で支えながら、これも久しぶりの無理矢理ではない射精の感覚に大きく息を吐く。
「はぁ……」
「―――っひ、……はひ……っッ」
見開かれた瑠璃色が、二度目とは思えない慣れの早さでうっとり細められるのを真上から見つめながら、添えていた手を下ろしてびく、びく、と跳ねる背をシーツに寝かせ、頃合いを見て一度モノを抜く。
こぷ、と好き勝手に注いだものが溢れてくる様が、その感触だけで高さを増す波に攫われている悦の表情と相まって凄まじくエロい。こんな扇情的な恋人を前に冷静さを保とうとするだけ無駄なので、出したばかりだと言うのに相変わらずの腕白さの自身についてはもう諦めることにした。
「次、どの体位がいい?」
「……ば、っく……」
「わかった」
お利口に膝を抱えていた両腕を解かせてうつ伏せにひっくり返し、貪欲に期待に震える腰を両手で掴んで膝を立たせる。やはり加減した分だけ縛りが軽く、”溜め”の長さがかなり影響しているようだ。本当はもう少し慣らしてからにするつもりだったが、この反応なら耐えられるだろう。
「ちょっとキツいやり方するけど、”待て”出来るか?」
「できる……っ」
「イイ子だ」
ぎゅっとシーツを握り締めて頷くうなじにキスを落として、リードの代わりに両手で腰を掴んだまま、三夜をかけて覚え込ませた動きで根本まで挿れる。
「んぅうぅ……ッ」
猿轡の代わりにシーツを噛む愛らしさに目を細めながらゆっくり引き、回転率と生存率を上げる為に激しいやり方に傾倒した悦が嫌いなペースで、逃したいほど大好きな所を緩慢に擦り上げると、塞いで縛られていない唇はすぐにシーツを離した。
「はあぁっ、ぁ、あー……っ!」
「ここ、好きだろ?」
「っす、き……すき……ッあぁぁぁ……!」
”躾”の最中に求めていたのとはかけ離れた緩やかさの筈だが、悦は濡れた頬に新しい涙を伝わせながら何度も頷く。普段なら連続でイってしまうので時々外して刺激を散らしてやる必要があるが、”待て”がかかっている今は勝手に動いてはいけない、から転じて勝手に気持ちよくなってはいけない―――のは無理だから勝手にイってはいけない、という精神的な制限が掛かっているので、小細工も手加減も不要だ。許容量の限界まで狙いを反らさず責めてやれる。
「気持ちいい?」
「いいっ……ぁんン……きもちいぃ……!」
「よかった」
これを機にがりがりと理性を削り取るばかりが最高のセックスではない、と覚えてくれればこの”躾”は大成功だ。身も世もなく暴力的な快感に泣き喚いている悦も可愛いが、喚く余地も与えられずにじっくり丁寧に嬲られてか細く啜り泣く顔も捨て難い。
悦の休暇が終わってそうそう時間をかけていられなくなったとしても、可愛い恋人から強靭に鍛えられた矜持や覚悟や意地を優しく剥ぎ取ってやる方法は、他に幾らでもある。
「んぅぅ、うぅっ……すぐる、すぐるぅ……ッ」
「あぁ、ここばっかりじゃ飽きるよな」
「ひぁああっ!」
「ちょっと強いか。このくらい?」
絶頂一歩手前のところでずっと宙吊りにされている悦が終わらない快感に怯え始めたので、ごちゅん、と突き上げた最奥に狙いを変えた。一番好きなノックするように小刻みに突く動きに加えて、時々押し上げたそこをぐちぐちと捏ねるように抉る。
「あっ、ぁ、あ、あぁッ……んゃあぁぁ……っ!」
「さっきの方がいい?」
「ちがっ……ぁあぁ……っぬ、ぬかない、で……!」
「抜かねーよ」
人間を人間扱いしない外道ばかりを相手にしていた悦は、S字を抜かれるのが嫌いだ。そこを許すと体を破壊される可能性が格段に上がるので、殆ど怖がってすらいる。ゆくゆくはその辺りも壊されるからではなく、そこでしか満足出来なくなったら困るから、に認識を塗り替えてやりたい所だが、いくら覚えが早いとはいえ詰め込みは禁物だ。人格に影響が出る。
「悦が好きなことしかしない、って言ったろ」
「はぁ、ぁああっ……んん……ッ」
”躾”中に何度も繰り返し教え込んだ角度と深さで腰を止めると、切なげにシーツを引っ掻きながら小さく頷いた。覚えたての深い快感を求めて蜜のように蕩けた瑠璃色が、打算も演出も無く哀願だけを湛えて傑の顔色を伺う。
「す、好き……がまん、するの……すき……っ」
「自由に動けないのも好きだよな」
「うん、ぅん……すき、だからぁ……っ」
「だから?」
求めた結果与える為に促した傑の膝を、これ以上は無いと断言出来る最適の力加減で、きゅっと爪先を丸めた悦の両足が挟み込んだ。
「よし、って……言って……!」
……ああ、もう。どうしてやろうか。
「……最高だな、お前」
それ以外の感想が無かったのでしみじみと呟いて、傑はゆっくり腰を引いた。また一息に突き上げられて連れて行かれる、と思った悦が縋るようにシーツを掴んでいるのが微笑ましい。
勿論、あんな殺し文句を貰って二番煎じを返すつもりは無いので、浅い所から順番に、じっくり感じるところを擦り上げながら貫き、ゆるゆると抜ける寸前まで引いて、奥へ誘う内壁に逆らわず緩慢に突き上げる。
「ぁ、あ、ぁ……っ?」
好みを差し引いても今の”最適解”である深く緩いストロークの意図に、4度目で気づいた悦が首を巡らせて傑を振り返った。鍛えられた観察眼で藍色の瞳に哀願を切り捨てる素振りが無く、約束を違える気も無いことを読み取って、微かに首を横に振る。
「や、やだ……!」
「ヤクに負けるわけにいかねぇからな」
「ッ……これやだっ……はやく、はやくして……!」
「大丈夫だから力抜いてろ。いい子だから」
一気に注ぎ込むよりも、時間を掛けてじわじわ注ぐ方が表面張力の限界まで”溜め”られるのは自明の理だ。また知らない所に、しかも知らないやり方で連れて行かれる、と怯える悦の手を握り、指の間を掠めるように撫でて余計な力が抜けるように促す。
極限の緊張状態を保つことで正気を守り抜いてきた悦は、その緊張が緩む危険性を本能で知っている。雑音を排して、それだけに集中して、身も心も溺れる快楽がそれ以外とは別物だということも、もう解っている。経験がある分恐れがあるのは当然だが、幸いにして傑は純血種だ。人間を壊す方法も、絶対に壊さない方法も熟知しているので、自我の限界まで溺れさせてやれる。
「だ、めっ……ゆ、っくり、だめぇ……!」
「ちゃんと降ろしてやるから」
「あぁ、ぁっ、あッ……い、言わないで、いま、だめ、だからぁッ、言わないでぇ……っ!」
「”よしよし”、怖くない怖くない」
「ぁ゛っ……~~~~~っッ!!」
お互い必要無いのでスイッチとして強く深く突き上げることもなく、背後から抱きしめて耳元に囁くのと同時に目を見開いた悦が、腕の中で一度ぎくんと大きく跳ねた。
声にならない声と共に引きつった指が傑の掌に爪を立て、強烈な締め付けに息が止まる。駆け上がった勢いのままに脳裏で弾ける快感と多幸感は、やはりそれ以外とは別物だ。最後の一滴まで搾り取ろうと痙攣する体が、より深く重い絶頂を上手に受け入れてとろんと瞳を蕩けさせる自我が、腕の中にすっぽり収まってくれた全てが愛おしくて仕方がない。
「……ひっ……ひぃ……っ…!」
「可愛いな、お前」
箍を飛ばしてベクトルを捻じ曲げた愛情が抑えられず、抑える必要性も無く、傑は与えた快感に深く浸った悦を抱き上げた。掠れた甘い悲鳴を上げてかくん、と肩に乗った頭を撫で、不規則に震える体を壊れないように抱き締める。
「うぁ……ぁ……っ」
「……はは、」
躊躇いがちに、それでも確かに応えるように背中に回った腕にきゅっと指先で抱き返され、思わず笑ってしまった。
この愛しさと幸福の全てを表す言葉は、さしもの純血種にも解らない。
「……よく飽きねぇな」
バスタブの中で胸板に凭れた悦が沈まないよう片腕で腰を抱き、もう片方でシーツを握ったり傑の背中に爪を立てたり髪を引っ張ったりと大活躍だった古傷の残る手をマッサージしていると、半分微睡んだ恋人が枯れた声でぼそりと呟いた。
「飽きる?」
「こんなの、……意味ねーのに」
言いながらされるがままだった指先が微かにお湯を掻き、ようやく傑は隠された主語を察する。ベルガモットのアロマキャンドルが燃え尽きて、その残り香も薄れるまで貪り尽くして満腹だったというのもあるが、それ以上に埒外過ぎてすぐには考えが及ばなかったのだ。
察してしまえば成る程、らしい言葉ではある。優しさや気遣いを一時でも受け入れてしまったら、Z地区の男娼としては、しかも”群れ”の生存率を上げるために金払いが良く外道な”上客”ばかりを引き受けていた悦にとっては、自分の耐久値の低下を招きかねない。正当な進化を経た生き物の、慣れと順応という脆弱な対応策を最大限活用しようと思えば、確かにそれは最適解だ。
人間相手なら。
「ぁ、……し、躾は……よかった、けど……」
邪魔なので早々に壊してやりたいが、根が深いので根幹に影響しかねない。早急かつ慎重にぶち壊そう、と考える傑の沈黙を不興と取ったのか、ぽそぽそした声で悦が可愛い補足を入れてくれる。勿論そんなことは百も承知だが、言葉で「よかった」と伝えられるのは純粋に嬉しかったので、頭を撫でておいた。
「好きでやってンだから、飽きるわけねぇだろ」
「……」
「それに、意味ならあるし」
今はな、誰だってそう言うんだよ、と言いたげに足の爪先を動かした悦の腰に両腕を回して、傑はしっとり濡れた蜂蜜色のつむじに鼻先を埋めた。
境遇を思えば疑い深くなるのは仕方がない。そういう所も可愛いし、邪魔な箍を全て弾き飛ばした今の傑には純然な事実として敵はいないし、過酷な環境を生き抜いてきた悦の本能の方は完璧な安寧を提供できる傑の味方だ。何も問題は無い。
「意味?」
「俺が楽しい」
「……ンだそれ」
呆れたように溜息を吐く悦を抱いたまま、傑は心地いいぬるま湯の中で目を閉じる。
目を閉じたままでも、言葉や態度がどれだけかけ離れていても、選んで掴んだ愛しい道連れが自分でも気づいていない本心から望むものくらい、純血種には手に取るように解るのだ。
Fin.
「あの人をよろこばせたい」というのは、とてもピュアな愛の形。
傑も、そして悦も、互いをよろこばせたい。
つまりこの2人はピュアです。
ピュアです。
