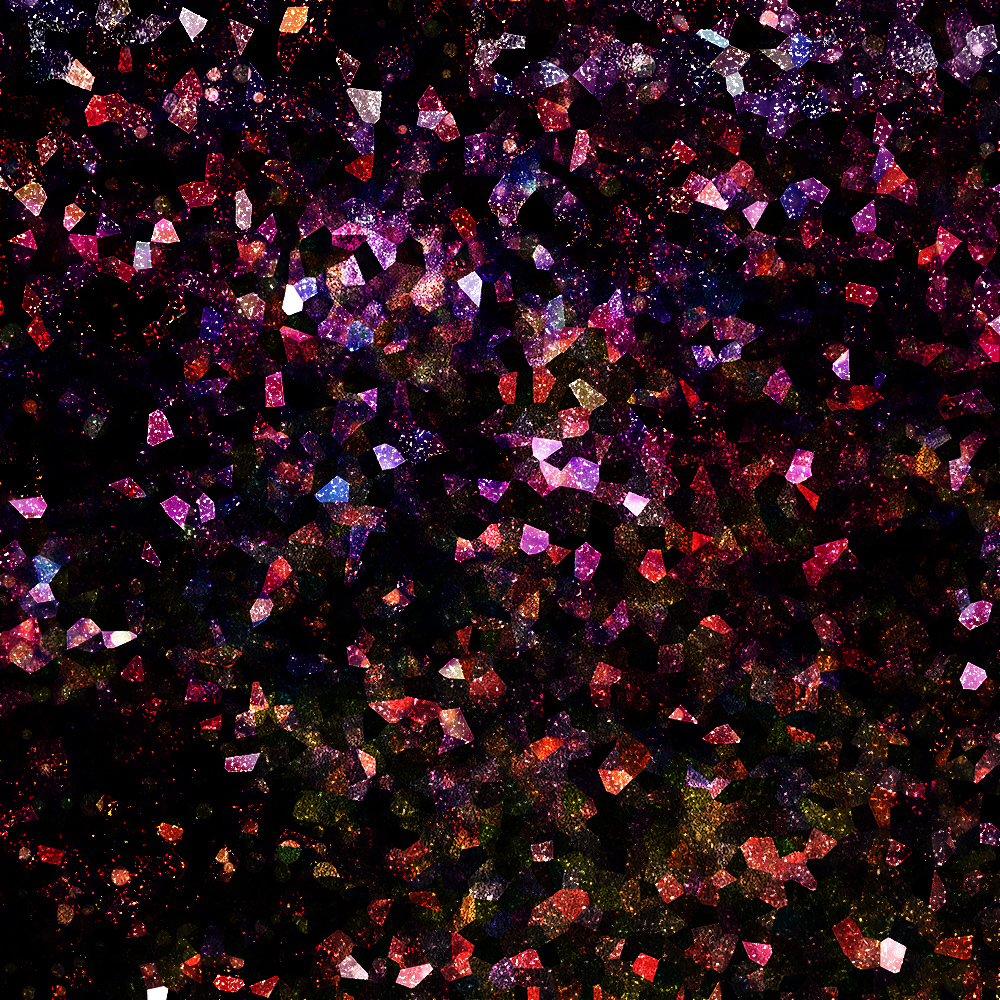
After E
結果から言えば、悦が”保った”のは2分足らずだった。
相手が傑じゃなく、テンションに任せたガン堀りで、双子が”観客”だったなら10倍以上は確実に保たせたが、兄貴はともかく怯えてご主人様の背に隠れた幽利から金を取れるわけもなく、淫乱専用拷問器具だと思っていた首輪の地位が玩具に落ちるくらい際っきわの極限を攻めた寸止めをされて、その上相手は傑だ。保つ筈が無い。
泣きじゃくって哀願と懇願を繰り返すZ地区出身で壱級指定賞金首で元男娼と、それを簡単に捻じ伏せて愉しそうに嬲る純血種の零級指定、という構図にビビり散らして興奮どころか心配も出来なかった幽利には悪いと思っている。鬼利には微塵も思わない。パンピーとしては度を越した兄貴の方は完全に見世物として楽しんでいたし、悦が幽利とのアレコレを嘘偽り無く本心から謝罪するなんて思ってもいないからだ。
Z地区育ちの貞操観念と道徳と倫理観が終わっていると、知らない最高幹部ではないだろう。
「ごめっ、んなざぃい……イかせて、ぇ゛……っ!」
「20。……どこで読んでるの?」
「全部。こいつ隠すの上手いんだよ」
「溜めも変えてる?」
「じゃねぇとすぐトぶからな。インターバル無しでずーっと気持ちいい方がイイだろ?」
「成る程」
こんな調子で傑が鬼利と喋るのも、メンタル面から悦に多大な追い打ちをかけた。本当にいつもの調子で平静に喋るものだから、その間でぐちゃぐちゃにされている自身の”獲物”感が際立って、精神的にとてもキた。勿論性的な意味でだ。シチュエーションだけで3回はイきかけたし、曰く悦の全部を見てそれを操っている傑は当然のように脳イキさえ許してくれなかった。
総評としては、悦だけがどろっどろのぐっちゃぐちゃにされる最高の乱交だった。結局鬼利のカウントがどこまで進んだのか、シャットダウンするように気絶した悦は知らないし、正直な所興味も無い。
互いのカップルの趣味嗜好が合致した素晴らしいスワッピングだったと思う。それ以上でも以下でも無い。
―――それで終わりの筈だったのだが。
「ただい、まっ」
「……」
スポーツ飲料のボトルと箔押しされた紙箱を両手にして、背中でドアを押し開けようとする傑を、悦は30センチ未満の隙間から寝室の中に引っ張り込んだ。
シャツのボタンが飛ぶ勢いで胸ぐらを引かれて語尾を跳ねさせた傑が、引き摺られながらも片足でドアを押して紙箱が潰れるのを回避する。C地区に先月出店したケーキ屋の箱だ。パンケーキもワッフルもジャムも今丁度切らしているから、狂乱の翌日の甘やかしに相応しい朝食として悦が寝ている間に買いに行ったのだろう。今はどうでもいい。
「あっぶね、……悦?」
「……」
「どした?」
「……」
気遣わしげな声をフルシカトしてベッドの側まで引き摺り、手首を入れて胸ぐらを掴んだまま、自分だけボスンと後ろ向きにベッドに座る。悦の動きに合わせて抵抗せずに身を屈めた傑から紙箱を取り上げ、ケーキに罪は無いので傾けないようにサイドボードに置いて、ペットボトルは頑丈なので裏拳で床にはたき落とし、腰の後ろに両手をついて眼の前の傑を睨み上げた。
「腹がおかしい」
唸るような声で言った悦に、胸ぐらを掴まれた位置のままで傑が視線を下げる。
「あー……痛いとか苦しいとかじゃねぇよな?」
「ちっげぇよ」
誰があんな酒無しヤク無しド健全乱交程度でヘバるか。ことさらに荒っぽく舌打ちをすると、だよな、と頷いた傑が肩幅以上に開いた悦の足の間に膝をついた。清潔なリネンのパジャマをお行儀よく着せられた腹から顔へ、わざわざ自分から位置を下げた藍色で見上げつつ、空になった手の片方が宥めるように悦の太腿を撫でる。
「鬼利にやられたやつ?」
「それ以外ねぇだろ」
「ガチっぽかったもんな、アレ」
「二度寝出来なかった」
「ごめんな、疲れてるのに」
「ちっげーよ」
ベッドの上で出すのとはまた違う、胸焼けする程甘い声で窒息しそうな程甘やかそうとしてくる傑に、悦はもう一度舌打ちをしてボタンが一つ飛んだ胸ぐらを掴んだ。相変わらず包容力と甲斐性全開で抵抗しない化け物を片腕で引き摺り寄せ、ベッドに寝転んだ自分の上に覆い被らせる。
視線が揺れないように傑を睨んだまま、短く息を吸って覚悟を決めて、言った。
「……抜け」
低い声を聞いて、逆らわずに悦の体の脇に手を突いた傑がぱちりと藍色を瞬かせる。
主語も無い尊大な命令だったが、この流れで”どこ”の話か解らない純血種じゃない。
「いいのか?」
「いい」
「それ以外がいくらでもあるのに?」
「……ぅ、……」
「な?他のでいいだろ、デザートなんだし」
ド正論をつかれて解りやすく言葉に詰まった悦を見下ろす藍色が、ぐらりと底を煮え立たせかけた熱をあっさり引っ込めて甘ったるく溶ける。砂糖菓子の蜂蜜漬けよりも甘やかして説き伏せる時の目だ。待てよ諦め早すぎんだろ変態の癖に。
「お前、……傑だって」
ここを逃せば次に腹を括るのにいつまで掛かるか解ったもんじゃないので、化け物がその自制心やら激重の愛情やらで抑えつけた熱を戻す為、手首を捻って胸ぐらを絞りながら慌てて口を動かす。傑の言う事は至極その通り過ぎるし、こいつなら本当にいくらでも「それ以外」を出せるという確信もあったが、それじゃ駄目だ。
10年以上も前に”商品”の危機を感じて命懸けで引いた境界線は、色々あって既に本能のレベルにまで食い込んでいる。頭で覚悟を決めるだけで済むならこんなにダラダラ引っ張って無い。生き残る為なら理性も感情も置き去りにする体の方がバグっている今じゃなければ駄目なのだ。
傑なら、そして今なら、魔王が別次元と称した快感で上手く境界を塗り潰してくれる。
「いい加減、ぶち込みたいだろ。……根本まで」
「……」
慣れた手つきで卑猥に下肢を這った指先に、傑は応えず、覚悟の程度を探るように軽く首を傾げた。
自棄になったわけ、でもあるがそれだけでは無いので真っ直ぐに藍色を見返すと、きっとそんな悦の心境の何もかもを察した美貌がふっと微笑む。
「……疼いてるのってどこ?」
屈めていた上体を起こしてマットレスに膝で乗り上げながら、傑は襟から離させた悦の手を腹の上に導いた。どこまで抉られたいのか教えろと、言外にそう命じて見下ろす藍色の底がぞわりと煮立つ。
「……ここ」
「ふーん、そこね」
より一層じんじんと切なく疼き出した所をパジャマの上から撫でると、口調だけはのんびりと相槌を打った傑がベルトのバックルを外す。急ぐわけでもなくボタンを外し、チャックを引き下ろして、引くタイミングを逃して太腿辺りに彷徨ったままだった悦の手を下着越しに押し当てた。
「コレだと、そこじゃなくて」
「っ、」
「ここまで、入れンだけど」
「んんっ」
指2本分、悦の手を上にずらして重ねられた傑の掌が、ぐり、とそこを押し込む。
「……それでもいい?」
勿体ぶったお伺いという建前の最後通牒に、悦は指に触れる下着を引きずり下ろす事で応えた。
悦としては、ローションぶち込んでガンとぶっ込んでそのままの勢いでバツンとぶち抜かれる、くらいの覚悟をキメていたのだが、勿論あの傑がそんな余裕もテクも語彙力も無い性急な行為を良しとするワケが無かった。
それについては考えてみれば当たり前だし、持ち込むまでにいいだけ煽り散らかしたし、昨日の名残でまだ柔らかい所にじれったくローションを馴染ませられても悦は我慢した。傑のモノと言わず太腿と言わず粘液塗れにする勢いでローションをぶっかけるだけに堪えた。傑は焦らすのが好きなサドだし、サドというものは早く早くと強請ると意地悪く勿体つける面倒な生き物だ。焦らしている分だけ自分も焦らされるんだからいっそマゾなんじゃないかと思う。
だから悦は我慢していたのだが、ようやく挿れたと思ったサドだかマゾだか解らない野郎がこともあろうに前立腺を当て堀りしてきやがった所で、ついにその我慢も限界を迎えた。
「あ゛ぁっ、クソッ……抜けって言ってんだろ!」
バックで挿れている傑を肩越しに思いっきり睨みつけて叫ぶ。これ以上余計な真似をしないように両手は指を絡めて握って顔の横に突かせているので、こんなにガチガチにしてやがる癖に呑気に苦笑する美貌はすぐそこだ。
「だらっだらヤってんじゃっ……んぅっ、やめろそれ!」
「俺のはそんなにチャチじゃねぇし、お前だってそんなにユルくねぇだろ」
「や、めろって言っ……あぅううっ!」
「そんなに構えられてちゃ入るモンも入らねぇんだって。いい子にイってろよ」
「あぁあっ!」
何がいい子にだせめて奥でイかせろふざけんな、と全身全霊で思ったが、これまた昨日の名残で腫れている前立腺をごりごりに押し潰されて眼の前に火花が散る。悔しさに歯噛みしながら思いっきり腰を上げてみたものの、傑はその分だけ腰を引く。悲しいかな、悦と野郎とでは足の長さが絶望的に違った。
「ふーっ、ふーっ……傑ぅう……ッ」
「落ち着けって。気持ちイイだろ?ここも」
「ぁあ゛ぁぁっ……!」
「あー、わかったわかった。じゃあ5回。5回イったらな」
2、3本へし折る勢いで絡めた指に逆関節に力を込めると、ようやっと悦が焦らしプレイを愉しめる精神状態ではない事を理解した傑が譲歩案を出す。5回だって悦は多すぎると思ったが、叫ぼうとした文句はあっさり振り解かれた右手で腰をシーツの上に押さえつけられ、ふぎゅ、という間抜けな声に変わった。悲しいかな、悦と野郎とでは膂力も絶望的に違っているのだ。
「これっ、これだめ、なやつぅっ!」
「んー」
押さえつけられたまま一番イイ角度で前立腺を捏ねられて、自由になる足をじたばたさせながら抗議する悦に、傑はあまりにも適当な相槌を打つ。宥めすかしたって大人しくならないから、もう強制的に大人しくさせようという魂胆だ。
この野郎、と心底思うがいくら腹を立てた所で傑の手を跳ね除けることは出来ないし、体内を透かし見ているような正確さで前立腺をカリに引っ掛けられて転がされる快感が無くなるわけでも無い。シーツに縫い留められたまま上から体重をかけてしこりを押し潰され、悔し紛れにシーツを叩いていた足がぴんと伸びる。
「ひあぁあッ!」
「いーち」
「あッ!?とめっ、やだ、やぁあああっ!」
「にーい」
「んぅう゛うぅっッ……ふっ、ふぅう゛うっ……!」
「さーん」
「いぁあ゛あぁあっ!やぁあ゛っあぁああっ!」
「よーん」
「あ゛ーっ、あぁあーーーっ!」
「よし、5回おわり」
「んぅ゛っ!」
どれだけ痙攣しても1ミリだってシーツから浮かなかった腰を急に引き上げられて、浅い所ばかりを甚振っていたモノが奥深くに入り込み、ぎくりと悦は全身を強張らせた。
連続絶頂によってぐちゃぐちゃに溶かされていた筈の頭が、キンと音を立てて冴える。
カウントダウンは5回で、それは終わった。やっとだ。願い通りの筈だ。体の強張りは取れないがもうこの際多少痛くっても構わない。うじうじぐだぐだと日和りやがる体が勝手に逃げを打たないように、シーツを握る右手に力を込める。そう言えば遠い昔の”前回”の時は初撃で吐いた気がするので、二の轍を踏まないように知らず詰めていた息を鋭く吸った。
吸った分を細く吐き出して、そこを開くことを意識する。幾度となく死線を越えて来た集中力の全てを体内に注ぎ込んでいる悦を驚かせないようにしてか、傑は普段なら焦れて泣き出すような緩慢さでラスト1センチを進めて、キスをするよりも柔らかく曲がり角へ先端を押し当てて、そして。
そして、2呼吸待ってもそのままだった。
「……いい加減にしろよてめぇ……!」
「しー」
もう、殴る。そう心に決めて右拳を固めながら捻ろうとした上半身は、この期に及んでは煽りにしか聞こえない声と共に背中にぴったり胸板をくっつけるような形でシーツの上に抑え込まれたが、別に殴るのに支障は無い。瞬時に拳から裏拳に変えて躊躇なくこめかみに向かって振り抜いた悦の右手を、傑は肩口に顔を埋めるようにして難なく避ける。
それならと、殴れないなら耳の一つか皮膚の10センチでも食い千切ってやるつもりで鋭く振り返った先で、深い藍色と目があった。
「悦」
悦の怒りよりも遥かに高温に煮え滾った瞳のままで、甘ったるい低音が名前を呼ぶ。
声自体には何を咎める響きも無かったが、これ以上八つ当たりに付き合うつもりはないと、うつくしく、おそろしく、細められた藍色がそう告げていた。
「……ごめ、ん」
「怒ってねぇよ」
途端にしゅんと怒りが萎えて、振り上げたままだった右手を下ろしながら謝る悦に、傑はいつもの調子でキスをする。
思えば、羞恥だの意地だのが邪魔をして形ばかり反抗する悦を適当な所で黙らせて事を先に進めるのも、いつもの通りだ。
そう、傑は最初からいつも通りだった。抜くの抜かないのと大騒ぎしているのは悦だけだ。
あまりにも情けなさ過ぎて認めたくは無いが、覚悟を決めたつもりでいて、結局は怖かっただけなのだろう。認めてしまえばこんなに単純な話も無い。自分の事ながら頭が悪すぎて嫌になる。
「もうちょい足開けるか?」
「ん……」
目元から頬、耳、首筋、うなじ、と順番に落とされるキスに従って起こしていた頭をシーツにつけながら、太腿を撫でる手に促されるまま足を開く。昨日まで”根本”としていた箇所からもう一段進む場合、もっと突き出すくらいに開いた方がいい気がしたが、馬鹿が馬鹿なりに考え込んだ所で馬鹿なことになるだけだと学んだばかりだ。
「ぅんっ……ん、ぁあ……っ」
余計なことはせずにその辺の調整は傑に任せて、揺するように緩慢な動きで慣らし直されるナカの感覚に意識を向ける。神経を尖らせて集中することはもうしなかった。わざわざそんな真似をしなくたって、とっくに傑好みに開発されきった悦は気持ちいいことが大好きだ。
ただ強弱をつけて押し上げられるだけだった所を軽く突かれてじんと尾骨が痺れ、それを呼び水にして八つ当たりの怒りが脇に追いやっていたそこの疼きを思い出す。一緒に昨夜の目が眩むような快感と、ただイけないだけじゃなかったもどかしさも。
「調子出て来たな」
「はぅううぅ……っ!」
「そのまま、息止めるなよ。ちゃんと緩んできてる」
トロ火で炙られているような所を壁1枚隔てて抉りながら、傑はいつもの調子でがくがくと震え始めた太腿から腰へと右手の置き場を変えた。腰骨を捉えてそこを掴み、逃げ道を塞がれたとやっぱり体を強張らせてしまう悦に構わずに、矛先を慣れた角度からほんの少しだけ変える。
「うあっ、あ、ぁあっ」
「んー……もうちょい……」
「はーっ……はぁあっ……ぁ、あぁ……っ!」
「あぁ、そうそう。その感じ」
慣れない角度で緩く突かれる度に詰まりそうになる息を吐く、ということ以外は何一つ意識的には出来ていない悦のどこかしらをおざなりに褒めて、傑はZ地区育ちも気づかない自然さで繋いだままの左手をひっくり返した。
ぐっとそこに体重をかけられてようやく、指先に触れていたシーツが無くなった事に気付いた悦の意識が一瞬そちらに逸れ―――実際の所は悦がいくら緩めようが締めようが関係なく、ただその一瞬だけを狙い澄ましていた傑は、掴んだ腰を引き寄せる。
「あ゛ッ」
全身を総毛立たせたその感覚が何なのか、健気に傑を信じていた悦には一瞬分からなかった。痛みも苦しさも吐き気も、覚悟していた何もかもがあまりにも何も無さ過ぎた所為だ。
一拍遅れて抜かれたのかと気づいて、じゃあこれはダメな所へ入りこまれた怖気かとまず思って、いやでも、と思い直した思考がスコンと抜ける。数秒か、それ未満かの空白の後に背骨を起点に全身の神経へ走った電流は、慣れ親しんだそれとは桁が違った。
重い。
「……あ、ぁ゛っ?……あ……ッはぁあ゛あぁあ……っっ!」
重さに耐え兼ねた体が無意識の内に上半身を引き上げるようにして背中を丸め、くぷん、と奥の奥から抜ける感触に悦は全身を鳥肌立てて額をシーツに擦り付けた。入っていたのは先端のほんの一部だけだというのに、そのほんの少しが曲がり角から出ていくだけで重い絶頂が視界を明滅させ、全身が細かく震える。
「なんで逃げンだよ。こうして欲しかったんだろ?」
「はッ……はぁ゛っ……!」
言葉とは裏腹に逃げた分を引き戻すことも止めることもなく、腰から離した手で普段とは逆方向に撓った背を撫でる傑を、悦はまだ痙攣の収まらない体をどうにか捻って振り仰いだ。
元男娼が仰け反らずに背中を丸めた事の意味を、薬を打たれた頭でも反射でそう動くよう癖付けた経緯を、きっと当の本人よりもよく理解している化け物は繋いだままの左腕一本分の距離でそこに居て、どう考えても覚悟をキメる方向性を間違えていた悦を愛おしそうに嗤う。
「……壁越しであれだけイきまくるトコを、直だぜ?」
そりゃそうなるだろ。いっそ呆れたように考えてみれば当たり前のことを言われて、悦はまだ感覚の戻りきらない左手できゅっと傑の手を握った。
10年以上振りの2回目でこんなに凄まじく気持ちいいなんて絶対におかしいと思っていたが、何のことはない。悦だけが気づいていない内に必要な準備も下拵えも、全て済んでしまっていただけの事だ。境界線が食い込んでいたのは本能だけではなく頭の方もそうで、体はラインのぎりぎり外からもう幾度となくそこを嬲られる快感を教え込まれていた。昨日の開発用器具は無意識にとって都合の良かったきっかけに過ぎない。
「……気長すぎ、だろ」
「そういう趣味なんだよ」
年単位の開発を今更思い知って愕然と呟く悦に、嫌がっていた行為をあらゆる手管を使って泣きながら懇願する程大好きにさせるのが趣味の傑は軽く首を竦めて見せた。
冗談めかした仕草が逆に空恐ろしく思えてぞっと身を縮めた悦の背の上で、長い指先がたとと、と愉しげに踊る。
「そんな顔すんなって、お陰で気持ち良かっただろ?痛い方がイイなら次はそっちでいくか?」
「つ、ぎ」
「そう、次」
浮いた骨の形を辿っていた手にぐっと力を込められて、丸めていた背を強制的に伸ばされた悦はシーツに縫い付けられた。上半身を抑えられて先にも後にも行けなくなった腰だけを高く上げたまま、ぐち、と押し当てられる感触に小さく悲鳴を上げる。
「さっきがここ」
悦が震えるばかりで本気で嫌がらないのを確認してから背を離れた指が、骨盤と背骨の継ぎ目辺りをとんと叩いた。
「次はここまで挿れる」
次にさっきより指2本分先を。
「……痛くして欲しい?」
「っ……!」
「だよな」
ぶんぶん首を横に振った悦に小さく笑って、数分前までとは別の意味合いで強張る体を宥めるように撫でながら、いっそ無造作とも思える動きで傑は腰を動かした。
ただ挿れるのではなく、動かした。
「あ゛――――っっ!」
逃げられないように悦の腰を押さえたまま、さっきと同じ深さまで曲がり角を越えて、無理にそれ以上突っ込むような事はせずに、抜けきらない場所まで引く。ただそれだけで悦は栓でも抜かれたように精液とも潮ともつかないものを吹き出したが、目標はあくまでもカリまでを挿れることなので、傑は腰を止めてくれなかった。
ついさっき口を開けることを覚えたばかりの場所を、もっと太いものを挿れられても痛まないように柔軟に、従順にさせる為に、曲がり角のそのすぐ先のとびきり敏感な粘膜を優しく叩く。受け入れるのに慣れた体が上手くこの致命的な快感を受け止められるように、簡単には意識を失わないように、どんな形に広げられているのか教え込むような緩慢さで。
「しょ、こッ……とんとん、しないれ゛っ……!」
「んー?」
「あたま、おかしくなる゛、ぅっ……い、ぐッ……おも、ぃい゛いっっ」
「うんうん、重いな。もうちょいで全部入るから頑張ろうな」
「あぐぅううう……っ!!」
とんとんなんて可愛いものではなく、体液を巻き込んでにぢゅにぢゅと突かれている所にほんの少し体重をかけられて、悦はまたぷしゃりと腰下のシーツを濡らした。相変わらずなにを吹いたのかは解らない。そんなことをかんがえるよゆうがない。
距離にすればほんの1、2センチの、ピストンとも呼べないような緩い抽挿を繰り返されているだけなのに、今や悦の頭の中は爆竹でも投げ込まれたような有様だ。間断なくイき続けて痙攣する内壁はきっと前立腺だって揉みくちゃにされているに違い無いのに、結腸を優しく嬲られる快感が信じられないほど深すぎてそちらには全く意識が届かない。
無理だ。こんなの頑張れない。そんな次元の話じゃない。
「いれ゛てっ、い……れてぇ゛ッ」
「まだ早ぇって。痛いのヤなんだろ」
「いいっ、いいから゛ぁっ!」
「しょうがねぇなァ」
ガチガチと奥歯を鳴らしながらの懇願に呆れるどころか、悦に見えていないのを良いことに待ってましたとばかりに笑って、傑は曲がり角を甚振り続けていた切っ先を一度完全に抜いた。ひゅう、と笛の音のような音を立てて悦が深く息をするのを待って、今度は一切の加減無しに突き入れる。
「―――!」
体の奥の奥から響いたぐぽん、という音に、なけなしの理性か本能によってまた頭がキンと冴えた。
死んでも是としなかった行為を示す音にシーツに涙を吸わせていた顔をがばりと上げて、逃げようとしてか殺そうとしてか、理性が追いついていない反射の動作でベッドヘッドの方を、そことマットレスの隙間に隠したナイフを見た瑠璃色が一度の瞬きで完全に乾く。生存に必要の無い要素を瞬時に切り捨てた五感は極限まで研ぎ澄まされ、武器への距離を目測しながら肘を伝った汗がシーツに落ちる音を聞き、全ての動きを制限している腰に置かれた掌を知覚した。
何の殺傷能力も無いシーツを握っていた右手を開いた辺りでやっと理性が追いつき、まず深く吸えない息苦しさを思い出す。重い熱と質量が境界線の内にまでみっちりと詰め込まれているからだ。汗だくの肌に張り付く布では無い感触。自分よりも低い体温。
「―――……あ、ぁ」
そう誂えたのかと錯覚するほどぴったりと密着した肌の奥に骨盤の硬さを感じた瞬間、一度の瞬きで元通りに瞳を潤ませた悦はぱたりとシーツに沈んだ。
はいってる。思わず漏れた譫言のような自分の声を聞いてようやく、ついに本当の意味でそこを”抜かれた”のだと自覚する。感覚的には鳩尾の上までいっぱいにされているような圧迫感以外にも、隙間無く合わさった滑らかな肌が何よりの証拠だった。
「悦」
詠うような声で呼んだ傑が、殺気と共に図らずも余計な力も抜けた左手を引く。逆らわずに上体を捻って振り返った悦の手を更に引いて、据わった目を笑みの形に細めた化け物は、大騒ぎしながらもようやくその全てを収めた腹に触れさせた。
「ここまで入ってる」
「……ぜ、んぶ……?」
「あぁ。これで全部」
撫でた指に反応した内側がきゅうと確かめるようにそれを締め付け、隙間無く満たされた充足感と視界の端がぱちぱち弾ける心地良さに、とろりと悦は目を細める。ぜんぶ。
―――ああ、それなら。
「おれも、これで……ぜんぶ」
どこかを抉るか切るかして新しい穴を作らない限り、悦の方もこれで、本当に全部だ。
初めてで無いのが少し申し訳ないけれど、それはお互い様だろう、とふにゃりと眼尻を下げた悦の手を、長い指を深く絡め直した傑が握り返す。
「……そーいうこと言うなよ」
「でも、ほしかったのは傑がはじめてで」
「………………あのな、悦」
望んでこうするのは初めてだから、と色々が振り切れた所為でふわふわした頭でなんとか説明しようとする悦の髪をさらりと優しく梳いてから、傑は伸ばした右手でシーツに転がっていたローションボトルを拾い上げた。
気の立っていた悦がぶちまけたお陰でもう殆ど中身の残っていない、半円のキャップのそれを悦にも見やすい位置に持ってきて、―――力を込める様子もなく、ノーモーションで握り潰す。
ぱん、と口ではなく底の方から破裂する音に少し理性が戻り、悦は丸くした目で傑を見上げた。
「俺、今ナカでこうなんだよ」
開かれた手の中、純血種の握力で締め付けられて中程から潰れたプラ容器から、もう一度傑に視線を向ける。
「ちなみにカリ上はこう」
「ひぇ……っ」
シュミレーションに適した形状のキャップ上が3本指で捻られ、粘土みたいに絞られて捩れたそれが意味する所とよく見れば完璧に据わっている藍色の両方に、悦はびくっと首を竦めた。
こわい。そこはほぼ処女の癖に相手が相手なら殺人になり得る名器っぷりを知らず発揮している自身のポテンシャルと、そんな風にぎちぎちのめりめりに締め上げられておきながら理性を保って平静に喋っている傑の精神力の両方が。
「な?……だから、頼むから煽ンな。結構ギリなんだよ」
「ゆっくり……ゆっくりに、して……」
「止めろっての。……抜く以外には動かねぇよ、今日は」
ダメ元でお伺いを立ててみた悦に、というよりは自分に言い聞かせるような低い声で呟いて、傑は一度ベッドの外へ視線を反らした。サイドボードと壁の境目辺りを殆ど睨んでいるような鋭さで見ながら深く息を吐き、残っていたローションで濡れた右手で無造作に前髪を掻き上げる。
顕になった額に薄く汗が滲んでいるのを見てもう半歩理性が戻り、悦は圧迫感の所為で浅くなっていた呼吸を深くした。これは、珍しく本気でヤバそうだ。
「……っは、ぁ」
こんなに奥まで犯されるのはほぼ初めてだが、いつもよりちょっと深いだけで場所が変わったわけでも、入っているモノが変わったわけでも無い。それなら理屈は変わらない筈だと、どこに力を入れて抜くべきなのか自身の内側を探る。元Z地区の”鴉”で稼ぎ頭の男娼という経歴はつまるところ、悦が適応能力の鬼であることを物語っていた。
自覚した途端にずんと芯に響く快感を堪えて、加減も技巧も無くただ締め上げていた所をどうにか緩める。そっちに意識を向けると直ぐにでもイきっぱなしになるのはさっきで学習していたから、一旦自分の事は脇に置いて、極限の集中力をもってなんとか置いて、傑を気持ちよくさせる事に集中した。
「ん゛、んッ……ふ……ぁあ……っ」
かつてはどんな真似をされても降りない緩まない鉄壁さで鳴らしたものだが、それは偏に悦の側に受け入れる気が微塵も無かったからだ。どこをどうすれば一番具合がイイのか、知識ならある。
2回目のトライで狙い通りに愛しい熱を具合よく絞り上げる事に成功し、それに連動して膨れ上がった快感に意識を持っていかれそうになりながらも、悦はぴくりと眉を揺らして戻ってきた藍色から視線を反らさずにいた。
「……きもち、ぃ?」
こんな事を真っ最中に聞くのは初心なド素人みたいで恥ずかしいけど、初めにおかしな癖をつけると抜くのが大変だし、折角ヤるなら自分だけじゃなく傑の頭にも爆竹を投げ込んでやりたいので、悦は素直に愚直に自分の巧拙を尋ねる。相手の欲を計るのに一番解りやすい部位を喰い締めながらこんなことを聞くのなんて、十年振りどころではなく初めてかもしれない。
でも、傑には聞いてみたかった。
「最高」
いつもより低い声で即答した傑が起こしていた上半身を倒し、右腕で悦を抱き込むようにしながら肩口へ顔を埋める。
「マジで最高。……悪い、語彙力ぶっ飛んでるわ」
「めずら、し」
「言っただろ、ギリギリなんだよ」
「はぅうっ……!」
それならそういう反応しろよ解り辛ぇんだよ、と笑おうとして、自身の掌ごと傑の左手に腹を揉み込まれた悦は喉を晒した。色々と総動員して意識を反らしていたが、悦の方も傑に負けず劣らずもう限界だった。
「あ゛っ……くるっ、くる、ぅ゛……!」
ずしんと体の芯に落ちたそれに今度は逆らわず、意識をすり潰されるような重く深い絶頂とそれを与えてくれる傑に身を任せる。
「ぅあ゛、ぁっ……~~~~~っ!」
繋がれたままの掌の下で、みっちりと奥の奥まで広げられた粘膜が自分でもそうと解るくらいにぐねりと蠢き、悦は全身を痙攣させながら声にならない嬌声を上げた。爆竹なんて目じゃない火薬量の花火がバン、と暗くなりかけた意識を警告色に染め上げる。
右手でシーツを手繰り、両足を爪先立ちに突っ張る悦を他所に、頭と違って物覚えのいい体の方はすっかりそこでの”やり方”を覚えてしまっていた。外側と同じように痙攣する内壁で自分から傑の裏筋に前立腺を擦り付けてだらだらと白濁を零しつつ、奥の奥にある肉輪がぐっぽり嵌まり込んだカリにしゃぶりついて、少し突かれるだけでイきまくった弱点をも自らの蠕動でもみくちゃに刺激される。
「ひッ……ひぃ゛ッ……!!」
「……ん、ん」
「あぁあ゛あぁあッ!?だめっ、それだめぇッ!」
「無茶言うなよ」
「あ゛ぁあ―――っ!」
ダメだと言ったのに、肩口に顔を埋めたままの傑が耳のすぐ近くで苦笑混じりに囁くものだから、悦はボックスシーツを端の方からぶちぶちと引き千切りながらもう一段深くイった。重く体の芯と精神に伸し掛かる絶頂にもう継ぎ目は殆ど無く、爆竹と花火が交互に弾けている視界は半分以上が暗い。
意識を落とさずにいられたのは、それがせめてもの操の示し方だと思ったからだ。
傑ならそれを汲み取ってくれると信じていた。
「悦……っ」
「ひあ゛っ!」
甘くない、押し殺したような低音で鼓膜を通り越して脳までも犯しながら、宣言通りに動かなかった傑がどくりと一番奥で熱を吐き出す。
「あ゛――……あつ、ぃ………っ」
内側から焦がされるような熱についに隅々まで満たされるのを感じながら、悦は爪を立てて引き止め続けていた意識を手放した。
Fin.
4Pの悦ver.その後日譚。
大騒ぎしながらついに男娼が全て傑のものになりました。
相手が傑じゃなく、テンションに任せたガン堀りで、双子が”観客”だったなら10倍以上は確実に保たせたが、兄貴はともかく怯えてご主人様の背に隠れた幽利から金を取れるわけもなく、淫乱専用拷問器具だと思っていた首輪の地位が玩具に落ちるくらい際っきわの極限を攻めた寸止めをされて、その上相手は傑だ。保つ筈が無い。
泣きじゃくって哀願と懇願を繰り返すZ地区出身で壱級指定賞金首で元男娼と、それを簡単に捻じ伏せて愉しそうに嬲る純血種の零級指定、という構図にビビり散らして興奮どころか心配も出来なかった幽利には悪いと思っている。鬼利には微塵も思わない。パンピーとしては度を越した兄貴の方は完全に見世物として楽しんでいたし、悦が幽利とのアレコレを嘘偽り無く本心から謝罪するなんて思ってもいないからだ。
Z地区育ちの貞操観念と道徳と倫理観が終わっていると、知らない最高幹部ではないだろう。
「ごめっ、んなざぃい……イかせて、ぇ゛……っ!」
「20。……どこで読んでるの?」
「全部。こいつ隠すの上手いんだよ」
「溜めも変えてる?」
「じゃねぇとすぐトぶからな。インターバル無しでずーっと気持ちいい方がイイだろ?」
「成る程」
こんな調子で傑が鬼利と喋るのも、メンタル面から悦に多大な追い打ちをかけた。本当にいつもの調子で平静に喋るものだから、その間でぐちゃぐちゃにされている自身の”獲物”感が際立って、精神的にとてもキた。勿論性的な意味でだ。シチュエーションだけで3回はイきかけたし、曰く悦の全部を見てそれを操っている傑は当然のように脳イキさえ許してくれなかった。
総評としては、悦だけがどろっどろのぐっちゃぐちゃにされる最高の乱交だった。結局鬼利のカウントがどこまで進んだのか、シャットダウンするように気絶した悦は知らないし、正直な所興味も無い。
互いのカップルの趣味嗜好が合致した素晴らしいスワッピングだったと思う。それ以上でも以下でも無い。
―――それで終わりの筈だったのだが。
「ただい、まっ」
「……」
スポーツ飲料のボトルと箔押しされた紙箱を両手にして、背中でドアを押し開けようとする傑を、悦は30センチ未満の隙間から寝室の中に引っ張り込んだ。
シャツのボタンが飛ぶ勢いで胸ぐらを引かれて語尾を跳ねさせた傑が、引き摺られながらも片足でドアを押して紙箱が潰れるのを回避する。C地区に先月出店したケーキ屋の箱だ。パンケーキもワッフルもジャムも今丁度切らしているから、狂乱の翌日の甘やかしに相応しい朝食として悦が寝ている間に買いに行ったのだろう。今はどうでもいい。
「あっぶね、……悦?」
「……」
「どした?」
「……」
気遣わしげな声をフルシカトしてベッドの側まで引き摺り、手首を入れて胸ぐらを掴んだまま、自分だけボスンと後ろ向きにベッドに座る。悦の動きに合わせて抵抗せずに身を屈めた傑から紙箱を取り上げ、ケーキに罪は無いので傾けないようにサイドボードに置いて、ペットボトルは頑丈なので裏拳で床にはたき落とし、腰の後ろに両手をついて眼の前の傑を睨み上げた。
「腹がおかしい」
唸るような声で言った悦に、胸ぐらを掴まれた位置のままで傑が視線を下げる。
「あー……痛いとか苦しいとかじゃねぇよな?」
「ちっげぇよ」
誰があんな酒無しヤク無しド健全乱交程度でヘバるか。ことさらに荒っぽく舌打ちをすると、だよな、と頷いた傑が肩幅以上に開いた悦の足の間に膝をついた。清潔なリネンのパジャマをお行儀よく着せられた腹から顔へ、わざわざ自分から位置を下げた藍色で見上げつつ、空になった手の片方が宥めるように悦の太腿を撫でる。
「鬼利にやられたやつ?」
「それ以外ねぇだろ」
「ガチっぽかったもんな、アレ」
「二度寝出来なかった」
「ごめんな、疲れてるのに」
「ちっげーよ」
ベッドの上で出すのとはまた違う、胸焼けする程甘い声で窒息しそうな程甘やかそうとしてくる傑に、悦はもう一度舌打ちをしてボタンが一つ飛んだ胸ぐらを掴んだ。相変わらず包容力と甲斐性全開で抵抗しない化け物を片腕で引き摺り寄せ、ベッドに寝転んだ自分の上に覆い被らせる。
視線が揺れないように傑を睨んだまま、短く息を吸って覚悟を決めて、言った。
「……抜け」
低い声を聞いて、逆らわずに悦の体の脇に手を突いた傑がぱちりと藍色を瞬かせる。
主語も無い尊大な命令だったが、この流れで”どこ”の話か解らない純血種じゃない。
「いいのか?」
「いい」
「それ以外がいくらでもあるのに?」
「……ぅ、……」
「な?他のでいいだろ、デザートなんだし」
ド正論をつかれて解りやすく言葉に詰まった悦を見下ろす藍色が、ぐらりと底を煮え立たせかけた熱をあっさり引っ込めて甘ったるく溶ける。砂糖菓子の蜂蜜漬けよりも甘やかして説き伏せる時の目だ。待てよ諦め早すぎんだろ変態の癖に。
「お前、……傑だって」
ここを逃せば次に腹を括るのにいつまで掛かるか解ったもんじゃないので、化け物がその自制心やら激重の愛情やらで抑えつけた熱を戻す為、手首を捻って胸ぐらを絞りながら慌てて口を動かす。傑の言う事は至極その通り過ぎるし、こいつなら本当にいくらでも「それ以外」を出せるという確信もあったが、それじゃ駄目だ。
10年以上も前に”商品”の危機を感じて命懸けで引いた境界線は、色々あって既に本能のレベルにまで食い込んでいる。頭で覚悟を決めるだけで済むならこんなにダラダラ引っ張って無い。生き残る為なら理性も感情も置き去りにする体の方がバグっている今じゃなければ駄目なのだ。
傑なら、そして今なら、魔王が別次元と称した快感で上手く境界を塗り潰してくれる。
「いい加減、ぶち込みたいだろ。……根本まで」
「……」
慣れた手つきで卑猥に下肢を這った指先に、傑は応えず、覚悟の程度を探るように軽く首を傾げた。
自棄になったわけ、でもあるがそれだけでは無いので真っ直ぐに藍色を見返すと、きっとそんな悦の心境の何もかもを察した美貌がふっと微笑む。
「……疼いてるのってどこ?」
屈めていた上体を起こしてマットレスに膝で乗り上げながら、傑は襟から離させた悦の手を腹の上に導いた。どこまで抉られたいのか教えろと、言外にそう命じて見下ろす藍色の底がぞわりと煮立つ。
「……ここ」
「ふーん、そこね」
より一層じんじんと切なく疼き出した所をパジャマの上から撫でると、口調だけはのんびりと相槌を打った傑がベルトのバックルを外す。急ぐわけでもなくボタンを外し、チャックを引き下ろして、引くタイミングを逃して太腿辺りに彷徨ったままだった悦の手を下着越しに押し当てた。
「コレだと、そこじゃなくて」
「っ、」
「ここまで、入れンだけど」
「んんっ」
指2本分、悦の手を上にずらして重ねられた傑の掌が、ぐり、とそこを押し込む。
「……それでもいい?」
勿体ぶったお伺いという建前の最後通牒に、悦は指に触れる下着を引きずり下ろす事で応えた。
悦としては、ローションぶち込んでガンとぶっ込んでそのままの勢いでバツンとぶち抜かれる、くらいの覚悟をキメていたのだが、勿論あの傑がそんな余裕もテクも語彙力も無い性急な行為を良しとするワケが無かった。
それについては考えてみれば当たり前だし、持ち込むまでにいいだけ煽り散らかしたし、昨日の名残でまだ柔らかい所にじれったくローションを馴染ませられても悦は我慢した。傑のモノと言わず太腿と言わず粘液塗れにする勢いでローションをぶっかけるだけに堪えた。傑は焦らすのが好きなサドだし、サドというものは早く早くと強請ると意地悪く勿体つける面倒な生き物だ。焦らしている分だけ自分も焦らされるんだからいっそマゾなんじゃないかと思う。
だから悦は我慢していたのだが、ようやく挿れたと思ったサドだかマゾだか解らない野郎がこともあろうに前立腺を当て堀りしてきやがった所で、ついにその我慢も限界を迎えた。
「あ゛ぁっ、クソッ……抜けって言ってんだろ!」
バックで挿れている傑を肩越しに思いっきり睨みつけて叫ぶ。これ以上余計な真似をしないように両手は指を絡めて握って顔の横に突かせているので、こんなにガチガチにしてやがる癖に呑気に苦笑する美貌はすぐそこだ。
「だらっだらヤってんじゃっ……んぅっ、やめろそれ!」
「俺のはそんなにチャチじゃねぇし、お前だってそんなにユルくねぇだろ」
「や、めろって言っ……あぅううっ!」
「そんなに構えられてちゃ入るモンも入らねぇんだって。いい子にイってろよ」
「あぁあっ!」
何がいい子にだせめて奥でイかせろふざけんな、と全身全霊で思ったが、これまた昨日の名残で腫れている前立腺をごりごりに押し潰されて眼の前に火花が散る。悔しさに歯噛みしながら思いっきり腰を上げてみたものの、傑はその分だけ腰を引く。悲しいかな、悦と野郎とでは足の長さが絶望的に違った。
「ふーっ、ふーっ……傑ぅう……ッ」
「落ち着けって。気持ちイイだろ?ここも」
「ぁあ゛ぁぁっ……!」
「あー、わかったわかった。じゃあ5回。5回イったらな」
2、3本へし折る勢いで絡めた指に逆関節に力を込めると、ようやっと悦が焦らしプレイを愉しめる精神状態ではない事を理解した傑が譲歩案を出す。5回だって悦は多すぎると思ったが、叫ぼうとした文句はあっさり振り解かれた右手で腰をシーツの上に押さえつけられ、ふぎゅ、という間抜けな声に変わった。悲しいかな、悦と野郎とでは膂力も絶望的に違っているのだ。
「これっ、これだめ、なやつぅっ!」
「んー」
押さえつけられたまま一番イイ角度で前立腺を捏ねられて、自由になる足をじたばたさせながら抗議する悦に、傑はあまりにも適当な相槌を打つ。宥めすかしたって大人しくならないから、もう強制的に大人しくさせようという魂胆だ。
この野郎、と心底思うがいくら腹を立てた所で傑の手を跳ね除けることは出来ないし、体内を透かし見ているような正確さで前立腺をカリに引っ掛けられて転がされる快感が無くなるわけでも無い。シーツに縫い留められたまま上から体重をかけてしこりを押し潰され、悔し紛れにシーツを叩いていた足がぴんと伸びる。
「ひあぁあッ!」
「いーち」
「あッ!?とめっ、やだ、やぁあああっ!」
「にーい」
「んぅう゛うぅっッ……ふっ、ふぅう゛うっ……!」
「さーん」
「いぁあ゛あぁあっ!やぁあ゛っあぁああっ!」
「よーん」
「あ゛ーっ、あぁあーーーっ!」
「よし、5回おわり」
「んぅ゛っ!」
どれだけ痙攣しても1ミリだってシーツから浮かなかった腰を急に引き上げられて、浅い所ばかりを甚振っていたモノが奥深くに入り込み、ぎくりと悦は全身を強張らせた。
連続絶頂によってぐちゃぐちゃに溶かされていた筈の頭が、キンと音を立てて冴える。
カウントダウンは5回で、それは終わった。やっとだ。願い通りの筈だ。体の強張りは取れないがもうこの際多少痛くっても構わない。うじうじぐだぐだと日和りやがる体が勝手に逃げを打たないように、シーツを握る右手に力を込める。そう言えば遠い昔の”前回”の時は初撃で吐いた気がするので、二の轍を踏まないように知らず詰めていた息を鋭く吸った。
吸った分を細く吐き出して、そこを開くことを意識する。幾度となく死線を越えて来た集中力の全てを体内に注ぎ込んでいる悦を驚かせないようにしてか、傑は普段なら焦れて泣き出すような緩慢さでラスト1センチを進めて、キスをするよりも柔らかく曲がり角へ先端を押し当てて、そして。
そして、2呼吸待ってもそのままだった。
「……いい加減にしろよてめぇ……!」
「しー」
もう、殴る。そう心に決めて右拳を固めながら捻ろうとした上半身は、この期に及んでは煽りにしか聞こえない声と共に背中にぴったり胸板をくっつけるような形でシーツの上に抑え込まれたが、別に殴るのに支障は無い。瞬時に拳から裏拳に変えて躊躇なくこめかみに向かって振り抜いた悦の右手を、傑は肩口に顔を埋めるようにして難なく避ける。
それならと、殴れないなら耳の一つか皮膚の10センチでも食い千切ってやるつもりで鋭く振り返った先で、深い藍色と目があった。
「悦」
悦の怒りよりも遥かに高温に煮え滾った瞳のままで、甘ったるい低音が名前を呼ぶ。
声自体には何を咎める響きも無かったが、これ以上八つ当たりに付き合うつもりはないと、うつくしく、おそろしく、細められた藍色がそう告げていた。
「……ごめ、ん」
「怒ってねぇよ」
途端にしゅんと怒りが萎えて、振り上げたままだった右手を下ろしながら謝る悦に、傑はいつもの調子でキスをする。
思えば、羞恥だの意地だのが邪魔をして形ばかり反抗する悦を適当な所で黙らせて事を先に進めるのも、いつもの通りだ。
そう、傑は最初からいつも通りだった。抜くの抜かないのと大騒ぎしているのは悦だけだ。
あまりにも情けなさ過ぎて認めたくは無いが、覚悟を決めたつもりでいて、結局は怖かっただけなのだろう。認めてしまえばこんなに単純な話も無い。自分の事ながら頭が悪すぎて嫌になる。
「もうちょい足開けるか?」
「ん……」
目元から頬、耳、首筋、うなじ、と順番に落とされるキスに従って起こしていた頭をシーツにつけながら、太腿を撫でる手に促されるまま足を開く。昨日まで”根本”としていた箇所からもう一段進む場合、もっと突き出すくらいに開いた方がいい気がしたが、馬鹿が馬鹿なりに考え込んだ所で馬鹿なことになるだけだと学んだばかりだ。
「ぅんっ……ん、ぁあ……っ」
余計なことはせずにその辺の調整は傑に任せて、揺するように緩慢な動きで慣らし直されるナカの感覚に意識を向ける。神経を尖らせて集中することはもうしなかった。わざわざそんな真似をしなくたって、とっくに傑好みに開発されきった悦は気持ちいいことが大好きだ。
ただ強弱をつけて押し上げられるだけだった所を軽く突かれてじんと尾骨が痺れ、それを呼び水にして八つ当たりの怒りが脇に追いやっていたそこの疼きを思い出す。一緒に昨夜の目が眩むような快感と、ただイけないだけじゃなかったもどかしさも。
「調子出て来たな」
「はぅううぅ……っ!」
「そのまま、息止めるなよ。ちゃんと緩んできてる」
トロ火で炙られているような所を壁1枚隔てて抉りながら、傑はいつもの調子でがくがくと震え始めた太腿から腰へと右手の置き場を変えた。腰骨を捉えてそこを掴み、逃げ道を塞がれたとやっぱり体を強張らせてしまう悦に構わずに、矛先を慣れた角度からほんの少しだけ変える。
「うあっ、あ、ぁあっ」
「んー……もうちょい……」
「はーっ……はぁあっ……ぁ、あぁ……っ!」
「あぁ、そうそう。その感じ」
慣れない角度で緩く突かれる度に詰まりそうになる息を吐く、ということ以外は何一つ意識的には出来ていない悦のどこかしらをおざなりに褒めて、傑はZ地区育ちも気づかない自然さで繋いだままの左手をひっくり返した。
ぐっとそこに体重をかけられてようやく、指先に触れていたシーツが無くなった事に気付いた悦の意識が一瞬そちらに逸れ―――実際の所は悦がいくら緩めようが締めようが関係なく、ただその一瞬だけを狙い澄ましていた傑は、掴んだ腰を引き寄せる。
「あ゛ッ」
全身を総毛立たせたその感覚が何なのか、健気に傑を信じていた悦には一瞬分からなかった。痛みも苦しさも吐き気も、覚悟していた何もかもがあまりにも何も無さ過ぎた所為だ。
一拍遅れて抜かれたのかと気づいて、じゃあこれはダメな所へ入りこまれた怖気かとまず思って、いやでも、と思い直した思考がスコンと抜ける。数秒か、それ未満かの空白の後に背骨を起点に全身の神経へ走った電流は、慣れ親しんだそれとは桁が違った。
重い。
「……あ、ぁ゛っ?……あ……ッはぁあ゛あぁあ……っっ!」
重さに耐え兼ねた体が無意識の内に上半身を引き上げるようにして背中を丸め、くぷん、と奥の奥から抜ける感触に悦は全身を鳥肌立てて額をシーツに擦り付けた。入っていたのは先端のほんの一部だけだというのに、そのほんの少しが曲がり角から出ていくだけで重い絶頂が視界を明滅させ、全身が細かく震える。
「なんで逃げンだよ。こうして欲しかったんだろ?」
「はッ……はぁ゛っ……!」
言葉とは裏腹に逃げた分を引き戻すことも止めることもなく、腰から離した手で普段とは逆方向に撓った背を撫でる傑を、悦はまだ痙攣の収まらない体をどうにか捻って振り仰いだ。
元男娼が仰け反らずに背中を丸めた事の意味を、薬を打たれた頭でも反射でそう動くよう癖付けた経緯を、きっと当の本人よりもよく理解している化け物は繋いだままの左腕一本分の距離でそこに居て、どう考えても覚悟をキメる方向性を間違えていた悦を愛おしそうに嗤う。
「……壁越しであれだけイきまくるトコを、直だぜ?」
そりゃそうなるだろ。いっそ呆れたように考えてみれば当たり前のことを言われて、悦はまだ感覚の戻りきらない左手できゅっと傑の手を握った。
10年以上振りの2回目でこんなに凄まじく気持ちいいなんて絶対におかしいと思っていたが、何のことはない。悦だけが気づいていない内に必要な準備も下拵えも、全て済んでしまっていただけの事だ。境界線が食い込んでいたのは本能だけではなく頭の方もそうで、体はラインのぎりぎり外からもう幾度となくそこを嬲られる快感を教え込まれていた。昨日の開発用器具は無意識にとって都合の良かったきっかけに過ぎない。
「……気長すぎ、だろ」
「そういう趣味なんだよ」
年単位の開発を今更思い知って愕然と呟く悦に、嫌がっていた行為をあらゆる手管を使って泣きながら懇願する程大好きにさせるのが趣味の傑は軽く首を竦めて見せた。
冗談めかした仕草が逆に空恐ろしく思えてぞっと身を縮めた悦の背の上で、長い指先がたとと、と愉しげに踊る。
「そんな顔すんなって、お陰で気持ち良かっただろ?痛い方がイイなら次はそっちでいくか?」
「つ、ぎ」
「そう、次」
浮いた骨の形を辿っていた手にぐっと力を込められて、丸めていた背を強制的に伸ばされた悦はシーツに縫い付けられた。上半身を抑えられて先にも後にも行けなくなった腰だけを高く上げたまま、ぐち、と押し当てられる感触に小さく悲鳴を上げる。
「さっきがここ」
悦が震えるばかりで本気で嫌がらないのを確認してから背を離れた指が、骨盤と背骨の継ぎ目辺りをとんと叩いた。
「次はここまで挿れる」
次にさっきより指2本分先を。
「……痛くして欲しい?」
「っ……!」
「だよな」
ぶんぶん首を横に振った悦に小さく笑って、数分前までとは別の意味合いで強張る体を宥めるように撫でながら、いっそ無造作とも思える動きで傑は腰を動かした。
ただ挿れるのではなく、動かした。
「あ゛――――っっ!」
逃げられないように悦の腰を押さえたまま、さっきと同じ深さまで曲がり角を越えて、無理にそれ以上突っ込むような事はせずに、抜けきらない場所まで引く。ただそれだけで悦は栓でも抜かれたように精液とも潮ともつかないものを吹き出したが、目標はあくまでもカリまでを挿れることなので、傑は腰を止めてくれなかった。
ついさっき口を開けることを覚えたばかりの場所を、もっと太いものを挿れられても痛まないように柔軟に、従順にさせる為に、曲がり角のそのすぐ先のとびきり敏感な粘膜を優しく叩く。受け入れるのに慣れた体が上手くこの致命的な快感を受け止められるように、簡単には意識を失わないように、どんな形に広げられているのか教え込むような緩慢さで。
「しょ、こッ……とんとん、しないれ゛っ……!」
「んー?」
「あたま、おかしくなる゛、ぅっ……い、ぐッ……おも、ぃい゛いっっ」
「うんうん、重いな。もうちょいで全部入るから頑張ろうな」
「あぐぅううう……っ!!」
とんとんなんて可愛いものではなく、体液を巻き込んでにぢゅにぢゅと突かれている所にほんの少し体重をかけられて、悦はまたぷしゃりと腰下のシーツを濡らした。相変わらずなにを吹いたのかは解らない。そんなことをかんがえるよゆうがない。
距離にすればほんの1、2センチの、ピストンとも呼べないような緩い抽挿を繰り返されているだけなのに、今や悦の頭の中は爆竹でも投げ込まれたような有様だ。間断なくイき続けて痙攣する内壁はきっと前立腺だって揉みくちゃにされているに違い無いのに、結腸を優しく嬲られる快感が信じられないほど深すぎてそちらには全く意識が届かない。
無理だ。こんなの頑張れない。そんな次元の話じゃない。
「いれ゛てっ、い……れてぇ゛ッ」
「まだ早ぇって。痛いのヤなんだろ」
「いいっ、いいから゛ぁっ!」
「しょうがねぇなァ」
ガチガチと奥歯を鳴らしながらの懇願に呆れるどころか、悦に見えていないのを良いことに待ってましたとばかりに笑って、傑は曲がり角を甚振り続けていた切っ先を一度完全に抜いた。ひゅう、と笛の音のような音を立てて悦が深く息をするのを待って、今度は一切の加減無しに突き入れる。
「―――!」
体の奥の奥から響いたぐぽん、という音に、なけなしの理性か本能によってまた頭がキンと冴えた。
死んでも是としなかった行為を示す音にシーツに涙を吸わせていた顔をがばりと上げて、逃げようとしてか殺そうとしてか、理性が追いついていない反射の動作でベッドヘッドの方を、そことマットレスの隙間に隠したナイフを見た瑠璃色が一度の瞬きで完全に乾く。生存に必要の無い要素を瞬時に切り捨てた五感は極限まで研ぎ澄まされ、武器への距離を目測しながら肘を伝った汗がシーツに落ちる音を聞き、全ての動きを制限している腰に置かれた掌を知覚した。
何の殺傷能力も無いシーツを握っていた右手を開いた辺りでやっと理性が追いつき、まず深く吸えない息苦しさを思い出す。重い熱と質量が境界線の内にまでみっちりと詰め込まれているからだ。汗だくの肌に張り付く布では無い感触。自分よりも低い体温。
「―――……あ、ぁ」
そう誂えたのかと錯覚するほどぴったりと密着した肌の奥に骨盤の硬さを感じた瞬間、一度の瞬きで元通りに瞳を潤ませた悦はぱたりとシーツに沈んだ。
はいってる。思わず漏れた譫言のような自分の声を聞いてようやく、ついに本当の意味でそこを”抜かれた”のだと自覚する。感覚的には鳩尾の上までいっぱいにされているような圧迫感以外にも、隙間無く合わさった滑らかな肌が何よりの証拠だった。
「悦」
詠うような声で呼んだ傑が、殺気と共に図らずも余計な力も抜けた左手を引く。逆らわずに上体を捻って振り返った悦の手を更に引いて、据わった目を笑みの形に細めた化け物は、大騒ぎしながらもようやくその全てを収めた腹に触れさせた。
「ここまで入ってる」
「……ぜ、んぶ……?」
「あぁ。これで全部」
撫でた指に反応した内側がきゅうと確かめるようにそれを締め付け、隙間無く満たされた充足感と視界の端がぱちぱち弾ける心地良さに、とろりと悦は目を細める。ぜんぶ。
―――ああ、それなら。
「おれも、これで……ぜんぶ」
どこかを抉るか切るかして新しい穴を作らない限り、悦の方もこれで、本当に全部だ。
初めてで無いのが少し申し訳ないけれど、それはお互い様だろう、とふにゃりと眼尻を下げた悦の手を、長い指を深く絡め直した傑が握り返す。
「……そーいうこと言うなよ」
「でも、ほしかったのは傑がはじめてで」
「………………あのな、悦」
望んでこうするのは初めてだから、と色々が振り切れた所為でふわふわした頭でなんとか説明しようとする悦の髪をさらりと優しく梳いてから、傑は伸ばした右手でシーツに転がっていたローションボトルを拾い上げた。
気の立っていた悦がぶちまけたお陰でもう殆ど中身の残っていない、半円のキャップのそれを悦にも見やすい位置に持ってきて、―――力を込める様子もなく、ノーモーションで握り潰す。
ぱん、と口ではなく底の方から破裂する音に少し理性が戻り、悦は丸くした目で傑を見上げた。
「俺、今ナカでこうなんだよ」
開かれた手の中、純血種の握力で締め付けられて中程から潰れたプラ容器から、もう一度傑に視線を向ける。
「ちなみにカリ上はこう」
「ひぇ……っ」
シュミレーションに適した形状のキャップ上が3本指で捻られ、粘土みたいに絞られて捩れたそれが意味する所とよく見れば完璧に据わっている藍色の両方に、悦はびくっと首を竦めた。
こわい。そこはほぼ処女の癖に相手が相手なら殺人になり得る名器っぷりを知らず発揮している自身のポテンシャルと、そんな風にぎちぎちのめりめりに締め上げられておきながら理性を保って平静に喋っている傑の精神力の両方が。
「な?……だから、頼むから煽ンな。結構ギリなんだよ」
「ゆっくり……ゆっくりに、して……」
「止めろっての。……抜く以外には動かねぇよ、今日は」
ダメ元でお伺いを立ててみた悦に、というよりは自分に言い聞かせるような低い声で呟いて、傑は一度ベッドの外へ視線を反らした。サイドボードと壁の境目辺りを殆ど睨んでいるような鋭さで見ながら深く息を吐き、残っていたローションで濡れた右手で無造作に前髪を掻き上げる。
顕になった額に薄く汗が滲んでいるのを見てもう半歩理性が戻り、悦は圧迫感の所為で浅くなっていた呼吸を深くした。これは、珍しく本気でヤバそうだ。
「……っは、ぁ」
こんなに奥まで犯されるのはほぼ初めてだが、いつもよりちょっと深いだけで場所が変わったわけでも、入っているモノが変わったわけでも無い。それなら理屈は変わらない筈だと、どこに力を入れて抜くべきなのか自身の内側を探る。元Z地区の”鴉”で稼ぎ頭の男娼という経歴はつまるところ、悦が適応能力の鬼であることを物語っていた。
自覚した途端にずんと芯に響く快感を堪えて、加減も技巧も無くただ締め上げていた所をどうにか緩める。そっちに意識を向けると直ぐにでもイきっぱなしになるのはさっきで学習していたから、一旦自分の事は脇に置いて、極限の集中力をもってなんとか置いて、傑を気持ちよくさせる事に集中した。
「ん゛、んッ……ふ……ぁあ……っ」
かつてはどんな真似をされても降りない緩まない鉄壁さで鳴らしたものだが、それは偏に悦の側に受け入れる気が微塵も無かったからだ。どこをどうすれば一番具合がイイのか、知識ならある。
2回目のトライで狙い通りに愛しい熱を具合よく絞り上げる事に成功し、それに連動して膨れ上がった快感に意識を持っていかれそうになりながらも、悦はぴくりと眉を揺らして戻ってきた藍色から視線を反らさずにいた。
「……きもち、ぃ?」
こんな事を真っ最中に聞くのは初心なド素人みたいで恥ずかしいけど、初めにおかしな癖をつけると抜くのが大変だし、折角ヤるなら自分だけじゃなく傑の頭にも爆竹を投げ込んでやりたいので、悦は素直に愚直に自分の巧拙を尋ねる。相手の欲を計るのに一番解りやすい部位を喰い締めながらこんなことを聞くのなんて、十年振りどころではなく初めてかもしれない。
でも、傑には聞いてみたかった。
「最高」
いつもより低い声で即答した傑が起こしていた上半身を倒し、右腕で悦を抱き込むようにしながら肩口へ顔を埋める。
「マジで最高。……悪い、語彙力ぶっ飛んでるわ」
「めずら、し」
「言っただろ、ギリギリなんだよ」
「はぅうっ……!」
それならそういう反応しろよ解り辛ぇんだよ、と笑おうとして、自身の掌ごと傑の左手に腹を揉み込まれた悦は喉を晒した。色々と総動員して意識を反らしていたが、悦の方も傑に負けず劣らずもう限界だった。
「あ゛っ……くるっ、くる、ぅ゛……!」
ずしんと体の芯に落ちたそれに今度は逆らわず、意識をすり潰されるような重く深い絶頂とそれを与えてくれる傑に身を任せる。
「ぅあ゛、ぁっ……~~~~~っ!」
繋がれたままの掌の下で、みっちりと奥の奥まで広げられた粘膜が自分でもそうと解るくらいにぐねりと蠢き、悦は全身を痙攣させながら声にならない嬌声を上げた。爆竹なんて目じゃない火薬量の花火がバン、と暗くなりかけた意識を警告色に染め上げる。
右手でシーツを手繰り、両足を爪先立ちに突っ張る悦を他所に、頭と違って物覚えのいい体の方はすっかりそこでの”やり方”を覚えてしまっていた。外側と同じように痙攣する内壁で自分から傑の裏筋に前立腺を擦り付けてだらだらと白濁を零しつつ、奥の奥にある肉輪がぐっぽり嵌まり込んだカリにしゃぶりついて、少し突かれるだけでイきまくった弱点をも自らの蠕動でもみくちゃに刺激される。
「ひッ……ひぃ゛ッ……!!」
「……ん、ん」
「あぁあ゛あぁあッ!?だめっ、それだめぇッ!」
「無茶言うなよ」
「あ゛ぁあ―――っ!」
ダメだと言ったのに、肩口に顔を埋めたままの傑が耳のすぐ近くで苦笑混じりに囁くものだから、悦はボックスシーツを端の方からぶちぶちと引き千切りながらもう一段深くイった。重く体の芯と精神に伸し掛かる絶頂にもう継ぎ目は殆ど無く、爆竹と花火が交互に弾けている視界は半分以上が暗い。
意識を落とさずにいられたのは、それがせめてもの操の示し方だと思ったからだ。
傑ならそれを汲み取ってくれると信じていた。
「悦……っ」
「ひあ゛っ!」
甘くない、押し殺したような低音で鼓膜を通り越して脳までも犯しながら、宣言通りに動かなかった傑がどくりと一番奥で熱を吐き出す。
「あ゛――……あつ、ぃ………っ」
内側から焦がされるような熱についに隅々まで満たされるのを感じながら、悦は爪を立てて引き止め続けていた意識を手放した。
Fin.
4Pの悦ver.その後日譚。
大騒ぎしながらついに男娼が全て傑のものになりました。
