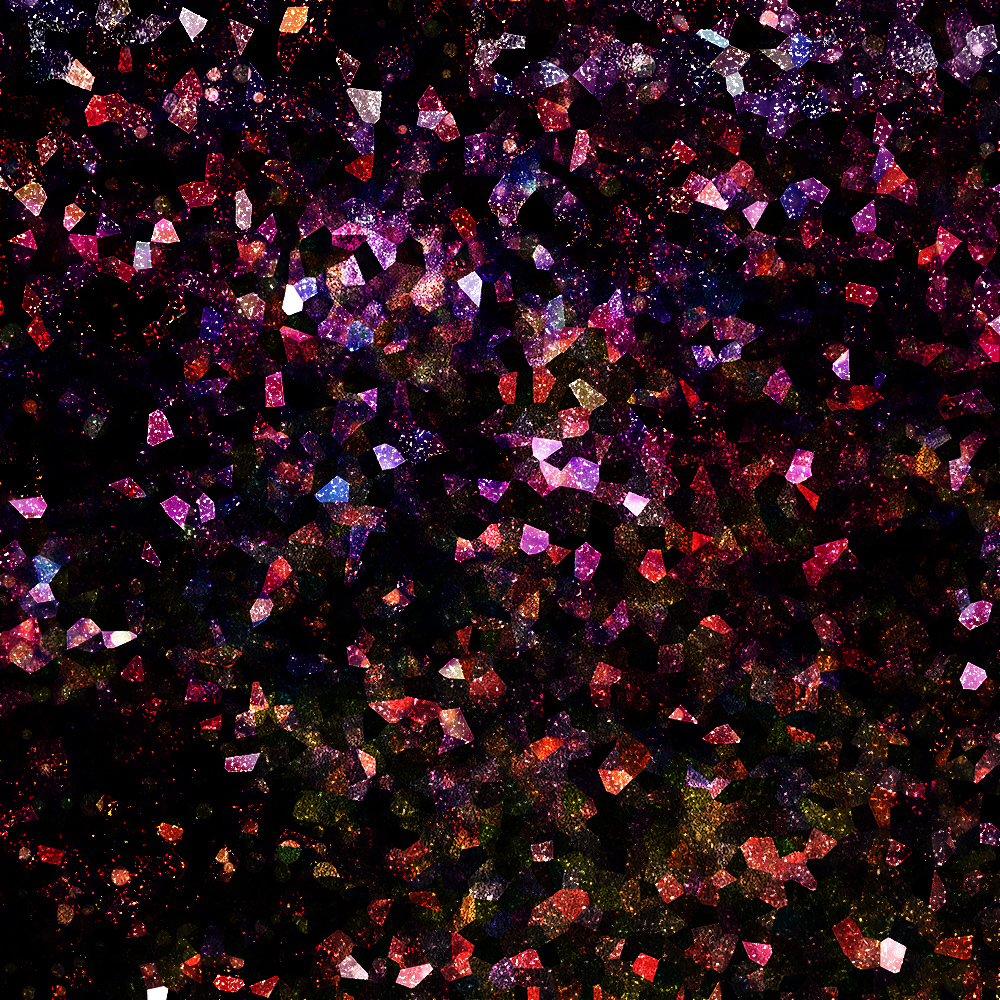
砂の城
息が、止まるかと思った。
「…きり?」
まだ少し拙さの残る声に名を呼ばれ、色を失っていた鬼利の世界はかちり、とピントを合わせたように明度を取り戻した。強ばった表情を自覚して深く息を吸い、柔らかく口角を上げて見せる。
「まだ1人で眠るのが怖いの?」
「そ、そんなことない!」
ああ、よかった。
頬を染めて慌てたように叫ぶ弟にくすくすと笑いながら、鬼利は自分の作り笑いが成功したことに心底安堵した。
ちゃんと1人で眠れる、もう大丈夫だから、なんて照れのせいで大きくなった声で言い募る弟に、解った解った、と頷く。ほんの数年前まで言葉を知らず、名前もなく、家畜にも劣る環境で幽閉されていた双子の弟が、身振り手振りで懸命に鬼利の言葉を否定しようとするのに柔らかく目を細めながら。
ただ普通に弟を思う、兄の顔で。
鬼利は聡明な子供だった。
言葉を話すのも文字を覚えるのも早く、初等部に入る年の頃には大学府で学ぶ理数学の内容を理解していた。砂に水が染みるようなその理解力と、柔軟な発想、時に経験豊富な大人をも凌駕する論理的な思考力は、天才秀才と呼ばれる御曹司達を多く教育した優秀な家庭教師さえも驚かせた。
鬼利は賢明な子供だった。
自分の優秀さを知っても決して奢ること無く、自分より遥かに無知で愚鈍な大人達を侮ることもしなかった。名家の掟と当主たる父の思惑を理解していたから、結果を知っていても毒の混入された夕食を抵抗せずに食べ、彼が“部品”と呼ぶ双子の弟が幽閉された屋根裏へは、屋敷の設計図を読み込んで調べた抜け道から通った。病床にある母の憎悪と狂気を理解していたから、父の面影が残る自分の顔を見せぬよう会うのを避け、双子の弟の悲惨な現状を告げ、狂った彼女の呪詛が幼い心を蝕むのを応報と受け入れた。
鬼利は利巧な子供だった。
あのままでは凄惨を極めた環境から双子の弟を救うのが不可能ということも、自分が父やその側近を排して家の実権を握ってからでは遅すぎることも解っていた。国と家の利益を最大化する機械として育まれた筈の心を、何でも理解できてしまう自分の脳漿と母の呪詛が歪めたことも、まだこの年齢なら修正可能なことも解っていた。父を親族を殺し、同年代のよく似た双子を身代わりに殺し、厳しくも面倒を見てくれた使用人を殺し、罪を着せた母を殺しその親族を貶め、考え得ることは全て考え使えるものは全て使い自分の年齢さえ利用して、作り上げたこの安寧が酷く歪であることも全て解っていた。
それを可能にしたこの感情が、愛と呼ぶにはあまりに深く重く穢れていることも。
「幽利、おいで」
驚かせないように努めて柔らかい声を出したつもりだったが、ソファの隅に座ってこくりこくりと船を漕いでいた幽利は、それを聞いて弾かれたように顔を上げた。
「あっ、きり、ごめんなさ、あの、ごめっんなさい、きり」
「いいんだよ。大丈夫。髪を乾かさないとね」
澄んだ橙色の瞳を見開いて顔を強ばらせる幽利の頭をそっと撫で、鬼利は軽く腰を屈めて幽利と視線を合わせながらにっこりと笑う。まだ不安そうに、何かとんでもない間違いを冒してしまったように狼狽える幽利の肩を撫でながら、細い体から強張りが取れるまで柔らかい声で大丈夫。いいんだよ。と何度も繰り返す。
ベッド以外の所でうたた寝をしただけで、髪を乾かさずにいただけで、それを鬼利に指摘させたというただそれだけで、幽利はまるでこの世の終わりのような顔をする。
今許されている全てのことが身に余る幸福なのに、身の程知らずにもそれに甘えてしまったと、普通の人間の、子供の扱いをされただけで、首に刃物を当てられたように怯える。
「ほら、おいで。早く乾かして寝ようね」
「うん。うん」
やっと強張りが解け、ぎこちなくも笑顔を作って頷く幽利の手を引いて洗面台に向かいながら、鬼利はそっと表情を消して家を出たあの夜を思い出していた。毒に冒されてのたうち回る父や親族や使用人の死に様は、今でも焼き付けたように鮮明に脳裏に蘇る。
…ああ、もっと苦しめて殺せばよかった。
「熱くない?」
「うん、へいき。大丈夫」
こくこくと頷く幽利にドライヤーを当ててやりながら、鬼利は脳裏の凄惨な想像を打ち消してそう、と微笑んだ。幽利の頭で半分以上隠れているが、洗面台の鏡がある今、どんなタイミングで自分の顔が鏡越しに幽利に見られるか分からないからだ。
表情は完璧でも、内心が少しでも瞳に出てしまったら、幽利がそれに気づいてしまうかもしれない。鞭で打たれ、痛覚を失ってからは水桶に沈められながら叩き込まれた自分の作り笑顔の精度を、鬼利は決して過信しない。
「綺麗だね。ちゃんと洗えてるよ」
「ほんと?後ろも?」
「うん。上手になったね、幽利。いい子だね」
「いいこ…?」
「そうだよ。ちゃんと自分で綺麗に髪を洗えるようになったんだから、幽利はとてもいい子だよ」
首を傾けて鏡越しに目を合わせながら褒めると、見つめる幽利の目尻が嬉しそうにふにゃりと下がる。それにつられて自然と微笑みながら、鬼利はドライヤーを持ち替えた。
成果を褒められて喜ぶ幽利の、純粋で清らかな感性が心底愛おしい。賛辞を受け入れられず、不安そうな目でぎこちなく笑っていた頃を思えば尚更だった。十分な栄養のお陰でさらさらと指通りのいい髪も、首筋を撫でる少し伸びた毛先にくすぐったそうにする仕草も、自分と同じ型のパジャマがまだ大きい細い体も、全部。
全部。
「はい、おしまい」
「ありがとう、鬼利」
「どういたしまして」
きちんと頭を下げた幽利に頷きながら、鬼利は一歩後ろに下がった。いつもなら幽利に歯ブラシを差し出してやる所だが、今日は敢えてそうせず、自分の髪を乾かすためにドライヤーを持ち直す。
風呂に入り、髪を乾かして歯を磨くのが幽利の中で習慣になるよう、鬼利は務めてきた。いずれ鬼利の手助けが無くても普通の生活が出来るように。ひとりでも生きていけるように。
邪魔にならないようにと脇に避けた幽利は、鬼利が手櫛で髪を梳くのをどこか所在なさ気にちらちらと伺っている。その手が何か言いたげにシャツの裾を握るのを横目にして、鬼利は心の中だけで小さく笑った。
「…き、鬼利っ」
ああ、まだ自主的に動くには早かったかと、歯ブラシに伸ばしかけた手を、幽利の小さな声が止める。
「どうしたの?」
「え、っと…あの…鬼利の…」
「僕の?」
「う、…鬼利の…あ…」
俯いたままもごもごと言葉をつっかえさせる幽利を、鬼利はドライヤーを下げて待った。幽利がちゃんと自分で考えて組み立てた言葉を言えるまで、辛抱強く。
聡明で賢明で利巧な鬼利には、幽利が何を言いたいのかなんて容易く予想がついていたけれど、すぅ、と息を吸い込んでから発せられた言葉に、幽利にも解るよう少し驚いて見せた。
「鬼利の、かみ…かわかして、みても、いい?」
「…幽利がしてくれるの?」
「うん、…うん」
機嫌を損ねないよう人形のように固まるのではなく、言いなりになるのでもなく、自主的に考えて行動することがとてもとても良いことだと、幽利に伝わるように。予想を裏切り期待以上のことをした時の他者の少しの驚きと感心が、幽利自身にも喜びを生むと学ばせ、自主性を育む為に。
「じゃあ、お願いしようかな」
「うんっ」
「疲れたら言うんだよ。途中でもいいからね」
「うん、大丈夫」
差し出したドライヤーを受け取り、いそいそと自分の背後に回りこむ幽利を鏡越しに眺めながら、鬼利は柔らかく目を細めた。
教えたことは無いが、幽利はドライヤーのスイッチを入れ、適切な距離を保って鬼利の髪にドライヤーを当てている。鬼利がいつもしているように髪を梳きながら、熱くないかと聞く。
鬼利がやっているのを見て覚えたのだろう。なにせ幽利の記憶力は鬼利をも凌ぐのだ。今までは記憶できていても様々な経験や情報が足りず、自分の言動にそれを反映させるのは難しいようだったが、もうその心配も無いようだ。鬼利の双子の弟なのだから地頭は悪くない。これからこうして色々なことを覚え、そのうち鬼利がいなくても身の回りのことが出来るようになるだろう。
それはとてもいいことだ。まだトラウマは多く残っているし、その所為で幽利の自己評価は異常に低いが、これからゆっくりと折り合いをつけていけばいい。上手く行けば中等部は厳しいが、高等部からは教育機関に通えるかもしれない。それまでの履修内容は鬼利が十分に教えられるし、金も人脈も十分にある。腕のいいカウンセラーを見つけて忌まわしい記憶を封印し、それが蘇らないよう兄としてサポートをする。環境を整えるのは鬼利の役目だ。そうすれば。
幽利はごく普通の子供として学校に通い、友達を作り、年頃になって恋のひとつでもして、普通の幸せな家庭を築くだろう。毒を食らうことも呪詛を聞くこともなく、普通の、ただ普通の幸せを得る。邪魔なものは全て幽利の分まで鬼利が背負えばいい。
それはとてもいいことだ。
「鬼利、かわいた?」
「うん、もういいよ」
「あつくなかった?」
「大丈夫。幽利は上手だね。これなら今度からは自分で乾かせるかな?」
「うん、できる!」
「すごいね、幽利は。これならきっと…」
ドライヤーを引き取って代わりに歯ブラシを手渡しながら、鬼利は嬉しそうに目を輝かせる幽利の頬をそっと撫でた。
「…すぐに、何でも自分で出来るようになるね」
それはとても、いいことだ。
柔らかくスプリングが沈むベッドに幽利を寝かせ、鬼利は埃を立てないようにそっと羽毛の入った上掛けをかける。
堅く冷たい床と薄く擦り切れたタオルケットしか知らない幽利は、少し前まではこのスプリングと布団を随分と怖がっていた。鬼利が添い寝すればなんとか寝付きはするが、無意識のうちにベッドを降りてしまっては、真っ青な顔で鬼利に許しを請うたものだ。
今はもう鬼利が添い寝する必要も無いし、夜中に堅いフローリングの上で体を丸めて眠ることもない。主寝室のダブルベットは鬼利がホテル側に頼み、少し前にセミシングルのツインに変えた。寝室を別にするのは、まだもう少し先でもいいだろう。
「おやすみ、幽利」
「おやすみなさい…」
眠たげに瞬く幽利の襟元を苦しくないよう整えてやって、鬼利は暖色の間接照明に輝く幽利の髪をそっと梳いた。
いつものようにキスをしようと軽く体を屈めた瞬間、脳裏に昼間の幽利の言葉が蘇る。
――― ねぇ、鬼利。あれ、
「…おやすみ」
甘く脳髄を満たす声を振り払い、鬼利はいつものように、幽利の頬にキスを落とした。
それを合図に目を閉じる幽利から視線を反らし、表情には出さないまま、胸の内だけで自らを嘲笑う。
…幽利にとって一番邪魔なのは、この僕だ。
幾度もくりかえした言葉を確認するように反芻し、鬼利は自分のベッドに横になった。ベッドヘッドに枕を当てて背中を預け、ローチェストに乗せていた本を引き寄せると、薄暗い間接照明の中で表紙を開く。
ホテルで出される食事には毒が入っていない。夜中に高熱を出すことも、胃液が無くなるまで嘔吐することも、激痛に息が出来なくなることも無いが、体に染み付いた習慣というやつなのだろうか。未だに鬼利は長時間ベッドの上で眠れたことが無かった。
背骨を貫かれるような激痛や嘔吐感を思い出すわけでもないのに、存在しない苦痛に備えて脳が覚醒する。だから鬼利は己の体が最低限求める睡眠時間を見極め、幽利が起きる時間から逆算して眠るようにしていた。
成長期の体には悪影響が出るかもしれないが、薬の類は鬼利の体には一切効かないし、例え効いたとしても鬼利はそれを飲まないだろう。考えることも得るべき知識も山のようにあるから時間を潰すのは容易いし、眠る時間が短ければその分幽利のことを見ていられるからだ。
幽利に何かがあった時素早く対応出来ることを思えば、例えそれが軟弱な自身の体にどんな悪影響を出したとしても、浅く短い眠りは鬼利にとって好都合だった。
喉の渇きを覚えて鬼利がベッドを出たのは、真夜中を少し過ぎた頃のことだった。
電気を点ける代わりに広い窓を覆うカーテンを少し開けたリビングで、鬼利はソファに姿勢よく座り、じっとテーブルの上にある瀟洒なカップを見つめる。
橙色の瞳は確かに暖かな湯気を上げる陶磁器を映しているが、鬼利の脳にはその芳醇な香りも、素足で踏むフローリングの冷たさも、何も何も届いてはいなかった。
「……」
年齢にそぐわない憂いを帯びた瞳の奥で、鬼利は考える。記憶しているものに今日読んだ5冊の専門書から得た知識を加えた上で、深く広く考える。
鬼才天才の名を欲しいままにする脳の全てを総動員して、自らの心を殺す方法を、考える。
鬼利が幽利に抱いているのは、兄弟愛などでは無い。
賢すぎる鬼利が己の感情を自覚し名前をつけるのに、時間は掛からなかった。
知識は並みの大人以上にあったし、家柄と立場上、手段を選ばない貴族の女達に両家同意の上で強姦紛いの行為を強いられていたせいか、驚きや戸惑いも少なかったと思う。
それの名前は執着だった。それは肉欲と劣情を伴い、酷く歪んで捻れて、深く重い。
初めて幽利の存在を知った時は、双子の弟という存在に純粋に焦がれた。初恋のように清らかだったそれは、鬼利の“部品”として父に引き出された幽利を見た瞬間に、庇護欲へ変わった。膨大な屋敷の設計図や見取り図を読み漁り、探し当てた隠し通路からやっと幽利のもとに辿り着いた時には、その庇護欲は少し歪んでいた。
言葉を知らず、名前も無く、残飯を食べる幽利のもとに通い詰め、菓子を与え、名前を与え、言葉を教えるうちに、それは執着へと悪化した。劣悪な環境に知識や脳に不釣合いな幼い心では、それが取り返しの付かない所まで捻れて歪むのにも、やはり時間は掛からなかった。
鬼利にとって大切なのは幽利だけだ。大切な人をこんな醜い感情で汚すなど考えられない。だからそれを幽利に悟られないように、知識や言葉と共にひとかけらでも移ってしまわないように、細心の注意を払わなければいけない、のに。
「…あぁ」
ぽすり、と幼い体をソファの背もたれに預けて、鬼利は嘆息する。
考えることは山のようにあるのに。鬼利が不慮の事故や病気で死んでも幽利が真っ当に生きていけるような準備や、そうならなかった場合の準備、幽利のサポートや環境が整えば、鬼利が死ぬタイミングも測らなければいけない。
自分を過信せず幽利を侮らない鬼利は、幽利が自分を必要としなくなったタイミングで自殺することを決定事項としていた。鬼利が生きている限り、幽利を汚してしまう可能性があるからだ。
様々なことを考慮して死に方は病死と決めたが、これは失踪やただの自殺と違い時間がかかる。この軟弱な体ではただ死ぬのに苦労は無いが、医者を幽利を欺き通してきちんと病で死ぬ為にはそれなりの準備が要るから、この計画は他より綿密に練らなければいけない。
そうだ、幽利の為に考えることは山のようにある。自分ごときの感情にかかずらわっている時間なんて、鬼利には無い。
「…キスなんて」
すっかり冷めた紅茶で満たされたカップを両手で持ちながら、鬼利は琥珀の水面に映った自分の目を見て嘲るような笑みを浮かべる。
脳裏に蘇るのは、昼間の幽利の言葉。
ニュースの合間に流れたCMの中で、舌を絡めるキスをする男女を見た幽利が言った、何気ない一言。
――― ねぇ、鬼利。あれ、
――― あれ、やってみたい。
あの柔らかな唇を塞いで震える舌を絡めとる想像など、何年も前から幾度となくしてきた筈だ。
なのに、あんな言葉に動揺するなんて。幽利には見えない脳の中でだけの行為だと理解している癖に、浅ましくも僅かに期待さえするなんて。
ああ。
「…しねばいいのに」
執着を滲ませる橙色の瞳に侮蔑を込めて吐き捨て、鬼利は一息にカップの中身を飲み干した。
ポットとカップを洗って片付けてしまってから軽く口を濯いで、鬼利は出た時と同じくそっと寝室に戻る。
寝返りを打ったのか、幽利は布団に顔を埋めるような格好で淡い明かりに背を向けていた。その姿に小さく苦笑して、鬼利は足音を忍ばせて幽利のベッドに歩み寄る。
息苦しいだろうと口元を覆う上掛けに手を伸ばし、鬼利が指を掛けた瞬間。それは鬼利の指を振り払う勢いで幽利の頭から剥ぎ取られた。
「…ゆ、うり?」
「鬼利…っ」
驚きに軽く目を見開いた鬼利を、内側から布団を引き下げた幽利が涙に滲んだ声で呼ぶ。きり、きり、と拙い声で、縋るように。
「大丈夫、僕はここにいるよ」
…馬鹿が。
優しく幽利に呼びかけ、そっと布団の上から抱きしめてやりながら、鬼利は優しい微笑みを貼り付けた顔の下で吐き捨てる。
幽利はいつから起きていたのだろう。鬼利が戻るのをどれだけ待ったのだろう。どれだけ心細かったか。不安だったか。喉の渇きを癒やす為にベッドを離れたのも、痛みを感じない体の為に紅茶が冷めるのを待ったのも、どれもこれも軽率な行動だった。
「ね、幽利。ここにいるからね」
「…っ…」
背中をとんとん、と優しく叩きながら安心させる為に囁いた言葉に、だが幽利はいつものように頷かなかった。細い指がシーツを握りしめるのを見て、鬼利は僅かに眉を顰める。
「…きり…ここにいる…?」
「いるよ。どうして?」
唐突な幽利の言葉に様々な憶測や感情が一瞬にして鬼利の脳裏を埋めたが、鬼利はそれらを全て一掃して即答した。その言葉通りに、当然じゃないか、何故そんなことを聞くんだ、という顔を作って。
「…きり、じゃま…だって」
「邪魔?」
腕の中でそろりと布団から覗いた幽利の目が、涙の膜を張ってゆらゆらと揺れる。
暖色の明かりのせいかいつもよりも濃く、熾火のような色をしたそれを見つめて、鬼利は自分の記憶を探る。昨日まで遡って思い返してみるが、独り言でも「邪魔」という言葉は使っていなかった。
だから、鬼利は判断した。柔らかく笑って幽利の頭を撫でながら、双子の弟が夢と現実を混同しているのだと、他の可能性を考えもせずに。
「そうか、怖い夢を見たんだね」
「…ゆめ」
「だって、邪魔だ、なんて僕は幽利に言ってないよ。思ったこともない」
「……」
胸元に抱き寄せた幽利をあやすようにゆっくりと体を前後に揺すりながら、鬼利はいつものように、幽利が落ち着くのを待った。冷えた自分の指先が幽利の体温を奪ってしまわないよう気をつけながら。
幽利を抱く鬼利の腕が痺れ始めた頃、拙い声が呟いた。
「…でも……だって、」
「うん?」
腕の中の幽利の瞳は涙の膜が張り、相変わらず不安に揺れていたが、その言葉は強い確信を持って紡がれた。
「…ねるまえ、だったのに」
「え?」
「まだ、ねむってなかった。キスしてくれた、ときだったから」
瞬時に記憶を引き出した鬼利の頭から、ざっと音を立てて血の気が引いた。
確かに心の中だけで思ったのに。まさか無意識のうちに声に。そんな筈は。まさか。まさかまさか。
「…それは、今日?」
「……」
強靭な精神力を総動員して平静な声で問うた鬼利に、幽利は小さく、首を横にふった。
「ねるまえだけじゃなくて、テレビ見てた時も。昨日も」
「…昨日、も」
「歯みがきのときにコップくれた時も。お昼のパンにバター塗ってる時も。その2日前に3冊目の本の375ページ読んでた時も」
頭上で目を見開き体を硬直させる鬼利には気づかないまま、じっと天井を見据えた幽利の言葉は続く。
「その前の日にそとで車の音がした時も。その前も。その3日前も。そとに行った日も。雨がふった日も。その前の雨の日も。スープのにんじんが3つだった日も。コップが欠けた日も。新しい絵本がとどいた日も。鬼利が電話してた日も。ベッドが2つになった日も。その前の、」
「っ幽利、ゆうり…!」
それ以上聞いていられなかった。
強く幽利の肩を揺さぶって震える声で呼びかけた鬼利を、幽利は瞳だけで見上げる。
深く濃い、炎を上げずに燃え上がる熾き火のような色の瞳は、焦点が合っていなかった。
「…っ…」
「…鬼利」
あらゆる最悪を想定して息を飲む鬼利を、聞いたことのない声が呼ぶ。
幽利の声にとてもよく似ていたが、幽利はこんな淡々とした話し方はしない。純粋で真っ当な子供になれる双子の弟は、こんな感情の抜け落ちた声を出さない。こんな声は。これでは、まるで。
「ねぇ、鬼利」
これではまるで、鬼利自身の声じゃないか。
「鬼利、おれ、みえるんだ」
鬼利によく似た声音で、鬼利によく似た顔をした子供が言う。
「鬼利のかんがえてること、みえるんだよ」
「…は…?」
「鬼利のことをかんがえると、わかるんだ」
呆然と幽利を見つめたまま二の句が継げない鬼利に、幽利は眉尻を下げ、困ったような笑みをぎこちなく浮かべて見せた。
鬼利は幽利の言っていることが理解出来ていた。想定していたどの最悪よりも上を行く幽利の告白に血の気が引くほど動揺していても、怜悧な脳は1つ残らずその言葉を理解した。
優秀すぎる脳は更に、大戦前に佐緒家が今“遺術”と呼ばれている技術の1つを買い上げ、当時の当主に移植したことを、その“千里眼”という技術は遺伝子レベルで作用し隔世遺伝を起こすことがあることを、それを知った文献と共に記憶から引きずり出した。だから。
「僕が考えたことが、みえる…」
聡明な鬼利には、そんな馬鹿なことを、と幽利の言葉を一笑に付すことは出来なかった。
賢明な鬼利には、それは見間違いだ、と見え透いた嘘で自分の心を守ることは出来なかった。
利巧な鬼利には、それは素晴らしいことだ、と現実から目を反らすことさえ出来なかった。
…だってこの頭はなんでもわかってしまうから。
「幽利、それは、いつから?」
「4年と118日前の、夜から」
「…そう」
空虚な声で頷いて、鬼利はそっと目を伏せた。
目を閉じてじっと考えるとぼんやり見えていたのが、目を開けていても、鬼利のことを考えると見えるようになった。声を聞くのも文字を読むのとも違う感覚で、鬼利の考えが見えた。気持ち悪がられるかもしれないと思って秘密にしていたけど、今夜もいつものように我慢して寝たけど、ベッドを抜けだした鬼利がなかなか帰ってこないから。このまま居なくなるんじゃないかと思うと怖くて、言ってしまった。
ぽつぽつと語る幽利の言葉を、鬼利は相槌を打つことすらせずにじっと聞く。起きている間は常に並行していくつも走らせていた思考は、もう全部必要なくなって、今考えていることはひとつだけだった。
鬼利にとって大切なのは幽利だけだ。何よりも大切な幽利を、自分のように歪めて汚してしまうなんて考えられない。だから願うのは一つだけだ。
どうかどうかどうかどうかどうか、あなただけは、きれいなままで。
「…鬼利」
語り終えた幽利が、いつもの声色で鬼利を呼ぶ。
血の気を失って氷のように冷たくなった鬼利の手を握り、人の考えが読める双子の弟は、祈るような仕草で指先にそっと唇を押し当てた。
「ごめんね、鬼利」
「……」
賢い鬼利には、それで十分だった。
なにをどうしたってもうとっくの昔に手遅れだったのだと理解するには、その言葉で十分だった。
「幽利」
囁くような呼びかけに、幽利が顔を上げる。
ゆっくりと目を開いて幽利と視線を合わせた鬼利は、今まで一度だって幽利には見せたことのない表情で、そっとその体から暖かな布団を剥ぎとった。
「…あれ、やってみようか」
返事を聞く前に、鬼利は想像でなく現実で、幽利の唇を塞ぐ。
今まで無垢な仮面の下でしていたように、鬼利の絶望と諦観と欲望を読み取って、その重さと深さを他の誰よりも理解した上で。
それでも嬉しそうにとろりと蕩けた双子の弟の瞳は、自分と同じ色に濁っていた。
Fin.
双子が屋敷を出てから1年と少し経った頃。
ふたりがつくった砂の城を、幽利が崩し、鬼利が踏みにじった話。
「…きり?」
まだ少し拙さの残る声に名を呼ばれ、色を失っていた鬼利の世界はかちり、とピントを合わせたように明度を取り戻した。強ばった表情を自覚して深く息を吸い、柔らかく口角を上げて見せる。
「まだ1人で眠るのが怖いの?」
「そ、そんなことない!」
ああ、よかった。
頬を染めて慌てたように叫ぶ弟にくすくすと笑いながら、鬼利は自分の作り笑いが成功したことに心底安堵した。
ちゃんと1人で眠れる、もう大丈夫だから、なんて照れのせいで大きくなった声で言い募る弟に、解った解った、と頷く。ほんの数年前まで言葉を知らず、名前もなく、家畜にも劣る環境で幽閉されていた双子の弟が、身振り手振りで懸命に鬼利の言葉を否定しようとするのに柔らかく目を細めながら。
ただ普通に弟を思う、兄の顔で。
鬼利は聡明な子供だった。
言葉を話すのも文字を覚えるのも早く、初等部に入る年の頃には大学府で学ぶ理数学の内容を理解していた。砂に水が染みるようなその理解力と、柔軟な発想、時に経験豊富な大人をも凌駕する論理的な思考力は、天才秀才と呼ばれる御曹司達を多く教育した優秀な家庭教師さえも驚かせた。
鬼利は賢明な子供だった。
自分の優秀さを知っても決して奢ること無く、自分より遥かに無知で愚鈍な大人達を侮ることもしなかった。名家の掟と当主たる父の思惑を理解していたから、結果を知っていても毒の混入された夕食を抵抗せずに食べ、彼が“部品”と呼ぶ双子の弟が幽閉された屋根裏へは、屋敷の設計図を読み込んで調べた抜け道から通った。病床にある母の憎悪と狂気を理解していたから、父の面影が残る自分の顔を見せぬよう会うのを避け、双子の弟の悲惨な現状を告げ、狂った彼女の呪詛が幼い心を蝕むのを応報と受け入れた。
鬼利は利巧な子供だった。
あのままでは凄惨を極めた環境から双子の弟を救うのが不可能ということも、自分が父やその側近を排して家の実権を握ってからでは遅すぎることも解っていた。国と家の利益を最大化する機械として育まれた筈の心を、何でも理解できてしまう自分の脳漿と母の呪詛が歪めたことも、まだこの年齢なら修正可能なことも解っていた。父を親族を殺し、同年代のよく似た双子を身代わりに殺し、厳しくも面倒を見てくれた使用人を殺し、罪を着せた母を殺しその親族を貶め、考え得ることは全て考え使えるものは全て使い自分の年齢さえ利用して、作り上げたこの安寧が酷く歪であることも全て解っていた。
それを可能にしたこの感情が、愛と呼ぶにはあまりに深く重く穢れていることも。
「幽利、おいで」
驚かせないように努めて柔らかい声を出したつもりだったが、ソファの隅に座ってこくりこくりと船を漕いでいた幽利は、それを聞いて弾かれたように顔を上げた。
「あっ、きり、ごめんなさ、あの、ごめっんなさい、きり」
「いいんだよ。大丈夫。髪を乾かさないとね」
澄んだ橙色の瞳を見開いて顔を強ばらせる幽利の頭をそっと撫で、鬼利は軽く腰を屈めて幽利と視線を合わせながらにっこりと笑う。まだ不安そうに、何かとんでもない間違いを冒してしまったように狼狽える幽利の肩を撫でながら、細い体から強張りが取れるまで柔らかい声で大丈夫。いいんだよ。と何度も繰り返す。
ベッド以外の所でうたた寝をしただけで、髪を乾かさずにいただけで、それを鬼利に指摘させたというただそれだけで、幽利はまるでこの世の終わりのような顔をする。
今許されている全てのことが身に余る幸福なのに、身の程知らずにもそれに甘えてしまったと、普通の人間の、子供の扱いをされただけで、首に刃物を当てられたように怯える。
「ほら、おいで。早く乾かして寝ようね」
「うん。うん」
やっと強張りが解け、ぎこちなくも笑顔を作って頷く幽利の手を引いて洗面台に向かいながら、鬼利はそっと表情を消して家を出たあの夜を思い出していた。毒に冒されてのたうち回る父や親族や使用人の死に様は、今でも焼き付けたように鮮明に脳裏に蘇る。
…ああ、もっと苦しめて殺せばよかった。
「熱くない?」
「うん、へいき。大丈夫」
こくこくと頷く幽利にドライヤーを当ててやりながら、鬼利は脳裏の凄惨な想像を打ち消してそう、と微笑んだ。幽利の頭で半分以上隠れているが、洗面台の鏡がある今、どんなタイミングで自分の顔が鏡越しに幽利に見られるか分からないからだ。
表情は完璧でも、内心が少しでも瞳に出てしまったら、幽利がそれに気づいてしまうかもしれない。鞭で打たれ、痛覚を失ってからは水桶に沈められながら叩き込まれた自分の作り笑顔の精度を、鬼利は決して過信しない。
「綺麗だね。ちゃんと洗えてるよ」
「ほんと?後ろも?」
「うん。上手になったね、幽利。いい子だね」
「いいこ…?」
「そうだよ。ちゃんと自分で綺麗に髪を洗えるようになったんだから、幽利はとてもいい子だよ」
首を傾けて鏡越しに目を合わせながら褒めると、見つめる幽利の目尻が嬉しそうにふにゃりと下がる。それにつられて自然と微笑みながら、鬼利はドライヤーを持ち替えた。
成果を褒められて喜ぶ幽利の、純粋で清らかな感性が心底愛おしい。賛辞を受け入れられず、不安そうな目でぎこちなく笑っていた頃を思えば尚更だった。十分な栄養のお陰でさらさらと指通りのいい髪も、首筋を撫でる少し伸びた毛先にくすぐったそうにする仕草も、自分と同じ型のパジャマがまだ大きい細い体も、全部。
全部。
「はい、おしまい」
「ありがとう、鬼利」
「どういたしまして」
きちんと頭を下げた幽利に頷きながら、鬼利は一歩後ろに下がった。いつもなら幽利に歯ブラシを差し出してやる所だが、今日は敢えてそうせず、自分の髪を乾かすためにドライヤーを持ち直す。
風呂に入り、髪を乾かして歯を磨くのが幽利の中で習慣になるよう、鬼利は務めてきた。いずれ鬼利の手助けが無くても普通の生活が出来るように。ひとりでも生きていけるように。
邪魔にならないようにと脇に避けた幽利は、鬼利が手櫛で髪を梳くのをどこか所在なさ気にちらちらと伺っている。その手が何か言いたげにシャツの裾を握るのを横目にして、鬼利は心の中だけで小さく笑った。
「…き、鬼利っ」
ああ、まだ自主的に動くには早かったかと、歯ブラシに伸ばしかけた手を、幽利の小さな声が止める。
「どうしたの?」
「え、っと…あの…鬼利の…」
「僕の?」
「う、…鬼利の…あ…」
俯いたままもごもごと言葉をつっかえさせる幽利を、鬼利はドライヤーを下げて待った。幽利がちゃんと自分で考えて組み立てた言葉を言えるまで、辛抱強く。
聡明で賢明で利巧な鬼利には、幽利が何を言いたいのかなんて容易く予想がついていたけれど、すぅ、と息を吸い込んでから発せられた言葉に、幽利にも解るよう少し驚いて見せた。
「鬼利の、かみ…かわかして、みても、いい?」
「…幽利がしてくれるの?」
「うん、…うん」
機嫌を損ねないよう人形のように固まるのではなく、言いなりになるのでもなく、自主的に考えて行動することがとてもとても良いことだと、幽利に伝わるように。予想を裏切り期待以上のことをした時の他者の少しの驚きと感心が、幽利自身にも喜びを生むと学ばせ、自主性を育む為に。
「じゃあ、お願いしようかな」
「うんっ」
「疲れたら言うんだよ。途中でもいいからね」
「うん、大丈夫」
差し出したドライヤーを受け取り、いそいそと自分の背後に回りこむ幽利を鏡越しに眺めながら、鬼利は柔らかく目を細めた。
教えたことは無いが、幽利はドライヤーのスイッチを入れ、適切な距離を保って鬼利の髪にドライヤーを当てている。鬼利がいつもしているように髪を梳きながら、熱くないかと聞く。
鬼利がやっているのを見て覚えたのだろう。なにせ幽利の記憶力は鬼利をも凌ぐのだ。今までは記憶できていても様々な経験や情報が足りず、自分の言動にそれを反映させるのは難しいようだったが、もうその心配も無いようだ。鬼利の双子の弟なのだから地頭は悪くない。これからこうして色々なことを覚え、そのうち鬼利がいなくても身の回りのことが出来るようになるだろう。
それはとてもいいことだ。まだトラウマは多く残っているし、その所為で幽利の自己評価は異常に低いが、これからゆっくりと折り合いをつけていけばいい。上手く行けば中等部は厳しいが、高等部からは教育機関に通えるかもしれない。それまでの履修内容は鬼利が十分に教えられるし、金も人脈も十分にある。腕のいいカウンセラーを見つけて忌まわしい記憶を封印し、それが蘇らないよう兄としてサポートをする。環境を整えるのは鬼利の役目だ。そうすれば。
幽利はごく普通の子供として学校に通い、友達を作り、年頃になって恋のひとつでもして、普通の幸せな家庭を築くだろう。毒を食らうことも呪詛を聞くこともなく、普通の、ただ普通の幸せを得る。邪魔なものは全て幽利の分まで鬼利が背負えばいい。
それはとてもいいことだ。
「鬼利、かわいた?」
「うん、もういいよ」
「あつくなかった?」
「大丈夫。幽利は上手だね。これなら今度からは自分で乾かせるかな?」
「うん、できる!」
「すごいね、幽利は。これならきっと…」
ドライヤーを引き取って代わりに歯ブラシを手渡しながら、鬼利は嬉しそうに目を輝かせる幽利の頬をそっと撫でた。
「…すぐに、何でも自分で出来るようになるね」
それはとても、いいことだ。
柔らかくスプリングが沈むベッドに幽利を寝かせ、鬼利は埃を立てないようにそっと羽毛の入った上掛けをかける。
堅く冷たい床と薄く擦り切れたタオルケットしか知らない幽利は、少し前まではこのスプリングと布団を随分と怖がっていた。鬼利が添い寝すればなんとか寝付きはするが、無意識のうちにベッドを降りてしまっては、真っ青な顔で鬼利に許しを請うたものだ。
今はもう鬼利が添い寝する必要も無いし、夜中に堅いフローリングの上で体を丸めて眠ることもない。主寝室のダブルベットは鬼利がホテル側に頼み、少し前にセミシングルのツインに変えた。寝室を別にするのは、まだもう少し先でもいいだろう。
「おやすみ、幽利」
「おやすみなさい…」
眠たげに瞬く幽利の襟元を苦しくないよう整えてやって、鬼利は暖色の間接照明に輝く幽利の髪をそっと梳いた。
いつものようにキスをしようと軽く体を屈めた瞬間、脳裏に昼間の幽利の言葉が蘇る。
――― ねぇ、鬼利。あれ、
「…おやすみ」
甘く脳髄を満たす声を振り払い、鬼利はいつものように、幽利の頬にキスを落とした。
それを合図に目を閉じる幽利から視線を反らし、表情には出さないまま、胸の内だけで自らを嘲笑う。
…幽利にとって一番邪魔なのは、この僕だ。
幾度もくりかえした言葉を確認するように反芻し、鬼利は自分のベッドに横になった。ベッドヘッドに枕を当てて背中を預け、ローチェストに乗せていた本を引き寄せると、薄暗い間接照明の中で表紙を開く。
ホテルで出される食事には毒が入っていない。夜中に高熱を出すことも、胃液が無くなるまで嘔吐することも、激痛に息が出来なくなることも無いが、体に染み付いた習慣というやつなのだろうか。未だに鬼利は長時間ベッドの上で眠れたことが無かった。
背骨を貫かれるような激痛や嘔吐感を思い出すわけでもないのに、存在しない苦痛に備えて脳が覚醒する。だから鬼利は己の体が最低限求める睡眠時間を見極め、幽利が起きる時間から逆算して眠るようにしていた。
成長期の体には悪影響が出るかもしれないが、薬の類は鬼利の体には一切効かないし、例え効いたとしても鬼利はそれを飲まないだろう。考えることも得るべき知識も山のようにあるから時間を潰すのは容易いし、眠る時間が短ければその分幽利のことを見ていられるからだ。
幽利に何かがあった時素早く対応出来ることを思えば、例えそれが軟弱な自身の体にどんな悪影響を出したとしても、浅く短い眠りは鬼利にとって好都合だった。
喉の渇きを覚えて鬼利がベッドを出たのは、真夜中を少し過ぎた頃のことだった。
電気を点ける代わりに広い窓を覆うカーテンを少し開けたリビングで、鬼利はソファに姿勢よく座り、じっとテーブルの上にある瀟洒なカップを見つめる。
橙色の瞳は確かに暖かな湯気を上げる陶磁器を映しているが、鬼利の脳にはその芳醇な香りも、素足で踏むフローリングの冷たさも、何も何も届いてはいなかった。
「……」
年齢にそぐわない憂いを帯びた瞳の奥で、鬼利は考える。記憶しているものに今日読んだ5冊の専門書から得た知識を加えた上で、深く広く考える。
鬼才天才の名を欲しいままにする脳の全てを総動員して、自らの心を殺す方法を、考える。
鬼利が幽利に抱いているのは、兄弟愛などでは無い。
賢すぎる鬼利が己の感情を自覚し名前をつけるのに、時間は掛からなかった。
知識は並みの大人以上にあったし、家柄と立場上、手段を選ばない貴族の女達に両家同意の上で強姦紛いの行為を強いられていたせいか、驚きや戸惑いも少なかったと思う。
それの名前は執着だった。それは肉欲と劣情を伴い、酷く歪んで捻れて、深く重い。
初めて幽利の存在を知った時は、双子の弟という存在に純粋に焦がれた。初恋のように清らかだったそれは、鬼利の“部品”として父に引き出された幽利を見た瞬間に、庇護欲へ変わった。膨大な屋敷の設計図や見取り図を読み漁り、探し当てた隠し通路からやっと幽利のもとに辿り着いた時には、その庇護欲は少し歪んでいた。
言葉を知らず、名前も無く、残飯を食べる幽利のもとに通い詰め、菓子を与え、名前を与え、言葉を教えるうちに、それは執着へと悪化した。劣悪な環境に知識や脳に不釣合いな幼い心では、それが取り返しの付かない所まで捻れて歪むのにも、やはり時間は掛からなかった。
鬼利にとって大切なのは幽利だけだ。大切な人をこんな醜い感情で汚すなど考えられない。だからそれを幽利に悟られないように、知識や言葉と共にひとかけらでも移ってしまわないように、細心の注意を払わなければいけない、のに。
「…あぁ」
ぽすり、と幼い体をソファの背もたれに預けて、鬼利は嘆息する。
考えることは山のようにあるのに。鬼利が不慮の事故や病気で死んでも幽利が真っ当に生きていけるような準備や、そうならなかった場合の準備、幽利のサポートや環境が整えば、鬼利が死ぬタイミングも測らなければいけない。
自分を過信せず幽利を侮らない鬼利は、幽利が自分を必要としなくなったタイミングで自殺することを決定事項としていた。鬼利が生きている限り、幽利を汚してしまう可能性があるからだ。
様々なことを考慮して死に方は病死と決めたが、これは失踪やただの自殺と違い時間がかかる。この軟弱な体ではただ死ぬのに苦労は無いが、医者を幽利を欺き通してきちんと病で死ぬ為にはそれなりの準備が要るから、この計画は他より綿密に練らなければいけない。
そうだ、幽利の為に考えることは山のようにある。自分ごときの感情にかかずらわっている時間なんて、鬼利には無い。
「…キスなんて」
すっかり冷めた紅茶で満たされたカップを両手で持ちながら、鬼利は琥珀の水面に映った自分の目を見て嘲るような笑みを浮かべる。
脳裏に蘇るのは、昼間の幽利の言葉。
ニュースの合間に流れたCMの中で、舌を絡めるキスをする男女を見た幽利が言った、何気ない一言。
――― ねぇ、鬼利。あれ、
――― あれ、やってみたい。
あの柔らかな唇を塞いで震える舌を絡めとる想像など、何年も前から幾度となくしてきた筈だ。
なのに、あんな言葉に動揺するなんて。幽利には見えない脳の中でだけの行為だと理解している癖に、浅ましくも僅かに期待さえするなんて。
ああ。
「…しねばいいのに」
執着を滲ませる橙色の瞳に侮蔑を込めて吐き捨て、鬼利は一息にカップの中身を飲み干した。
ポットとカップを洗って片付けてしまってから軽く口を濯いで、鬼利は出た時と同じくそっと寝室に戻る。
寝返りを打ったのか、幽利は布団に顔を埋めるような格好で淡い明かりに背を向けていた。その姿に小さく苦笑して、鬼利は足音を忍ばせて幽利のベッドに歩み寄る。
息苦しいだろうと口元を覆う上掛けに手を伸ばし、鬼利が指を掛けた瞬間。それは鬼利の指を振り払う勢いで幽利の頭から剥ぎ取られた。
「…ゆ、うり?」
「鬼利…っ」
驚きに軽く目を見開いた鬼利を、内側から布団を引き下げた幽利が涙に滲んだ声で呼ぶ。きり、きり、と拙い声で、縋るように。
「大丈夫、僕はここにいるよ」
…馬鹿が。
優しく幽利に呼びかけ、そっと布団の上から抱きしめてやりながら、鬼利は優しい微笑みを貼り付けた顔の下で吐き捨てる。
幽利はいつから起きていたのだろう。鬼利が戻るのをどれだけ待ったのだろう。どれだけ心細かったか。不安だったか。喉の渇きを癒やす為にベッドを離れたのも、痛みを感じない体の為に紅茶が冷めるのを待ったのも、どれもこれも軽率な行動だった。
「ね、幽利。ここにいるからね」
「…っ…」
背中をとんとん、と優しく叩きながら安心させる為に囁いた言葉に、だが幽利はいつものように頷かなかった。細い指がシーツを握りしめるのを見て、鬼利は僅かに眉を顰める。
「…きり…ここにいる…?」
「いるよ。どうして?」
唐突な幽利の言葉に様々な憶測や感情が一瞬にして鬼利の脳裏を埋めたが、鬼利はそれらを全て一掃して即答した。その言葉通りに、当然じゃないか、何故そんなことを聞くんだ、という顔を作って。
「…きり、じゃま…だって」
「邪魔?」
腕の中でそろりと布団から覗いた幽利の目が、涙の膜を張ってゆらゆらと揺れる。
暖色の明かりのせいかいつもよりも濃く、熾火のような色をしたそれを見つめて、鬼利は自分の記憶を探る。昨日まで遡って思い返してみるが、独り言でも「邪魔」という言葉は使っていなかった。
だから、鬼利は判断した。柔らかく笑って幽利の頭を撫でながら、双子の弟が夢と現実を混同しているのだと、他の可能性を考えもせずに。
「そうか、怖い夢を見たんだね」
「…ゆめ」
「だって、邪魔だ、なんて僕は幽利に言ってないよ。思ったこともない」
「……」
胸元に抱き寄せた幽利をあやすようにゆっくりと体を前後に揺すりながら、鬼利はいつものように、幽利が落ち着くのを待った。冷えた自分の指先が幽利の体温を奪ってしまわないよう気をつけながら。
幽利を抱く鬼利の腕が痺れ始めた頃、拙い声が呟いた。
「…でも……だって、」
「うん?」
腕の中の幽利の瞳は涙の膜が張り、相変わらず不安に揺れていたが、その言葉は強い確信を持って紡がれた。
「…ねるまえ、だったのに」
「え?」
「まだ、ねむってなかった。キスしてくれた、ときだったから」
瞬時に記憶を引き出した鬼利の頭から、ざっと音を立てて血の気が引いた。
確かに心の中だけで思ったのに。まさか無意識のうちに声に。そんな筈は。まさか。まさかまさか。
「…それは、今日?」
「……」
強靭な精神力を総動員して平静な声で問うた鬼利に、幽利は小さく、首を横にふった。
「ねるまえだけじゃなくて、テレビ見てた時も。昨日も」
「…昨日、も」
「歯みがきのときにコップくれた時も。お昼のパンにバター塗ってる時も。その2日前に3冊目の本の375ページ読んでた時も」
頭上で目を見開き体を硬直させる鬼利には気づかないまま、じっと天井を見据えた幽利の言葉は続く。
「その前の日にそとで車の音がした時も。その前も。その3日前も。そとに行った日も。雨がふった日も。その前の雨の日も。スープのにんじんが3つだった日も。コップが欠けた日も。新しい絵本がとどいた日も。鬼利が電話してた日も。ベッドが2つになった日も。その前の、」
「っ幽利、ゆうり…!」
それ以上聞いていられなかった。
強く幽利の肩を揺さぶって震える声で呼びかけた鬼利を、幽利は瞳だけで見上げる。
深く濃い、炎を上げずに燃え上がる熾き火のような色の瞳は、焦点が合っていなかった。
「…っ…」
「…鬼利」
あらゆる最悪を想定して息を飲む鬼利を、聞いたことのない声が呼ぶ。
幽利の声にとてもよく似ていたが、幽利はこんな淡々とした話し方はしない。純粋で真っ当な子供になれる双子の弟は、こんな感情の抜け落ちた声を出さない。こんな声は。これでは、まるで。
「ねぇ、鬼利」
これではまるで、鬼利自身の声じゃないか。
「鬼利、おれ、みえるんだ」
鬼利によく似た声音で、鬼利によく似た顔をした子供が言う。
「鬼利のかんがえてること、みえるんだよ」
「…は…?」
「鬼利のことをかんがえると、わかるんだ」
呆然と幽利を見つめたまま二の句が継げない鬼利に、幽利は眉尻を下げ、困ったような笑みをぎこちなく浮かべて見せた。
鬼利は幽利の言っていることが理解出来ていた。想定していたどの最悪よりも上を行く幽利の告白に血の気が引くほど動揺していても、怜悧な脳は1つ残らずその言葉を理解した。
優秀すぎる脳は更に、大戦前に佐緒家が今“遺術”と呼ばれている技術の1つを買い上げ、当時の当主に移植したことを、その“千里眼”という技術は遺伝子レベルで作用し隔世遺伝を起こすことがあることを、それを知った文献と共に記憶から引きずり出した。だから。
「僕が考えたことが、みえる…」
聡明な鬼利には、そんな馬鹿なことを、と幽利の言葉を一笑に付すことは出来なかった。
賢明な鬼利には、それは見間違いだ、と見え透いた嘘で自分の心を守ることは出来なかった。
利巧な鬼利には、それは素晴らしいことだ、と現実から目を反らすことさえ出来なかった。
…だってこの頭はなんでもわかってしまうから。
「幽利、それは、いつから?」
「4年と118日前の、夜から」
「…そう」
空虚な声で頷いて、鬼利はそっと目を伏せた。
目を閉じてじっと考えるとぼんやり見えていたのが、目を開けていても、鬼利のことを考えると見えるようになった。声を聞くのも文字を読むのとも違う感覚で、鬼利の考えが見えた。気持ち悪がられるかもしれないと思って秘密にしていたけど、今夜もいつものように我慢して寝たけど、ベッドを抜けだした鬼利がなかなか帰ってこないから。このまま居なくなるんじゃないかと思うと怖くて、言ってしまった。
ぽつぽつと語る幽利の言葉を、鬼利は相槌を打つことすらせずにじっと聞く。起きている間は常に並行していくつも走らせていた思考は、もう全部必要なくなって、今考えていることはひとつだけだった。
鬼利にとって大切なのは幽利だけだ。何よりも大切な幽利を、自分のように歪めて汚してしまうなんて考えられない。だから願うのは一つだけだ。
どうかどうかどうかどうかどうか、あなただけは、きれいなままで。
「…鬼利」
語り終えた幽利が、いつもの声色で鬼利を呼ぶ。
血の気を失って氷のように冷たくなった鬼利の手を握り、人の考えが読める双子の弟は、祈るような仕草で指先にそっと唇を押し当てた。
「ごめんね、鬼利」
「……」
賢い鬼利には、それで十分だった。
なにをどうしたってもうとっくの昔に手遅れだったのだと理解するには、その言葉で十分だった。
「幽利」
囁くような呼びかけに、幽利が顔を上げる。
ゆっくりと目を開いて幽利と視線を合わせた鬼利は、今まで一度だって幽利には見せたことのない表情で、そっとその体から暖かな布団を剥ぎとった。
「…あれ、やってみようか」
返事を聞く前に、鬼利は想像でなく現実で、幽利の唇を塞ぐ。
今まで無垢な仮面の下でしていたように、鬼利の絶望と諦観と欲望を読み取って、その重さと深さを他の誰よりも理解した上で。
それでも嬉しそうにとろりと蕩けた双子の弟の瞳は、自分と同じ色に濁っていた。
Fin.
双子が屋敷を出てから1年と少し経った頃。
ふたりがつくった砂の城を、幽利が崩し、鬼利が踏みにじった話。
