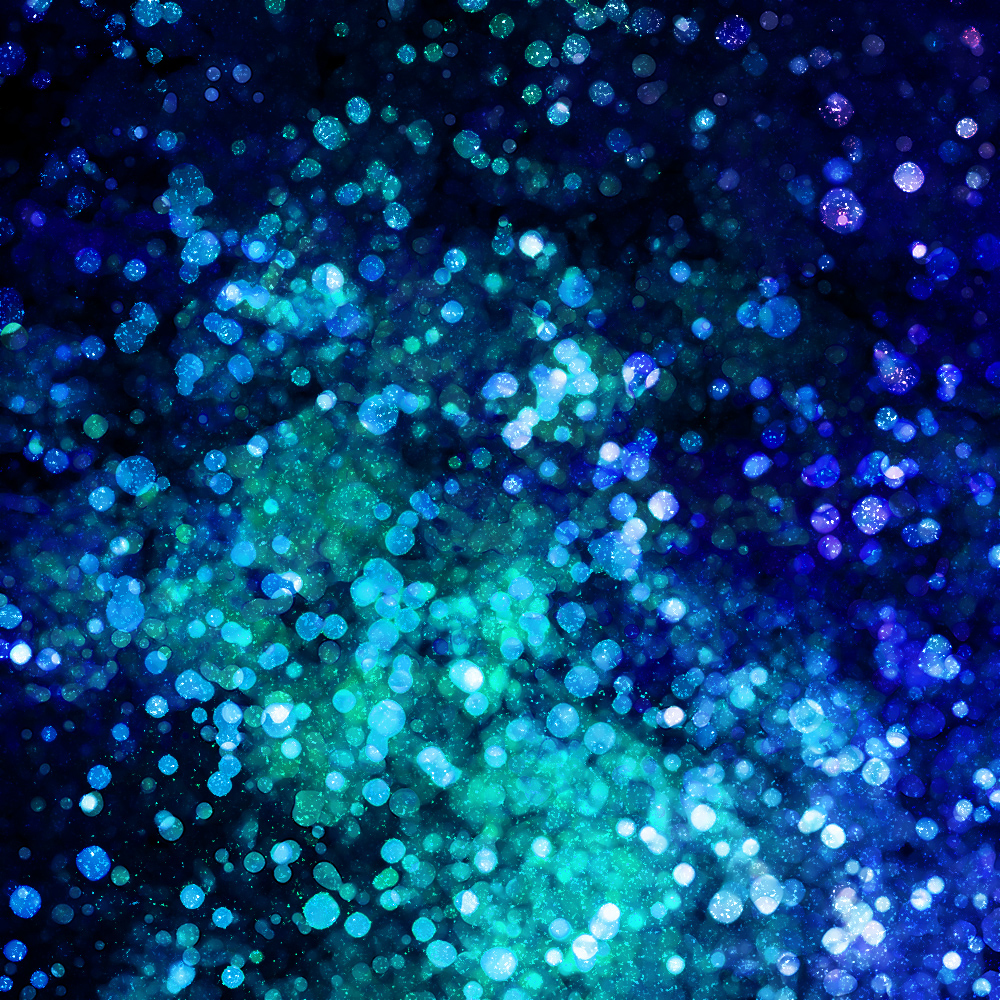
螺旋階段
「―――を出して、仁王の所に行って、武器庫の後はゴシックの野郎に…」
「……」
運転席のセピアが唱える呪文のような独り言と、あらゆる交通法を無視して走るバンへの非難のクラクションに、悦は鬱陶しそうに伏せていた目を開けた。
諸々の必要事項を忘れてタイトなスケジュールを更に秒刻みにしているセピアの、“この後の予定再確認”という名の呪文も邪魔くさいが、周囲からのクラクションやブレーキ音がそれ以上に喧しい。これではとても眠れない。
普段ならそれなりに合いの手を入れてやる所だが、タイトなスケジュールなのは同じだし、その所為で悦は若干苛ついている。完全に目の据わったセピアの相手をしてやる気にはさらさらなれず、悦は子守唄代わりに聞いていたラジオのボリュームを上げた。
―――誰かの不幸があなたの幸運を運ぶように
あなたの不幸もまた、誰かの幸運を運んでいる―――
「…ひでぇ歌」
逃避の為に聞き流していた歌詞に耳をすませればこの様だ。
溜息と共にラジオをカーステレオごと切り、悦はなんとかILL本部棟の地下駐車場に入ったバンの座席に座り直す。
「―――警備システムのハッキング頼んで、鬼利に報告書出して、仁王に…」
「…何回言うんだよ」
諸々の条件が重なった所為で、久しぶりに最悪の気分だ。
スピードを落とさないままどんどん近づいてくる駐車場の空きスペース、の壁をフロントガラス越しに眺めながら、悦は億劫そうにシートベルトを締めた。
権力者の不祥事、民族紛争、革命、新技術の争奪戦、戦争、支配者階級の死去、生誕、結婚離婚養子縁組、等々。
“ILL”に依頼が持ち込まれる理由は幾つもあるし、それらは毎日毎日飽きもせず、常に世界のどこかで行われているが、それが最も集中するのは「戦争前」だ。
つまり俗に『氷壁の八国』と一纏めにされる北方の小国の内2つが、長年の宗教抗争の末に一色即発となっている現在などは、“ILL”にとって世界中から最も歓迎されない「繁忙期」ということになる。
「あー…気持ち悪ぃ」
汗と返り血と泥に汚れた服の襟元を引っ張って肌から離しながら、悦はうんざりとした表情で、昇降機前ホールの天井を仰いだ。
国家名義で直接依頼が来ることは無いが、こういう時期の依頼主は軍部の上級士官であったり、指導者の息が掛った議員であったり、両方の国に武器を売りたい巨大軍事企業だったりと、とにかくお得意様が多い。当然依頼の難易度は高く達成条件はシビアになってくるので、絶対数の少ない弐、壱級の登録者に依頼は集中することになる。
特に悦のような「得意分野」を持つ登録者は引っ張りだこで、3日前から国を跨いでの依頼が立て続けに入っている。食事や睡眠は問題無いが、仕事と移動の連続でシャワーを浴びる暇もない程だ。
悦でこうなのだから、人間の色々な生理現象を無視できる傑はそれ以上に忙しい。もう10日は顔も見ていないし声も聞いていない。当然、SEXもしていない。
「…ッ…」
なかなか降りてこない昇降機の文字盤を見上げ、悦は苛立たしげに舌打ちをした。禄に平らな所で眠れない忙しさによるストレスに、欲求不満が拍車をかけている。
次の仕事の為にここを出るまでの猶予は、後40分。
いっそ階段で登ってやろうかと荒んだ精神状態で考え始めた頃、ようやく昇降機は降りてきた。
不快にべたつく服を引っ張りながら無駄に広い箱の中に乗り込み、他の乗客を確認することなく、自分の部屋の階のボタンと扉を閉じるボタンを殴るように叩く。幸い他の乗客は居なかったようで、音もなく閉じていく扉を眺めながら、悦は特に意味のない溜息をひとつ。
―――吐いた瞬間、鉄の箱がぐらりと揺れた。
「う、わ…ッ」
不意をつかれてバランスを崩した悦の前で、閉じようとする機械の圧力をねじ伏せた腕が扉から伸びる。
こんな無茶をしてまでこの昇降機に乗り込もうとするような馬鹿は、1人だ。
「なん、…どうしたんだよ」
「廊下から見えたから。久しぶり」
扉の閉じるボタンを軽く手の甲で叩きながら、扉が開ききる前に昇降機に乗り込んで来た傑はあっさりと答える。
10日、いや、体感では1ヵ月ぶりに見る傑は、見覚えのないグレーのシャツを着ていた。悦の倍以上の依頼を詰め込まれている筈なのに、疲労とは無縁のような、憎たらしいくらいにいつも通りの顔をして。
…いや、いつも通りではないか。
「…1時間ある?」
「いや、粘って40分」
「俺もそのくらい」
「シャワーと…準備?」
「車だから途中で幽利ンとこ寄る」
「怪我は」
「ない」
「じゃあ、25分ってとこだな」
「動物かよ…」
「そう言うなって」
苦笑交じりに悦の頭を撫でた傑の手が、そのまま後頭部を捉えて引き寄せる。
「ちょ、ここで…ッ」
「…時間短縮」
きっと自分と同じ種類の目をして甘ったるく囁く傑から、悦は顔を反らさなかった。
ベッドに行くような余裕はお互いになかった。
「ん、んっ…ふ…ぅう…っ!」
昇降機から近い悦の部屋に2人早足で駆け込み、音を立ててドアを閉めた途端、壁に背中を押し当てられた悦の唇を傑のそれが塞ぐ。
いつもより少し荒っぽいキスは、体の芯で燻っていたものを油でも注いだように燃え上がらせた。裾から入り込んで素肌を撫でる傑の手にぞくぞくと背筋を震わせながら、悦は指先まで甘く痺れた手を恋人の背中に回す。
「っぁ、は…傑…ッ」
「してんじゃねぇか、怪我」
「あぃ…っ!」
右脇腹の少し上に出来た擦過傷を目ざとく見つけた傑に、咎めるように首筋を甘噛みされ、悦は既に立っているのも辛い体を小さく強張らせた。
痛み混じりの快感でさえ今は骨まで響いてきて、首筋から胸の中心、臍の上を辿って下へ下へと頭を下げながらキスを落としていく傑を、涙の膜が張った瑠璃色で縋るように見下ろす。
「は…っぁ…すぐ、る…っ」
「…ちゃんと立ってろよ」
薄く浮いた腰骨の上にかり、と歯を立てながら、傑は弾くようにして悦のジーンズのボタンを外した。手と膝で下着ごと足首までずり下ろされたそれから引き抜いた悦の右足を、膝立ちになった自らの肩に担ぐようにして掛けさせる。
「す、傑…?…っんぁ、あぁあ!」
淫猥な期待に掠れた呼び声に答える代わりに、先端の濡れたモノを柔らかい口内に含まれて、悦は悲鳴のような嬌声と共に背を仰け反らせた。傑の肩に引っ掛けた右足がガツ、と意図せず広い背中を蹴るが、傑は気にも留めずに悦のモノに舌を絡ませる。
「ひっ…ひぁ、あぁ…っ!」
じゅぷ、じゅぷ、と音を立ててしゃぶられるともう堪らなくて、悦は頬に涙を伝わせながら傑の肩に両腕を着いた。支えがないと、もう立っていられない。
「だ、め…ぁああ…っや、で…でちゃ、う…からぁ…っッ」
「……」
「ひッぅ…っぁ、それ、やだ…はあ、ぁあ…!」
口を離すのでは無く、今にも達してしまいそうなモノの根本を指で戒めるようにされて、悦は涙声を上げる。思わず傑の肩にぎゅっと爪を立てるが、傑は出口を塞がれた悦のモノを咥えたまま、悦の左足を支えていた手を後ろへと伸ばした。
前から伝う悦の先走りと傑の唾液とを潤滑油にして、いつもより狭いナカを細くて長い指先に押し開けられ、悦の脳裏で真っ白な光が弾ける。
「はぁあ…っや、だ…ゆび、じゃ…ゃあ、ぁっ…!」
「…いきなり入れたら切れンだろ」
「ひ、ぁっ…だ…いじょぶ、だか、らっ…は、はや…く…ッ」
「…ッ…」
戒めのお陰で出さずに済んだが、とてもこれ以上は我慢出来そうに無かった。舌打ちと共に指を引き抜いて立ち上がった傑の背中に両腕を回しながら、悦はうわ言のようにはやく、はやく、とその熱を強請る。
いつになく、ともすれば爪を立てそうな力強さで太腿を持ち上げられ、ひやりとした空気が触れた奥に、熱い熱い傑の欲が触れた。じん、と電気でも流されたように骨まで痺れた腰を小さく跳ねさせ、悦は背をかき抱いた傑の肩口に顔をすり寄せる。
「すぐる、いれて…ナカに欲し…っ」
ずり、と入り口を辿るように擦れる粘膜と皮膚の境目が堪らない。焦らされているわけではなく、悦の体を気遣っての行為だと分かっていても耐えられなかった。触れている熱が欲しくて欲しくて気が狂いそうだ。
快感に身を任せて理性さえ捨て去ろうとしている今の悦に、そんな己の心情をきちんと傑に伝えるなど無理な話だから、代わりに名前を呼んだ。
離れていた期間がどれほど長く切ないものだったか。どれほどその体温を、声を欲していたか。どれほど、どれほど焦がれていたかが、少しでも伝わるように。
「すぐ…っんぅ、んン…!」
「……」
頬を掬われ、半ば強引に絡められた舌が、僅かに押し入ってきた熱に震える。
隅々まで粘膜を犯す舌が僅かに離れた隙にもう一度、小さく名前を呼んだ悦に、傑が困ったような顔で笑った。
「わぁったから。……ちょっと黙ってろ」
「っ…あ、ぁ…ッ!」
直後に深く深く貫かれ傑の背に爪を立てた悦が、ねだるような甘い声音で囁かれたその言葉を聞き分けることは、勿論不可能だった。
床を蹴って靴に無理矢理足を突っ込みながら開いたドアの先に、ほんの数秒前悦の頬にキスを落とし、先にドアを潜った傑の背中は影も形も見当たらなかった。
「おっも…」
“仕事道具”とその整備用具が詰まった黒いショルダーバッグを肩に担ぎ、悦はまだ半乾きの前髪をかき上げた。血の跡の無いミリタリーパンツのポケットから小さく震える通信端末を引っ張り出しつつ、背後で閉まったドアに鍵を掛けないまま、緩く歪曲した長い廊下を走りだす。
「なに。…あぁ、今出た。先乗って……あぁ、じゃあ表に回しといて」
どうやら上手く用事を間に合わせたらしいセピアに応えつつ、悦は端末を一度耳から離して画面に表示された時間を確認した。
遅れてはいないが、余裕も無い。
運良く来ていた昇降機に乗り込み、セピアとこの後の動きを確認しながら、武器庫がある最地下階まで降りる。
この後の仕事には運転手役の参級が同行することになっていたが、急遽その同行者は弐級のヤク中で有名なトリガーハッピーに変更されたらしい。今日も薬でトんでいるのだとしたら、殺す相手が1人増えそうだ。
「ん、すぐ行く。……幽利!」
通信を切ると同時に半開きの鉄扉を押し開けると、多種多様の武器を並べた無数の棚の奥、軍仕様の大きくて丈夫なナップザックを足元に置いた幽利が軽く手を挙げて応える。
「刃が20、55、12を5本と5、22、10が10本。狙撃と機関銃の弾が10箱ずつ。手榴弾5種を適当に、爆薬3キロと信管が予備入れて10」
「完璧。ありがと」
持ち上げようとする幽利の横合いから手を伸ばし、有に10キロを超える重いナップザックを遠心力を使って背に負いながら、悦は幽利の肩を軽く叩いた。
「この後はどちらで?」
「西側、北の。明け方くっそ寒ィらしい」
「そりゃァまた…」
気遣わしげに目隠しの上の眉を潜める幽利に軽く笑い、悦は肩紐を詰めつつ踵を返す。幽利と会うのも久しぶりだが、立ち話の時間は無い。
「お気をつけて、旦那!」
「大丈夫。じゃな」
出口まで見送ってくれた幽利に軽く手を振り、ナイフを挟んで強制的に待たせていた昇降機に乗り込む。
滑るように閉じていく扉を背に、ちっとも感触の消えない頬を乱暴に袖で拭いながら、悦は軽く舌打ちをした。
「…やっぱ舌入れりゃよかった」
Fin.
余裕の無い2人。
「……」
運転席のセピアが唱える呪文のような独り言と、あらゆる交通法を無視して走るバンへの非難のクラクションに、悦は鬱陶しそうに伏せていた目を開けた。
諸々の必要事項を忘れてタイトなスケジュールを更に秒刻みにしているセピアの、“この後の予定再確認”という名の呪文も邪魔くさいが、周囲からのクラクションやブレーキ音がそれ以上に喧しい。これではとても眠れない。
普段ならそれなりに合いの手を入れてやる所だが、タイトなスケジュールなのは同じだし、その所為で悦は若干苛ついている。完全に目の据わったセピアの相手をしてやる気にはさらさらなれず、悦は子守唄代わりに聞いていたラジオのボリュームを上げた。
―――誰かの不幸があなたの幸運を運ぶように
あなたの不幸もまた、誰かの幸運を運んでいる―――
「…ひでぇ歌」
逃避の為に聞き流していた歌詞に耳をすませればこの様だ。
溜息と共にラジオをカーステレオごと切り、悦はなんとかILL本部棟の地下駐車場に入ったバンの座席に座り直す。
「―――警備システムのハッキング頼んで、鬼利に報告書出して、仁王に…」
「…何回言うんだよ」
諸々の条件が重なった所為で、久しぶりに最悪の気分だ。
スピードを落とさないままどんどん近づいてくる駐車場の空きスペース、の壁をフロントガラス越しに眺めながら、悦は億劫そうにシートベルトを締めた。
権力者の不祥事、民族紛争、革命、新技術の争奪戦、戦争、支配者階級の死去、生誕、結婚離婚養子縁組、等々。
“ILL”に依頼が持ち込まれる理由は幾つもあるし、それらは毎日毎日飽きもせず、常に世界のどこかで行われているが、それが最も集中するのは「戦争前」だ。
つまり俗に『氷壁の八国』と一纏めにされる北方の小国の内2つが、長年の宗教抗争の末に一色即発となっている現在などは、“ILL”にとって世界中から最も歓迎されない「繁忙期」ということになる。
「あー…気持ち悪ぃ」
汗と返り血と泥に汚れた服の襟元を引っ張って肌から離しながら、悦はうんざりとした表情で、昇降機前ホールの天井を仰いだ。
国家名義で直接依頼が来ることは無いが、こういう時期の依頼主は軍部の上級士官であったり、指導者の息が掛った議員であったり、両方の国に武器を売りたい巨大軍事企業だったりと、とにかくお得意様が多い。当然依頼の難易度は高く達成条件はシビアになってくるので、絶対数の少ない弐、壱級の登録者に依頼は集中することになる。
特に悦のような「得意分野」を持つ登録者は引っ張りだこで、3日前から国を跨いでの依頼が立て続けに入っている。食事や睡眠は問題無いが、仕事と移動の連続でシャワーを浴びる暇もない程だ。
悦でこうなのだから、人間の色々な生理現象を無視できる傑はそれ以上に忙しい。もう10日は顔も見ていないし声も聞いていない。当然、SEXもしていない。
「…ッ…」
なかなか降りてこない昇降機の文字盤を見上げ、悦は苛立たしげに舌打ちをした。禄に平らな所で眠れない忙しさによるストレスに、欲求不満が拍車をかけている。
次の仕事の為にここを出るまでの猶予は、後40分。
いっそ階段で登ってやろうかと荒んだ精神状態で考え始めた頃、ようやく昇降機は降りてきた。
不快にべたつく服を引っ張りながら無駄に広い箱の中に乗り込み、他の乗客を確認することなく、自分の部屋の階のボタンと扉を閉じるボタンを殴るように叩く。幸い他の乗客は居なかったようで、音もなく閉じていく扉を眺めながら、悦は特に意味のない溜息をひとつ。
―――吐いた瞬間、鉄の箱がぐらりと揺れた。
「う、わ…ッ」
不意をつかれてバランスを崩した悦の前で、閉じようとする機械の圧力をねじ伏せた腕が扉から伸びる。
こんな無茶をしてまでこの昇降機に乗り込もうとするような馬鹿は、1人だ。
「なん、…どうしたんだよ」
「廊下から見えたから。久しぶり」
扉の閉じるボタンを軽く手の甲で叩きながら、扉が開ききる前に昇降機に乗り込んで来た傑はあっさりと答える。
10日、いや、体感では1ヵ月ぶりに見る傑は、見覚えのないグレーのシャツを着ていた。悦の倍以上の依頼を詰め込まれている筈なのに、疲労とは無縁のような、憎たらしいくらいにいつも通りの顔をして。
…いや、いつも通りではないか。
「…1時間ある?」
「いや、粘って40分」
「俺もそのくらい」
「シャワーと…準備?」
「車だから途中で幽利ンとこ寄る」
「怪我は」
「ない」
「じゃあ、25分ってとこだな」
「動物かよ…」
「そう言うなって」
苦笑交じりに悦の頭を撫でた傑の手が、そのまま後頭部を捉えて引き寄せる。
「ちょ、ここで…ッ」
「…時間短縮」
きっと自分と同じ種類の目をして甘ったるく囁く傑から、悦は顔を反らさなかった。
ベッドに行くような余裕はお互いになかった。
「ん、んっ…ふ…ぅう…っ!」
昇降機から近い悦の部屋に2人早足で駆け込み、音を立ててドアを閉めた途端、壁に背中を押し当てられた悦の唇を傑のそれが塞ぐ。
いつもより少し荒っぽいキスは、体の芯で燻っていたものを油でも注いだように燃え上がらせた。裾から入り込んで素肌を撫でる傑の手にぞくぞくと背筋を震わせながら、悦は指先まで甘く痺れた手を恋人の背中に回す。
「っぁ、は…傑…ッ」
「してんじゃねぇか、怪我」
「あぃ…っ!」
右脇腹の少し上に出来た擦過傷を目ざとく見つけた傑に、咎めるように首筋を甘噛みされ、悦は既に立っているのも辛い体を小さく強張らせた。
痛み混じりの快感でさえ今は骨まで響いてきて、首筋から胸の中心、臍の上を辿って下へ下へと頭を下げながらキスを落としていく傑を、涙の膜が張った瑠璃色で縋るように見下ろす。
「は…っぁ…すぐ、る…っ」
「…ちゃんと立ってろよ」
薄く浮いた腰骨の上にかり、と歯を立てながら、傑は弾くようにして悦のジーンズのボタンを外した。手と膝で下着ごと足首までずり下ろされたそれから引き抜いた悦の右足を、膝立ちになった自らの肩に担ぐようにして掛けさせる。
「す、傑…?…っんぁ、あぁあ!」
淫猥な期待に掠れた呼び声に答える代わりに、先端の濡れたモノを柔らかい口内に含まれて、悦は悲鳴のような嬌声と共に背を仰け反らせた。傑の肩に引っ掛けた右足がガツ、と意図せず広い背中を蹴るが、傑は気にも留めずに悦のモノに舌を絡ませる。
「ひっ…ひぁ、あぁ…っ!」
じゅぷ、じゅぷ、と音を立ててしゃぶられるともう堪らなくて、悦は頬に涙を伝わせながら傑の肩に両腕を着いた。支えがないと、もう立っていられない。
「だ、め…ぁああ…っや、で…でちゃ、う…からぁ…っッ」
「……」
「ひッぅ…っぁ、それ、やだ…はあ、ぁあ…!」
口を離すのでは無く、今にも達してしまいそうなモノの根本を指で戒めるようにされて、悦は涙声を上げる。思わず傑の肩にぎゅっと爪を立てるが、傑は出口を塞がれた悦のモノを咥えたまま、悦の左足を支えていた手を後ろへと伸ばした。
前から伝う悦の先走りと傑の唾液とを潤滑油にして、いつもより狭いナカを細くて長い指先に押し開けられ、悦の脳裏で真っ白な光が弾ける。
「はぁあ…っや、だ…ゆび、じゃ…ゃあ、ぁっ…!」
「…いきなり入れたら切れンだろ」
「ひ、ぁっ…だ…いじょぶ、だか、らっ…は、はや…く…ッ」
「…ッ…」
戒めのお陰で出さずに済んだが、とてもこれ以上は我慢出来そうに無かった。舌打ちと共に指を引き抜いて立ち上がった傑の背中に両腕を回しながら、悦はうわ言のようにはやく、はやく、とその熱を強請る。
いつになく、ともすれば爪を立てそうな力強さで太腿を持ち上げられ、ひやりとした空気が触れた奥に、熱い熱い傑の欲が触れた。じん、と電気でも流されたように骨まで痺れた腰を小さく跳ねさせ、悦は背をかき抱いた傑の肩口に顔をすり寄せる。
「すぐる、いれて…ナカに欲し…っ」
ずり、と入り口を辿るように擦れる粘膜と皮膚の境目が堪らない。焦らされているわけではなく、悦の体を気遣っての行為だと分かっていても耐えられなかった。触れている熱が欲しくて欲しくて気が狂いそうだ。
快感に身を任せて理性さえ捨て去ろうとしている今の悦に、そんな己の心情をきちんと傑に伝えるなど無理な話だから、代わりに名前を呼んだ。
離れていた期間がどれほど長く切ないものだったか。どれほどその体温を、声を欲していたか。どれほど、どれほど焦がれていたかが、少しでも伝わるように。
「すぐ…っんぅ、んン…!」
「……」
頬を掬われ、半ば強引に絡められた舌が、僅かに押し入ってきた熱に震える。
隅々まで粘膜を犯す舌が僅かに離れた隙にもう一度、小さく名前を呼んだ悦に、傑が困ったような顔で笑った。
「わぁったから。……ちょっと黙ってろ」
「っ…あ、ぁ…ッ!」
直後に深く深く貫かれ傑の背に爪を立てた悦が、ねだるような甘い声音で囁かれたその言葉を聞き分けることは、勿論不可能だった。
床を蹴って靴に無理矢理足を突っ込みながら開いたドアの先に、ほんの数秒前悦の頬にキスを落とし、先にドアを潜った傑の背中は影も形も見当たらなかった。
「おっも…」
“仕事道具”とその整備用具が詰まった黒いショルダーバッグを肩に担ぎ、悦はまだ半乾きの前髪をかき上げた。血の跡の無いミリタリーパンツのポケットから小さく震える通信端末を引っ張り出しつつ、背後で閉まったドアに鍵を掛けないまま、緩く歪曲した長い廊下を走りだす。
「なに。…あぁ、今出た。先乗って……あぁ、じゃあ表に回しといて」
どうやら上手く用事を間に合わせたらしいセピアに応えつつ、悦は端末を一度耳から離して画面に表示された時間を確認した。
遅れてはいないが、余裕も無い。
運良く来ていた昇降機に乗り込み、セピアとこの後の動きを確認しながら、武器庫がある最地下階まで降りる。
この後の仕事には運転手役の参級が同行することになっていたが、急遽その同行者は弐級のヤク中で有名なトリガーハッピーに変更されたらしい。今日も薬でトんでいるのだとしたら、殺す相手が1人増えそうだ。
「ん、すぐ行く。……幽利!」
通信を切ると同時に半開きの鉄扉を押し開けると、多種多様の武器を並べた無数の棚の奥、軍仕様の大きくて丈夫なナップザックを足元に置いた幽利が軽く手を挙げて応える。
「刃が20、55、12を5本と5、22、10が10本。狙撃と機関銃の弾が10箱ずつ。手榴弾5種を適当に、爆薬3キロと信管が予備入れて10」
「完璧。ありがと」
持ち上げようとする幽利の横合いから手を伸ばし、有に10キロを超える重いナップザックを遠心力を使って背に負いながら、悦は幽利の肩を軽く叩いた。
「この後はどちらで?」
「西側、北の。明け方くっそ寒ィらしい」
「そりゃァまた…」
気遣わしげに目隠しの上の眉を潜める幽利に軽く笑い、悦は肩紐を詰めつつ踵を返す。幽利と会うのも久しぶりだが、立ち話の時間は無い。
「お気をつけて、旦那!」
「大丈夫。じゃな」
出口まで見送ってくれた幽利に軽く手を振り、ナイフを挟んで強制的に待たせていた昇降機に乗り込む。
滑るように閉じていく扉を背に、ちっとも感触の消えない頬を乱暴に袖で拭いながら、悦は軽く舌打ちをした。
「…やっぱ舌入れりゃよかった」
Fin.
余裕の無い2人。
